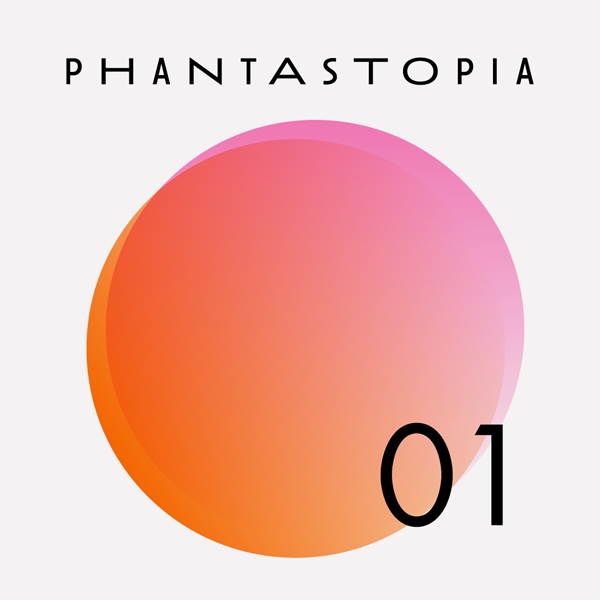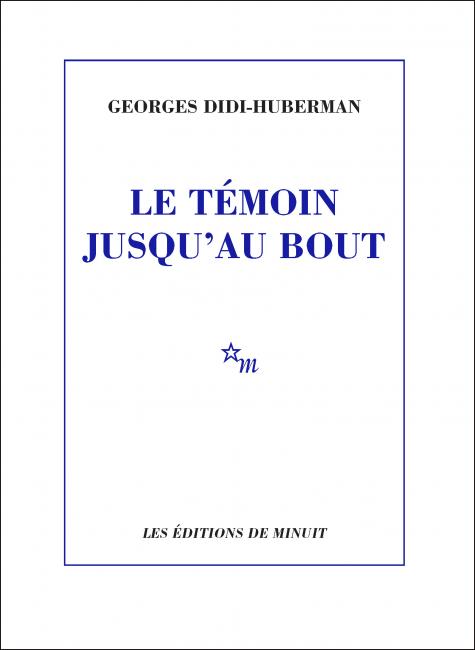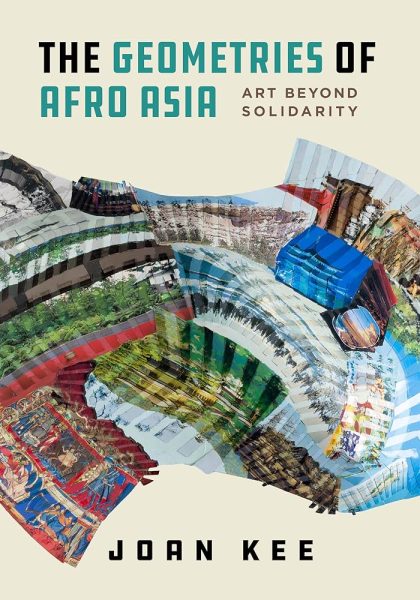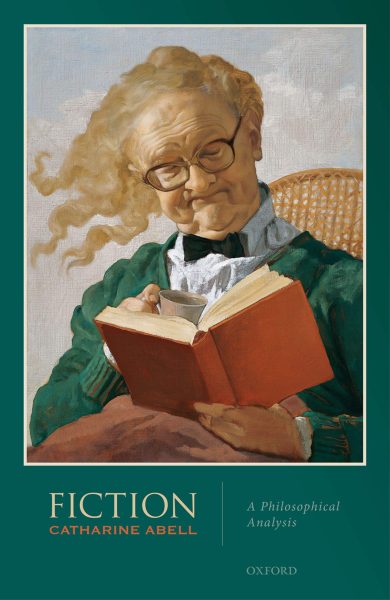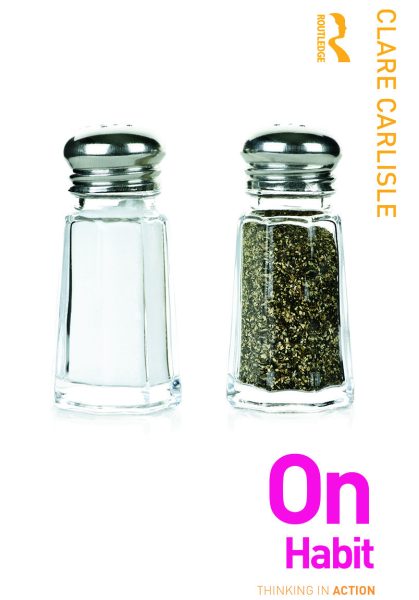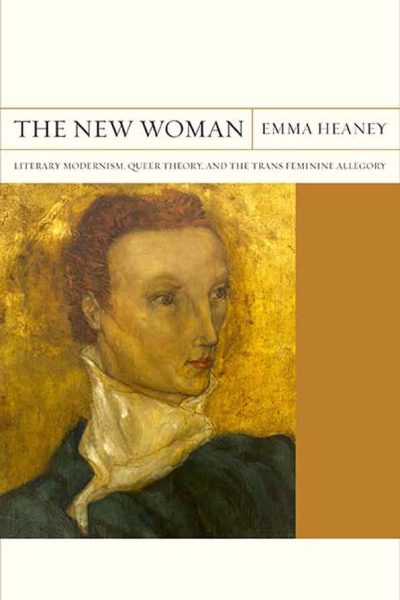フロイトの最後のテクストのひとつ、『モーセという男と一神教』のなかで宣明されるスキャンダラスなテーゼについてはよく知られていよう。モーセはユダヤ人ではなくエジプト人であったという、滑稽にさえ思われる仮説は手を変え品を変えて跡づけられ、次のようなプロットとして提示される——「エジプト人モーセ」はアメンホテプの太陽神信仰をユダヤ民族に導入したが、民族はその峻厳さと不寛容に耐え切れずかれを殺害した。この殺害の記憶は民族全体にとってトラウマ的な意味をもったがゆえに抑圧され、「エジプト人モーセ」の痕跡は歴史から抹消され、その存在は「ミディアン人モーセ」と混同される。だがその教えだけは伝承を通じて——とりわけ割礼の儀礼をとおして——生き残り、ユダヤ教が厳格な一神教として形成された(キリスト教もまた、この「抑圧されたものの回帰」の延長線上に位置づけられ解釈される)。
とはいえ、よりスキャンダラスであるように思われるのは、民族の純粋性と同一性を起源において破壊しようとする企図の効果が、ほかならぬフロイト自身に跳ね返ってくる点にある。フロイトもまたユダヤ人であるのだから。〈父〉の殺害とその記憶の執拗な残存を中心的なモティーフとするこのテクストは、いうまでもなく、ナチスによる迫害、つまり精神分析の〈父〉と知の危機を前にして編まれたものであり(第一論文の執筆がはじめられたのは1934年、第三論文が書き上げられたのはロンドン亡命後の1938年、その間にオーストリア併合が断行されたのだった)、さらには父ヤーコプとのアンビヴァレントな関係をも暗に含み込む、すぐれて「自伝的」な書物といえる。このように、自己言及的あるいは自己脱構築的とさえいえる『モーセと一神教』は、まさにフロイトが自分自身に症状を読み込みながら、その同じ場所に歴史の徴候を読解する試みであり、「歴史的真理」への賭けにほかならないのだった。
本稿がとりあげるジョルジュ・ディディ゠ユベルマン『最後までの証人』(2022年)[1]において読まれるのは、フロイトの同時代、迫害のさなかにあって、同じくみずからの症状を歴史の徴候として読解してやまなかった文献学者ヴィクトール・クレンペラー(1881-1960)である。ユダヤ教ラビの父のもとで育ち、やがて兄弟とともにプロテスタントに改宗したクレンペラーは、ナチスの反ユダヤ人政策が拡大、激化するなかでも亡命の途を選ぶことなく、妻エファとともにドレスデンにとどまった。「アーリア人」エファとのいわゆる「混合婚」であったため、クレンペラーは強制収容所への移送をかろうじて免れ、拘禁や家宅捜索を幾度も受けながら、いままさに自分の身に起きていることを日記に書きつけてゆく。ナチスのプロパガンダに呑み込まれる人々の言語使用、振る舞い、そして自身が被ったさまざま感情や出来事を詳細にわたり綴った記録をもとにして、戦後、クレンペラーは『LTI——ある文献学者の手記』(1947年)という著作を発表する[2]。「LTI」とはLingua Tertii Imperii、すなわち「第三帝国の言語」を意味するラテン語の略号である(ディディ゠ユベルマンはこのタイトル自体に、クレンペラーが時代にたいして保持しつづけた「距離」を読み取っている[p. 40-41])。クレンペラーの日記はかれの没後、そして冷戦終結後の1995年、『わたしは最後まで証言する(Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten)』というタイトルで出版され[3]、刊行後の一年間に12万5000部が売れ、ベストセラーとなった(フランス語訳は2000年に出版された)[4]。本稿が紹介を試みるディディ゠ユベルマンの小著のタイトルは、もちろん、このクレンペラーの日記から着想されたものである。
およそ「「型にはまった」文体」で「いかなるパトスも見出せない」(p. 28)とみなし、クレンペラーの真価をとらえ損なってきた従来の研究に抗して、クレンペラーは「sensibleな証人」であり、クレンペラーのテクストとは「sensibleなエクリチュール」であるとディディ゠ユベルマンは述べている(p. 151)。さしあたり「感覚的」と訳しておくが、「感度が高い」、「敏感な」、「感性的」とも訳しうる« sensible »という語に、著者はいかなる含意を込めているのだろうか。このような問題関心のもと、本稿では、ディディ゠ユベルマンにおいて互いに重なりあう三つの論点、すなわち、感情、症状/徴候、そしてエクリチュールという論点を辿ることにしたい。
I.感情(émotion)
あるインタビューにおいてディディ゠ユベルマンは、本書は「予定されたものではなかった」と述べている[5]。クレンペラーの読解は、もともと『情動事象(Faits d’affect)』の一部として位置づけられていたが[6]、それが肥大化してひとつの独立したパートになり、別の著作、つまり本書として刊行されたという経緯がある。こうした成立事情が示すとおり、本書は「感情」や「情動」を主題とする。クレンペラーが自分自身の感情にたいして結んでいた関係と、全体主義の体制が強いるところの情動的関係とが対置され、その対立構図のなかでクレンペラーの『日記』が読みとかれてゆく。これが本書の基本的なプロットである。だが、その対立がいかなるものであるのかを確かめるよりも前に、まずここでは素朴に、感情とは何かと問うてみることから出発しよう。
感情は「「自我」の統一性に亀裂を入れる」のだとディディ゠ユベルマンはいう(p. 9)。自己の同一性に揺らぎをもたらし、「世界の織地のうちにニュアンスや襞をつくりだす」もの、それが感情である。本書の冒頭では、感情にまつわるディディ゠ユベルマンの基本的な問題構成が端的に、また事柄に相応した注意深さをもって語られ、実質的にはそれが三つ目の章以降でクレンペラーを読解してゆく作業の理論的な土台となる。よって、感情がもたらす「ニュアンス」とはいかなるものの謂いであるのかを、その行論に即して簡潔に示すことにまずは注力しよう。以下は最初の章の冒頭から数えて二番目の段落の全体である。
しばしば感情は、迸りによって、身振りによって表出する。けれども感情はその背後に、ほかの多くの起伏、ほかの多くの裂け目や風景を、要するに、ほかのさまざまな情動の状態が並び立つ森の全体を垣間見せもする。わたしは怒っている、けれども、あるひとを前にして机をこぶしで叩いてみせても、その人物へのわたしの愛情や敬意はつねにそこにあって、変わることがない。わたしの苛立った身振りの奥深くに、多くのものが引き退いている——しかし、それでもなお現前し、効力を失わないでいる。ひとつの感情とは、口にはしないすべてのことやあらゆる機微を負っている発話のようなものなのだろう。だから、一つひとつの「情動事象」には、少なくとも二つの意味が、二つの感情がある。〈けれども〉という対抗モティーフあるいは対立する身振りを絶えず呼び起こすという点に、感情の豊饒さが——こういってよければ、感情の自由の分け前が——あるのだ。わたしたちを内的に分ちあい引き裂く、だが密かにであれ明らかにであれ、だれかに差し向けられもする、〈けれども〉。だれかを非難する、けれどもかれには密かに称賛の念をいだいている。称賛しているけれども、口にされざる競争意識や攻撃性のスペクトルが浮かび上がる。あからさまな喜びを示す、けれども恐怖で胸が張り裂けそうだ。恐れを感じる、けれどもしゃあしゃあと挑んでみせる。羞恥に顔を赤らめる、けれども婀娜な身振りをわずかに示す。絶望する、けれどもおのれの欲望の線を執拗に辿りつづける。(p. 10. 強調は原文による。)
ここに描かれているのは、日常的な経験に照らしても瞬時に納得のゆくことがらではないだろうか。わたしたちがある対象にかんしてもつ情動的な経験(「情動事象」)の全体を、ひとつの感情に還元することはできない(だれかに愛着をもつことは、すでにいくぶんの憎しみを胚胎しているし、その逆もまた然りである)。感情は、心身が単一の状態であるのを許さないほどに、対立する別の感情(「対抗モティーフあるいは対立する身振り」)をすでに含み込んで[7]、わたしたちを突き動かし、疼きを与えては悶えさせ、耐え忍ばせる。以上の一節を注釈しながら、本書の問題設定を確認してゆこう。
(1)一読して明らかなように、ここでディディ゠ユベルマンは、感情をつねに他人との関係のなかで位置づけている。必ずしもそうとは言い切れない箇所も見受けられるが、基本的に感情が他人との関係のなかで語られ、特徴づけられていることには、たんなる例証以上の意味がある。手掛かりとなるのは、「分ちあい引き裂く」と訳した動詞« partager »である。本書の冒頭では、「感情はわたしたちを分ちあい引き裂く」(p. 9)ともいわれる。共有と分裂を同時に意味する語によってほのめかされるのは、情動的な経験が、だれかとともに揺り動かされる出来事であるだけでなく、自分自身が引き裂かれの場となることでもあるという事実にほかならない。ディディ゠ユベルマンにおいて感情とは、「わたしたちが他性を、そしてわたしたち自身が他なるものとなることを受け入れる身振り〔geste où nous acceptons l’altérité autant que notre propre altération〕」なのだ(p. 12)。
(2)第二文でいわれる「けれども〔et pourtant〕」は本書のキーワードのひとつであり、この分裂の経験を徴づけている。引用文の後半では、相対する感情を述べる二つのフレーズをつなぐ接続的表現として用いられるが、ディディ゠ユベルマンはこれを実詞化してもいる(実詞的に用いられている箇所には〈 〉を付して訳した)。この語は、「情動事象」のもつ起伏や差異、揺らぎを言わんとするものだ。
(3)この〈けれども〉と厳密に対置されるかたちで挿入されるのが、「けれどもなんてない〔pas de pourtant〕」という圧政的な情動の体制である(p. 12)。もっと口語的に、「つべこべいうな」、あるいは思いきって抹消線を引いて「それでも」と訳すべきかもしれないが、いずれにせよこの術語は、ニュアンスを欠いた独裁的な言語の秩序を意味している。アーレントの言葉を借りてディディ゠ユベルマンが言うように、「あらゆる政治的独裁が目標とする」のは、「わたしたちを無感情で無関心にさせること、つまり生成変化を奪われ、わたしたちの時間と主体化を欠いている状態にすること」である(p. 89. 強調原文)[8]。「生成変化を奪われた」感情は、「切り離された感情〔émotions disjointes〕」とも換言される(p. 29, 90)。ディディ゠ユベルマンはこれにかんして、フロイト/ラカン的な図式のなかでその機制を精神病における「排除〔forclusion〕」に重ね、複数の感情が共立する〈けれども〉を神経症の機制(抑圧されたものの回帰)に比している(p. 18-21)。「けれどもなんてない」においては、ただ一つの感情がループしつづけ、動機はほかの動機と衝突せず、主体が抵抗や摩擦を感じることはない。それは、揺り動かされることがないという意味においてつねに静的であり、そうであるがゆえに動的でありつづける怪物的な情動のありようなのだ。ディディ゠ユベルマンは、全体主義がつくりだす情動のプロセスをこのように取り出してみせている。クレンペラーの日記は、〈けれども〉と「けれどもなんてない」のあいだでつねに揺らぎながら、後者に呑み込まれかけながらも前者を死守しようと試みるプロセスとして読み解かれる。そのプロセスこそが日記を書くことにほかならないのだが、どうして書くことが、全体主義的な情動の体制への抵抗の起点(「再主体化のようなものへと自分自身の悲嘆を分岐=転進〔bifurquer〕させる」力、「想像する能力を再び見出す」ための手段[p. 92])となるのだろうか。このことを考えるうえでは、「症状/徴候」の問題へ目を向けてみなくてはならない。
II.症状/徴候(symptôme)
クレンペラーが『日記』に書きつけるもの、それは「症状」としての感情である。
「症状〔symptôme〕」は本書のなかでもっとも頻繁に使用されている語のひとつであるが、ディディ゠ユベルマンの読者には、『ヒステリーの発明』(1982年)以来ずっと独特な負荷がこの語にかけられていることはよく知られているはずだ。たとえば、『イメージの前で』(1990年)においてこの語は、「夢の作用や残存物の作用のように[……]それが生じる場に行使する部分的な裂け目や脱形象化を通して初めて現れる」、「危機的出来事、特異性、侵入」であると同時に、「意味に満ちた構造の、体系の発動」であるといわれ[9]、その多重決定性が強調される。別の箇所では、ベルゴットが死の間際にみたフェルメール《デルフトの眺望》の「面〔pan〕」[10]と同一視される。この場合symptômeとは、イコノロジー的な分析が取りこぼす、表象の領野の特異点とでもいうべきものであり、ラカン的な対象aとしての「まなざし〔regard〕」に比肩されもする。ここからは、symptômeを「症状」ではなく「徴候」として、その視覚性をしかるべく強調して翻訳する選択肢が導かれる。もっとも、本書『最後までの証人』はイメージ論を主題とするものではないが、こうした文脈をふまえることで、概念どうしが切り結ぶ関係により注意深くアプローチする余地が生まれるのではないか。本書におけるsymptômeは、イメージ論に潜在する問題構成をたえず喚起しつつも、基本的には、精神分析的なsymptôme、すなわち「症状」の意味が前景にある。その場合、「症状」を呈する分析主体とそれに解釈を与える分析家とに視点は二重化するから、感情がもたらす自我の分裂というありようとその視点はおのずと重なり合う。クレンペラーが証言するのは、このような「症状」としてのおのれの感情なのだ[11]。
八番目の章でディディ゠ユベルマンは、クレンペラーのエクリチュールそのものに焦点を絞って、「どうして自分の感情をも証言しなくてはならなかったのか」と端的に問うている(p. 76)。これにたいする回答は次のとおり——「感情は、歴史のためのほかのあらゆる資料と同じ資格をもって想起されるに値する」からである(p. 76-77)。だが、テクストやイメージと同じような歴史的価値を感情に認めるこの言明は、感情をいかに証言するかという言語の問いと軌を一にして展開される点を見逃さないでおきたい。感情を証言する言葉は、その時代の政治体制が強いる言語使用とのたえざる軋轢や混淆のなかに置かれているかぎりで、「わたしたちが思考し、触発され、行動するその仕方を結晶したもの」といえる(p. 33)。したがって、感情を証言することは、二重の証言をすることにほかならない。すなわち、「歴史のための資料」として感情を提示することであるとともに、それを語る自身の言葉を、時代の葛藤が刻印されたひとつの「症状」として告げることでもある(p. 77)。
ここで興味深いことに、感情=症状を歴史叙述の問いと結びあわせるとき、ディディ゠ユベルマンはクレンペラーの読解からいくらか横道に逸れて、これまたかれの読者にはなじみ深いアナクロニスムを原動力とする弁証法を読者に提示する。
言語の事実、情動の事実は、流れゆく持続のなかに、主体と歴史のあいだのより深い関係をめぐる、横断的でしばしばアナクロニックな、別の時間のようなものを透けて見えるようにする。(p. 77. 強調は原文による。)
「別の時間」、それは「触発された時間〔un temps affecté〕」ともいわれる(「どんな感情も触発された時間の症状にほかならない」[p. 81])。「触発された時間」とは何か。第一に、それは情動(affect)を伴う、情動を抜きにしては語れない時間であり、第二に、出来事によって変容をうけ(心身を)動かされる時間である。形式的にはこのように整理できるとしても、やはりその内実はクレンペラーのテクストに沿って跡づけなければ見えてはこないだろう。だが、そのような自明な作業をおこなうよりも、本書のなかで著者が具体化してはいない途をあえて辿ることによって、「感覚的〔 sensible〕」という語に込められた含意とその豊かさを示すことができると思われる。そこで手掛かりとなるのは、「触発された時間」といわれるとき、ルソーやジョイスともに名を挙げられる、プルーストである。
III.エクリチュール
クレンペラーの日記を「sensibleなエクリチュール」と形容するときにディディ゠ユベルマンがプルーストのことを念頭に置いていたというのは、大いにありうることだ。そのような推測は、本書でその名を挙げているという事実によるだけでなく、プルーストのテクストそのものから引き出すことができる。『消え去ったアルベルチーヌ』からの一節を証左として引用しよう。出奔したアルベルチーヌの訃報が「私」のもとに届いた直後のシークエンスで、「触発された時間」は次のように描き出される。
もはやカーテンを閉めるだけでは足りず、私はおのが記憶の目と耳を塞いで、あの日のオレンジ色の帯を見ないようにしたうえ、当時いまは亡き女に愛情をこめて接吻されていた私の両側で、木から木へと鳴き交わしていたあのすがたの見えぬ小鳥たちのさえずりを聞かないようにした。私は夕刻の木の葉の湿り気や、山なりの街道ののぼりくだりから与えられる感覚をなんとか回避しようと努めた。しかしそうした感覚はすでに私をとらえ、私を現在の瞬間から遠くへ運び去っていたものだから、アルベルチーヌが死んだという考えは、必要なだけ後退したのち充分に勢いをつけ、あらためて私を襲うのだった。ああ、二度と森にははいるまい、もう木々のあいだを散歩するようなことはすまい。だが広大な平原ならそれほど辛い目に遭うことはないのだろうか。アルベルチーヌを迎えに行くとき、あのクリックヴィルの広大な平原を何度つっ切ったことだろう、またいっしょに帰るときも何度そこを通ったことだろう。[12]
夕刻、部屋のなかの「私」には、かつてアルベルチーヌと過ごしたバルベックの地での想い出が呼び起こされる。この想起が「私」にとってひとつの出来事たりうるのは、〈かつてあった〉と〈もはやない〉とが重なりあう「似たものの認識」が、複合的な感覚としてもたらされるからである[13]。「オレンジ色の帯」が過去の光景との呼応を実感させ、それが引き金となって「小鳥たちのさえずり」、「木の葉の湿り気」、「山なりの街道ののぼりくだり」といった多様な感覚的イメージが現在のものとしてふたたび生きられる、というよりむしろ、生きるよう強いられる。ここで重要なのは、「私」が想起するのはあの日あの時とひとつに特定できる時間なのではなく、複数の時であったという点である。複数の時であるがゆえに死者はより生々しいリアリティをもって呼び起こされ、そのリアリティの強さゆえにアルベルチーヌは「無数のアルベルチーヌ」に分裂する[14]。別の時間たちが闖入してくる、その到来の場として身体があり、感情はその到来の徴なのだ。
プルーストを「感覚的なエクリチュール」[15]の範例として考えられるのは、以上にくわえて、記憶のなかでアルベルチーヌが無数の姿に分裂してゆくにつれて同じほどに「私」の自我も分裂してゆく点が、ディディ゠ユベルマンの述べていた感情の性質に合致するからである[16]。さらに、プルーストが同じ『消え去ったアルベルチーヌ』において、「印象や想念」に「症状としての価値」を与えてもいることを言い添えておこう[17]。
以上をふまえてあらためて問うなら、クレンペラーにとって、日記のなかで感情を綴ること、すなわち「感覚的なエクリチュール」がどうして全体主義の課す情動的体制への抵抗となるのだろうか。それは、感情を症状として記述することが、自分自身の分裂を護ることにひとしいからである。「絶望する、けれどもおのれの欲望の線を執拗に辿りつづける」分裂。継起する記憶のなかに甦った無数のアルベルチーヌを愛する/愛した「私」の分裂。症状を呈するひとりの人間における分析主体と分析家とのあいだの分裂。これらの分裂を宿した「感覚的なエクリチュール」が、「けれども」ということのない情動、いわば感情本来のありかたそれ自体からの断絶に抗して、「主体と歴史のあいだのより深い関係をめぐる、横断的でしばしばアナクロニックな、別の時間のようなもの」を呈示するのだ。
もっとも、ディディ゠ユベルマンは別の回答も差し出しているように思われる。その手掛かりとなるのは、拘禁のさなか紙と鉛筆をもらい受けたクレンペラーが綴った一節、「私は鉛筆をつたい、この四日間の地獄を抜け出て地上へ這い上がる」(p. 115)[18]という言葉であり、この場合、書くことそれ自体がひとつのユートピアを織りなすことにほかならない。本稿ではくわしく辿ることができなかったが、ほかにも興味深い論点は本書に数多く伏在している。とくに、ベンヤミンとの思想的呼応(p. 120-121, 147-148)や想像力(p. 92, 102-103, 114, 116, 131)といったトピックは、本書をほかの著作と並べ、ディディ゠ユベルマンの仕事を俯瞰して評価するにあたっては重要な参照点となるにちがいない。
「器具が精確さを得るためには、何よりもまず、地震計〔sismographe〕がそうであるように、敏感〔sensible〕でなくてはならない」(p. 30)。この一節を、本稿がここまで辿ってきた議論と考え併せるならば、ディディ゠ユベルマンにとって記述が「感覚的〔sensible〕」であることは——プルーストにおけるのと同じように——「精確さ」を損なうものではないのだといえよう。むろん、それは対象や文脈に依存することがらであり、無暗やたらに一般化することは慎まねばならない。だが、「精確」であるために「感覚的」でなくてはならないという要請が、かならずしも全体主義をめぐる考察に限定されるものではないのだとすれば、わたしたちは以下のアーレントの言明をよすがとして、学術的な文体の問いを洗練させてゆかなくてはならないように思われる。
強制収容所を怒りなしに描くのは「客観的」なのではなく、赦しているのである。[……]地上における地獄として収容所を描いたことは、純粋に社会学的あるいは心理学的性質の言明よりも、より「客観的」である。すなわち、その本質にとってより適切であると思う。(p. 128)[19]
註
-
[1]
Georges Didi-Huberman, Le témoin jusqu’au bout. Une lecture de Victor Klemperer, Paris, Les Éditions du Minuit, 2022. 以下、本文中の括弧内で本書のページ数を指示する。
-
[2]
Victor Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen, Berlin, Aufbau-Verlag, 1947.[ヴィクトール・クレムペラー『第三帝国の言語〈LTI〉——ある言語学者のノート』羽田洋・赤井慧爾・藤平浩之・中村元保訳、法政大学出版局、1974年。]
-
[3]
Id, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, herausgegeben von Walter Nowojski, Berlin, Aufbau-Verlag, 1995. 邦訳は1997年に刊行された縮約版に基づいている。ヴィクトール・クレンペラー『私は証言する ナチ時代の日記[1933-1945年]』小川-フンケ里美・宮崎登訳、大月書店、1999年。
-
[4]
クレンペラーの伝記的事実については、本書の記述のほかに以下も参照した。石田勇治「解説 ヴィクトール・クレンペラーとその時代」『私は証言する ナチ時代の日記[1933-1945年]』、333-352頁。
-
[5]
「librairie mollat」におけるニコラ・パタンとの対談より。« Georges Didi-Huberman – Le témoin jusqu’au bout (Medicis essais 2022) » [https://www.youtube.com/watch?v=9Sl4uHbDJLk] 最終アクセス:2024年11月2日。
-
[6]
Georges Didi-Huberman, Faits d’affects, Paris, Les Éditions de Minuit, 2023.
-
[7]
著者が好んで引き合いに出す、両性性をめぐる1908年のフロイトの論文を参照のこと。「ヒステリー性空想、ならびに両性性に対するその関係」道籏泰三訳、『フロイト全集9』岩波書店、2007年、249-250頁。
-
[8]
1937年8月17日付の日記に、クレンペラーは次のように書きつけている。「よく自分で観察したように、一般的にいってぼくには人々にたいしてほんの少しの感情しか残っていない」(p. 91)。
-
[9]
ジョルジュ・ディディ゠ユベルマン『イメージの前で——美術史の目的への問い[増補改訂版]』江澤健一郎訳、法政大学出版局、2018年、270頁、434頁。
-
[10]
プルースト『失われた時を求めて10 囚われの女Ⅰ』吉川一義訳、岩波書店(岩波文庫)、2016年、417頁。
-
[11]
ラカンにおいて「症状」とは、抑圧されたものの回帰としての「真理」にほかならない(Jacques Lacan, Écrits, Paris, 1966, p. 234)。あるいは(同じことだが)「主体の意識において抑圧されたシニフィエのシニフィアン」であり(p. 280)、「妥協〔形成〕における抑圧されたものの回帰」であるともいわれる(p. 358)。
-
[12]
プルースト『失われた時を求めて12 消え去ったアルベルチーヌ』吉川一義訳、岩波書店(岩波文庫)、2018年、146-147頁。
-
[13]
ジョルジュ・ディディ゠ユベルマン『イメージ、それでもなお──アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真』橋本一径訳、平凡社、2006年、210頁。
-
[14]
プルースト『失われた時を求めて12 消え去ったアルベルチーヌ』、142-143頁。
-
[15]
たとえば以下の研究は、メルロ゠ポンティとプルーストの比較考察をとおして、両者のスタイルを「感覚的なエクリチュール」として特徴づけている。Franck Robert, L’écriture sensible. Proust et Merleau-Ponty, Paris, Classiques Garnier, 2021.
-
[16]
同書、166-167頁。クリスチャン・ボルタンスキーを論じるエッセーにおいては、『消え去ったアルベルチーヌ』における「歴史」のミューズが言及されていた(ジョルジュ・ディディ゠ユベルマン『歴史の眼2 受苦の時間の再モンタージュ』森元庸介・松井裕美訳、ありな書房、2017年、226頁)。
-
[17]
「医者が病人の訴える不調を聞いて、それを頼りに患者の知るよしもないもっと深い病因へとたどり着こうとするのと同じく、われわれの印象や想念もまた、症状としての価値しか持たないのである」(プルースト『失われた時を求めて12 消え去ったアルベルチーヌ』、317頁)。
-
[18]
ヴィクトール・クレンペラー『私は証言する ナチ時代の日記[1933-1945年]』、166頁。
-
[19]
Hannah Arendt, « Une réponse à Eric Voegelin », trad. É. Tassin, in Les origines du totalitarisme (1951-1971), Paris, Gallimard, 2002, p. 969.[ハンナ・アーレント「エリック・フェーリンゲンへの返答」山田正行訳、『アーレント政治思想集成2——理解と政治』J・コーン編、みすず書房、2002年、246頁。]
この記事を引用する
福井有人「症状を伝達する──ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『最後までの証人 ヴィクトール・クレンペラーを読む』書評」『Phantastopia』第4号、2025年、82-91ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/temoin-jusqu-au-bout/。(2026年01月30日閲覧)