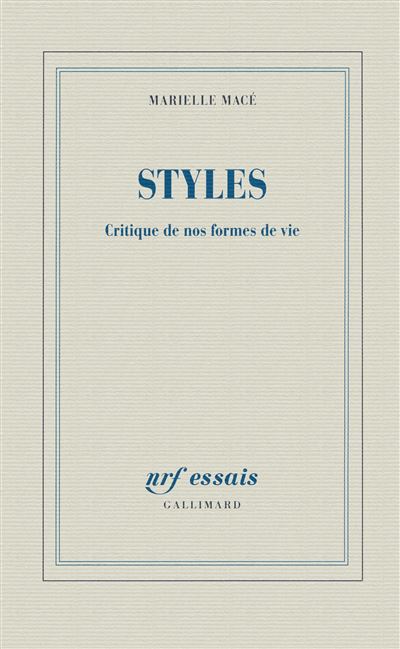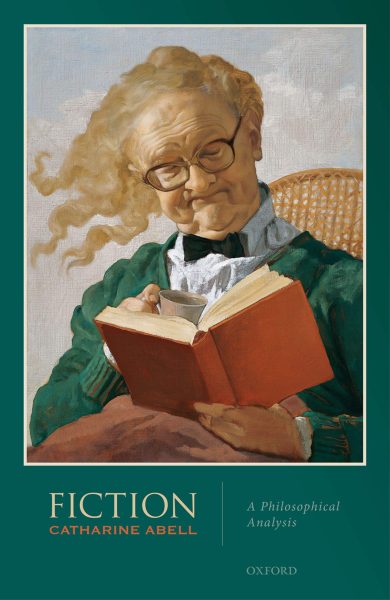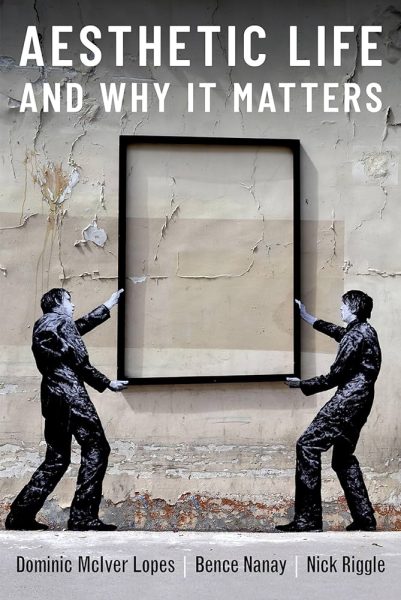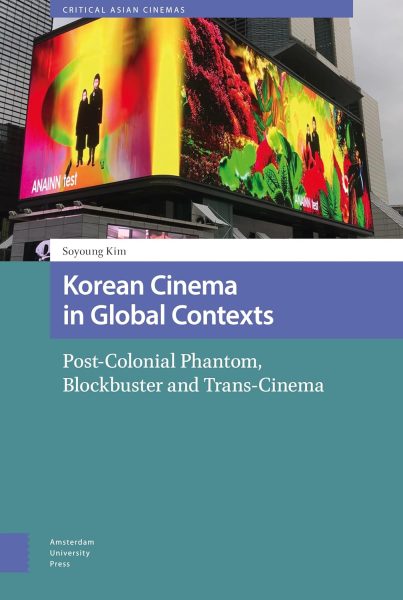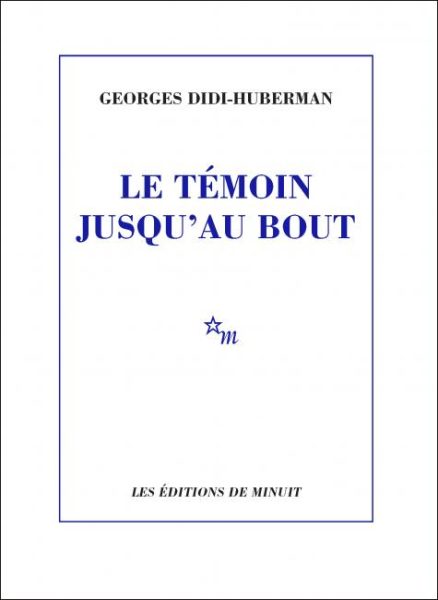p.304はじめに
東京オリンピック・パラリンピックの開催延期を決定した2020年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にむけて、政府が「新しい生活様式(new life style)」を提言したことは未だ記憶に新しい。厚生労働省がまとめるところによれば、「新しい生活様式」のうちには、可能なかぎり真正面での会話をおこなわないこと、感染拡大を助長する要素である「三密」の回避、テレワークを活用した「働き方の新しいスタイル」などが盛り込まれている[1]。提唱された「スタイル」の多くがすでに自明のものとなりはじめている現在、そもそもわたしたちは、「生活様式」や「スタイル」というものをいかに理解し、生きているのだろうか。未だ過去のものとなっていない危機から発して、「スタイル」という概念をどのようにとらえなおすことができるだp.305ろうか。あるいは、芸術や哲学は、「スタイル」に関していかなる理論的ないし実践的なパラダイムを提供しうるのだろうか。芸術にしか呈示できない「スタイル」があるとすれば、それはどのようなものだろうか。
*
本稿が取り上げるマリエル・マセの著作『(さまざまな)スタイル──わたしたちの生の形式についての批判』(2016年)[2]は、いま「スタイル」や「生き方」をとらえなおすための手掛かりと示唆に溢れている。マセは現在、社会科学高等研究院(EHESS)の指導教授を務めており、文学研究・批評理論をベースとしながら、「生存のスタイル論〔une stylistique de l’existence〕」と彼女自身が呼ぶ領域を専門としている。
初めに本書の問題設定を確認しておこう。マセの問題意識の根底にあるのは、「スタイル〔style〕」、「様態〔manière〕」、「方法〔façon〕」といった言葉をマーケティングの論理から救い出し、わたしたちの生をより繊細な仕方で理解するために不可欠な、倫理的、存在論的な語彙として彫琢することだ。それをおこなう独自の領域としてマセが提案するのが、「生存のスタイル論」である。晩年のフーコーの鍵語である「生存の美学〔une esthétique de l’existence〕」[3]へ引き寄せながら、マセがあえて「美学」という語を用いないのは、「生存のスタイル論」においては、「きらきら輝くような勝者の生や、高く評価される外観やエレガントな身体が必ずしも扱われるわけではない」からだ(p. 13)[4]。むしろマセが尊重しようとするのは、生における「不確かさ〔incertitude〕」、「生を活気づける形式〔formes qui animent la vie〕」(p. 19)、「引き受けられるべき痛み〔peine que l’on y tienne〕」(p. 24)であり、要するに、生を特異なものとしているさまざまなエレメントにほかならない。「スタイル」の基準は、美的であるか否かにはない。時に耐えがたい症状、動物たちの飛び方や住み方もまた、考察されるべき「スタイル」として数え上げらえることになる。そうした本書の方向性は、母アンリエットを亡くした直後の生活に現れる亡きひとのリズムを綴るバルト『喪の日記』についての解釈(p. 97-99)、ミショー「消える鳥」を例にとる動物のスタイルについての洞察(p. 100-101)などにおいて顕著にあらわれているといえる。
そもそも、マセは生きることをどのようにとらえているのだろうか。マセは本書の冒頭で、生の本質的な多層性を次のように叙述している。
実際、ひとつの生は、みずからの形式や様態、規則や身振り、作法や振る舞いから切りはなすことができないものなのだろう。それらは、それだけですでに主張=理念なのだ。倫理的なまなざしにとって、あらゆる存在は存在の仕方〔manière d’être〕にほかならないのではないか。そして世界とは、つまりわたしたちが共有し、意味を与えるようなこの世界は、たんに複数の個人や階級、あるいは集団へと分割されるようなものであるだけではなくて、さまざまな「スタイル」として──かくも多様な、生きることの分節法〔phrasés dep.306 vivre〕にほかならない「スタイル」として──切り分けられるものなのではないか。(p. 11. 強調は原文による)
わたしたちには、きまって口を衝いて出る言葉や特徴的な身振りがあり、それぞれのハビトゥスに結びついた「なんとなく」がある。歩行、食事、読書、恋愛、おしゃべり、休息、排せつや病との付き合い方など、それぞれの行為には一人ひとりに独自の論理や規則があることを、だれもが知っている。マセは以上のように述べることで、そうした生の豊かさや多層性──それは必ずしも喜ばしいものであるとはかぎらない──を強調している。実のところ、ここには本書を貫いている三つの重要な論点が提示されているように思われる。すなわち、(1)「みずからの形式や様態、規則や身振り、作法や振る舞いから切りはなすことができない〔inséparable de ses formes, de ses modalités, de ses régimes, de ses gestes, de ses façons, de ses allures〕」生、(2)「主張=理念〔idées〕」としての生の形式、(3)「倫理的なまなざし〔regard éthique〕」、である。わたしたちは以上の三つの論点を導きの糸としながら、本書のアプローチや意義、ならびに示唆される課題などを明らかにしていこう。
1.「その形式から切りはなすことのできない生」
第一に、「みずからの形式や様態、規則や身振り、作法や振る舞いから切りはなすことができない」生についてであるが、これはもちろん、ジョルジョ・アガンベンが自身の哲学の中心的概念である「生の形式〔forma-di-vita〕」を特徴づける際に用いている表現──「その形式から切りはなすことのできない生」──を踏まえたものである[5]。アガンベンへの思想的な依拠は、本書の副題である「わたしたちの生の形式についての批判」においてすでに示唆されている。たしかにマセは、アガンベンのテクストに関してくわしい注釈をおこなっているわけではないが、そのエッセンスを継承してはいる。まずここでは、アガンベンの議論を一瞥しておきたい。たとえば、『到来する共同体』(1990年)には次のようなパッセージが見受けられる。
自分自身のうちにとどまりつづけているのではない存在、隠れた本質として自分自身を前提しているのではない存在、偶然あるいは運命によって、それから拷問のごとき形容〔qualifications〕へと追いやられるのではなくて、さまざまに形容されるなかでみずからをさらす存在。余すところなくこのようにある存在。そのような存在は偶然的でも必然的でもなく、いわば自分の様式から不断に産み出される〔continuellement engendré par sa propre manière〕のである。[……]わたしたちに起きたり、わたしたちを基礎づけたりするのではなくて、わたしたちを産み出す様式こそが倫理的なのだ。[6]
以上を含む一連の箇所でアガンベンが注意深く取り出そうと試みているのは、わたしがわたし自身を構成するその様態である。きわめて大づかみにいうならば、自己のうちに本質が潜在していて、それが遺憾なく発揮されることでわたしが本当の意味でわたしになるという理解は、p.307アガンベンによるなら現実から乖離している。可能性が汲み尽くされて本来のわたしが現実化するわけではないというのである。わたしがわたしであるという事態は、むしろ、絶えざる自己生成として、習慣的、持続的な様態としてとらえなおされる必要がある。別の角度からいえば、わたしについてなされる「形容」を抜きにした裸のわたしなるものがどこかにあるわけではない。アガンベンのいう「生の形式」とは、さまざまな「形容」──「スタイル」や「形式」──と丸ごと一つになった、可能性としての生のことであるといえよう。
もっとも、マセはアガンベンの議論に含まれている哲学的、思想史的な文脈──たとえば、アリストテレス形而上学におけるデュナミス/エネルゲイアの理論の独自の読みかえや、ハビトゥス概念の再解釈、フランシスコ会にひとつの範型をみる「使用」の実践など[7]──を厳密に踏襲しているわけではない。「形式」、「様態」、「規則」、「身振り」、「作法」、「振る舞い」、これらはすべて、マセにおいては「スタイル」と緩やかに重なり合う同義語として理解されているにすぎない。
さらにいえば、本書全体において探究されているのは、哲学的な文脈への補助線を含みつつ、そこから社会科学や文学へと接続しうる主題や概念であり、それらのネットワークである。それゆえ本書のコーパスは多岐にわたっており、社会科学からはゴフマンやジンメル、モース、ブルデュー、レヴィ゠ストロース、カンギレム、セルトー、ラトゥールらが召喚され、哲学からはニーチェ、メルロ゠ポンティ、フーコーがしばしば援用されている(文学については後述)。要するに、本書はアガンベンの議論を踏まえつつも、それを社会学や歴史学、エコロジー思想や文学といった他領域へと一般化することによって、より具体的かつ多面的に「生の形式」を考察しようとしているといえる(そのため、やはり全体としては議論の焦点に幾分ばらつきがあることは否めない)。
2.「主張=理念」としてのスタイル
次に、「主張=理念〔idées〕」という語に注目してみたい。一つひとつのスタイルや「生の形式」が« idée »であるという表現は、本書においてしばしばみられる(cf. p. 23, 31, 33, 35, 45, 59, 63-64, 102, 114, 285, etc.)[8]。スタイルが「主張」として姿を現すのは、それが既存の制度や価値観に対する問題提起であるとともに、わたしたちによる「承認」や知的理解の変革を要求するものであるからだ。「スタイルがつねに解釈されるべきものであるのは、スタイルにおいてひとつの形式が意味を賭けにさらし、「主張=理念」を参加させ、なんらかの思考を表明しているからにほかならない」(p. 23)といわれるように、スタイルはけっして自明のものではない。「生きることの形式は、ア・プリオリに意味や価値を負うわけではない。[……]その形式は、つねに創られるべき〔à faire〕意味ないし価値なのであり、討議される意味ないし価値なのだ」(p. 283)[9]。
さらにいえば、スタイルが一個の« idée »であるとは、それがひとを触発し、模倣され、当人をこえて拡がってゆくものとなりうることを示唆している。
スタイルは物ではないし、人物のことでもない。スタイルとは、それらを特徴づける様態p.308のことであり、身を投じ、超えてゆこうとする特異な所作〔façon〕のことだ。すなわち、個人的なもの(「このような」もの)こそが、共有することへと、共通のものへと開かれてゆくのであり、それゆえ、脱所有〔expropriation〕にも開かれてゆく。そこにあって形式は、反復されるごとに持続的なものとなり、様式となるにいたる。つまり、状況に応じて或るものから別のものへと移ってゆくことのできるものとなって、どこまでも自分のものにできると同時に、どこまでも所有されることのない、非固有なもの〔impropre infiniment appropriable et jamais tout à fait approprié〕となるのだ。(p. 23)
つまり、スタイルには二つの軸があることになる。一方には、個人を形容する特異な「様態〔manière〕」としてのスタイルがあり、他方には、そうした「様態」が個人の手をはなれることで一般化され、共有しうるものとなった「様式〔modus〕」としてのスタイルがある。正確を期すならば、特異であることは「個人的であること」と等しくない。むしろ、共同性の次元へと身を開いてゆくほどに唯一無二であるスタイルこそが特異であるといわねばならない。本書の第2章でマセは、ポンジュやモース、セルトーを引きながら、スタイルにおいて本質的な一般化への傾向を「モダリティ〔modalité〕」として分析しているが、それは以上のような視座においてである。要するに、ここにはスタイルに固有の逆説的な構造が存しているのであって、特異なものは極点において共有可能なものへと転ずるのである[10]。
3.「倫理的なまなざし」──スタイルを見ようとすること
スタイルが「主張=理念」としてみずからを表明するということ、それはとりもなおさず、「主張=理念」として見られることを要求するということを意味する。そのようなスタイルは、注意深くあろうとするまなざしにしか現れてはこないのではないか。これが「倫理的なまなざし」と述べるときにマセが念頭においている事柄であろう。「ぼくは見ることを学んでいる」と書いたリルケのごとく、わたしたちもまた、スタイルについて語ろうとするならば、世界のなかで承認や注意を要求している微細なスタイルを見るすべを身に付けなければならない。
ではいかにしてか。ここにこそ、本書における文学の賭け金が置かれている。端的にいえば、文学はスタイルとそれを見る方法をともに呈示する、特権的な参照項となっている。マセは、文学的想像力によってこそスタイルの具体相が浮かび上がると考えているようだ[11]。マセは本書の冒頭で、文学を探求の「味方」あるいは「ガイド」として扱うとしているが(p. 14)、全体をとおしてみれば、文学にはたんなる「ガイド」以上の役割が担わされているように思われる。ここには、文学研究からキャリアをスタートさせたマセそのひとの自負が多分に込められているだろう。イントロダクションにあたる章から関連する記述を引いておこう。
自分自身に関していえば、わたしが文学研究に従事しているのは、生について(個人の生、共同の生、社会的生について)、まさに以下のことを理解したいと望んでいるからである。すなわち、生におけるなにものかは、みずからの形式につなぎとめられている〔quelquep.309 chose en elle tient à ses formes〕ということを。文学研究(文学を読み、探究し、そして教えること)とは、こうしたことを見ようとする行為〔un vouloir-voir cela〕であるとわたしは理解している。文学的であること。それは形式を、生をそのままに見ようとすることにほかならない。(p. 52)
たしかに、文学が本書の直接的な論及対象となるケースは数少ないが、文学なしに「生存のスタイル論」の探究はありえないということを以上のパッセージは告げている。ボードレール、ポンジュ、ナイポール、バルザック、カフカ、ヴァレリーらは、本書において、スタイルとは何かについての議論の起爆剤のような役割を果たしている。そのなかでもひと際大きな存在感を放っているのがアンリ・ミショーであり、彼は本書のなかで指示回数がもっとも多い作家のひとりである。以下では、ミショー『逃れゆくものに向きあって〔Face à ce qui se dérobe〕』(1975年)に収録された散文「折れた腕」と、それについてのマセの注釈を参照しながら、ここまでの議論を具体的に跡づけてみたい。
*
「折れた腕〔Bras cassé〕」は、ミショーが右腕を骨折し脱臼した自己経験から出発して、回復期までの状態を追跡した自己観察の書である。利き腕が使えなくなったことで、左腕によって組織される新たな自己──それは左人間と名づけられる──が浮かび上がる。ミショーはこの不器用なもう一人の自分に対する違和感を終止保っているが、それは「わたしの左腕には自分の流儀がなく、生き生きとした動きがなく、成長がなく、無力なので主張もない」[12]からだ。自分にはうまく制御できず、本来の自分を表現していないと思われる場面、だがその重苦しさを引き受けるのはどこまでも自分自身でしかないような瞬間を切り取るとき、ミショーは明晰さを失っていない。
事故の後、長い間、わたしはまだ、この左手とわたしのうちの複雑なわたしとの間に有効な関係を確立することができなかった。その左手が書く文字は、形をなさず、小学生の書く文字のようであり、動きがなく、不恰好で、無性格で、感動性のない状態にとどまることになるだろう。[13]
極度の苦痛。(これは血栓の前兆だろうか? そんなことがありうるだろうか?)何かがどこかを通りたがっている。通路を探すか、こじ開けるか、発見するかしたがっている、ここを、それからあそこと、またここを、どこでだろうか?[14]
このように淡々とした、だがそれだけに悲痛な痛みの吐露には多くの紙幅が費やされている。ミショーのパッセージを、マセは「個体化〔individuation〕」の経験として解釈し、それは「特異p.310なものの出現〔émergence d’une singularité〕」(p. 204)であると述べている[15]。彼女の記述をふまえてパラフレーズするならば、「個体化」とはほかでもないこのわたしがにわかに生成してくる出来事であり、それは自己が構成されてくる場面を言い表す特権的な語彙である。マセが述べるように、そこには「ひとり以上、ひとり未満〔plus que quelqu’un, moins que quelqu’un〕」の次元がある(p. 205)。なぜなら、ミショーのテクストにおいては、左腕を使うスタイルとしての自己はあくまで(左人間・右人間を合わせた全体的な「わたし」からすれば)一部にすぎないが、それはなおも「わたし」を表現しながらそれを超えてゆき、あるべき生の理念さえも描き始めるからだ。右腕が再び使えるようになったあと、ミショーは次のように回顧している。
一兵卒に戻った左腕については、わたしはそれを忘れようとしていた。忘れてはならなかった。愚かにもそれを訓練して、第二の右腕にしようと試みることもまた、してはいけないことだった。特に、左手を右手の模造品にすることは。[……]左手の役割は別なのだ。もしも左手が輝かしいものになれば、それは自らの存在を失うだろう、そしてその存在の方がずっと重要なのであり、左手はその存在によってひそかにわたしと関係づけられているのである。わたしは確かに左手の存在を必要としている。あまりにも活動的で、あまりにも有能な右手には(そしてその右手に関わる脳髄の地帯には)感じ取れない現実の特殊な局面とも調和してゆくために、誰でも左手の存在が必要なのである。[16]
ミショーを注釈しながら「個体化」としてのスタイルを描いてゆく一連の箇所は、本書における白眉のひとつをなしているだろう[17]。ひるがえって考えてみるならば、スタイルがひとつの主張=理念であるというのは、スタイルが、それを有する「わたし」がどんな人間であるかを形容するとともに、どうしてそれが「わたしたち」にとって必要なのかを述べるものでもあるからだ(「現実の特殊な局面と調和してゆくために、誰でも左手の存在が必要なのである〔Tout le monde a besoin [de son être] pour demeurer en harmonie avec les particuliers aspects du réel〕」)。本書において文学は、このように、スタイルをその具体相において考察するために不可欠な方法として提示されていると同時に、マセ自身がスタイルをどのように理解しているかを示す手段にもなっているといえるかもしれない。
音楽性としてのスタイル(p. 114-115)や、不定法の意義(p. 80)[18]、ヴァレリー『ドガ、ダンス、デッサン』における能動性と受動性の混交(p. 254)など、充分に展開されてはおらず、興味ぶかい示唆にとどまっているトピックは少なからず確認される。だがそれでも、本書がかくも貴重であるといえるのは、スタイルはたんなる思弁や報告のなかには存在せず、わたしたちが想像し、実際にそれを生きてみせることでしか理解できないということを明確に教えてくれるからにほかならない。以下の一節は、部分的には前著から借用されたものだが、マセ自身の主張=理念を端的に告げている。
スタイルとは、わたしたちの目の前に差し出されたたんなる一場面なのではない。それは、p.311生きもののなかに執拗に現れる足跡〔piste〕なのだ。スタイルを同定し理解するには、思考のうちでこの足跡をたどってみなければならない。足跡が指し示す方向へと、実際に向かってみなければならない。可能なものとして、あるいは不可能なものとして、スタイルを自分自身のうちで支えてみなければならない。いかなる存在のスタイルであっても、ひとを惹きつける力を有している。生きものにおけるこうした複数の表現によって〔みずからが〕とらえられるのを受けいれようとする注意、ただそれだけが、わたしたちに自分自身の様態を経験させてくれるのであり、わたしたち自身を「〔さまざまな〕スタイル」として理解することをゆるしてくれる。(p. 103)[19]
本書はコロナ・パンデミックよりも以前に書かれたものである。しかしながら、わたしたちが「生活様式」を問いなおすたびに、より一層の切迫感とアクチュアリティとをもって、本書は問いかけてくるだろう。或るものを想像することが、ほんの少しそれになることであるのならば。
註
-
[1]
「新しい生活様式の実践例」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 最終アクセス:2023年2月5日)。
-
[2]
Marielle Macé, Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard, 2016. 以下、本文中の頁数はすべて本書を指示する。
-
[3]
Michel Foucault, « une esthétique de l’existence », Dits et écrits (1954-1988), t. IV, 1980-1988, Paris, Gallimard, 1994, p. 730-735 ; Id., L’usage des plaisirs, in Œuvres, t. 2, édition publiée sous la direction de Frédéric Gros, avec la collaboration de Philippe Chevallier, Daniel Defert, Bernard E. Harcourt, Martin Rueff, Philippe Sabot et Michel Senellart, Paris, Gallimard, « Bibliothéque de la pléiade », 2015, p. 746-747.
-
[4]
マセは本書のなかで、フーコーの「生存の美学」のプロジェクトを直接相手取った批判をおこなっているわけではなく、むしろ、ピエール・アドによるフーコーへの批判に対して再批判をおこなっている。この点に関しては以下を参照のこと。Marielle Macé, Styles, op. cit., p. 223-226 ; Pierre Hadot, « Un dialogue interrompu avec Michel Foucault. Convergences et divergences », Exercices spirituels et philosophie antique, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Albin Michel, 2002, p. 305-311. さらにいえば、「生存のスタイル論」という語自体も、フーコーから借用されたものであると思われる。例えば、以下を参照のこと。Michel Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France. (1983-1984), édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric Gros, Paris, Gallimard / Seuil, 2009, p. 149.
-
[5]
Giorgio Agamben, « Forme-de-vie » [1993], Moyens sans fins, Notes sur le politique, Paris, Payot & Rivages, 2002, p. 14〔ジョルジョ・アガンベン『人権の彼方に──政治哲学ノート』高桑和巳訳、以文社、2000年、12頁〕; Id, Homo Sacer, IV, 2, L’usage des corps, traduit de l’italien par Joël Gayraud, Paris, Seuil, 2015, p. 287-288〔ジョルジョ・アガンベン『身体の使用──脱構成的可能態の理論のために』上村忠男訳、みすず書房、2016年、346頁〕.
-
[6]
Id, La communauté qui vient. théorie de la singularité quelconque, traduit de l’italien par Marilène Raiola, Paris, Seuil, 1990, p. 34-35〔ジョルジョ・アガンベン『到来する共同体[新装版]』上村忠男訳、月曜社、2015年[2012年]、41-42頁〕. 仏訳を参照し、訳文を一部変更した。
-
[7]
ジョルジョ・アガンベン『いと高き貧しさ──修道院規則と生の形式』上村忠男・太田綾子訳、みすず書房、2014年、163-193頁を参照。
-
[8]
フランシス・ポンジュ「ツバメたちのスタイルのなかに」、バルザック『歩き方の理論』などがマセの主張の典拠となっていると考えられる。以下を参照のこと。Marielle Macé, Façon de lire, manière d’être, Paris, Gallimard, 2011, p. 12-13.
-
[9]
cf. Marielle Macé, Styles, op. cit., p. 52.
-
[10]
ジョルジョ・アガンベン『イタリア的カテゴリー──詩学序説』岡田温司監訳、みすず書房、2010年、170頁を参照のこと。
-
[11]
「形式を見ようとすること〔vouloir voir les formes〕、それは別の形式を要求すること、別の形式を想像することに行き着かざるをえない」(Marielle Macé, Styles, op. cit., p. 54)。
-
[12]
Henri Michaux, Face à ce qui se dérobe, Œuvres complètes, édition établie par Raymond Bellour, avec Ysé Tran et la collaboration de Mireille Cardot, Paris, Gallimard, « Bibliothéque de la Pléiade », 3 vol. 1998-2004, t. III, 2004, p. 859〔アンリ・ミショー『逃れゆくものに向きあって』、『アンリ・ミショー全集II』小海永二訳、青土社、1986年、518頁〕.
-
[13]
Ibidi., p. 878〔同頁〕.
-
[14]
Ibid., 867〔同上、532-533頁〕.
-
[15]
「個体化」としてのスタイルという発想は、もちろんジルベール・シモンドン(とジル・ドゥルーズによるその解釈)をふまえているが、アガンベンへの依拠と同様、哲学的な厳密さはいったん脇に置かれている。Marielle Macé, Styles, op. cit., p. 203, 241 ; Gilbert Simondon, L’individuation physique et collective, Paris, Aubier, 1989 ; Id., L’individuation à la lumière des notions de formes et d’information, Grenoble, Jérôme Millon, 2005.
-
[16]
Henri Michaux, op. cit., p. 876-877〔アンリ・ミショー、前掲書、552頁〕.
-
[17]
「スタイルがここで指し示しているのは、ほかから区別される独自の作品ではなく[……]、新たなひとつの「関係性」であり、つまりは世界との、自己との関係のうちに入ってゆく新たな仕方のことなのだ」(Marielle Macé, Styles, op. cit., p. 212)。
-
[18]
不定法の意義に関しては、次著である『わたしたちの小屋』(2019年)において部分的に論じられ、実践されている。以下を参照のこと。Marielle Macé, Nos cabanes, Lagrasse, Verdier, 2019, p. 40, 96-97.
-
[19]
Marielle Macé, Façon de lire, manière d’être, op. cit., p. 14.
この記事を引用する
福井有人「「ライフスタイル」から文学的「スタイル」へ──マリエル・マセ『(さまざまな)スタイル わたしたちの生の形式についての批判』書評」『Phantastopia』第2号、2023年、303-312ページ、URL : https://phantastopia.com/2/styles-critique-de-nos-formes-de-vie/。(2025年07月16日閲覧)