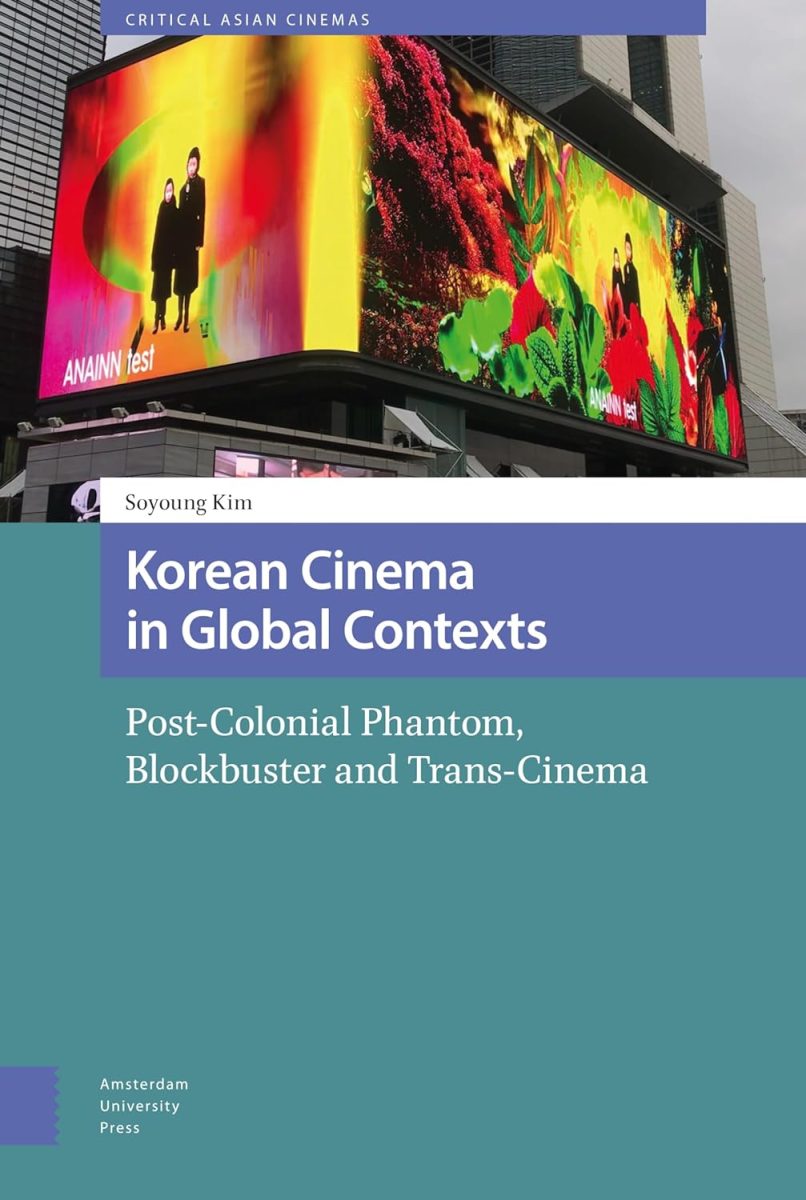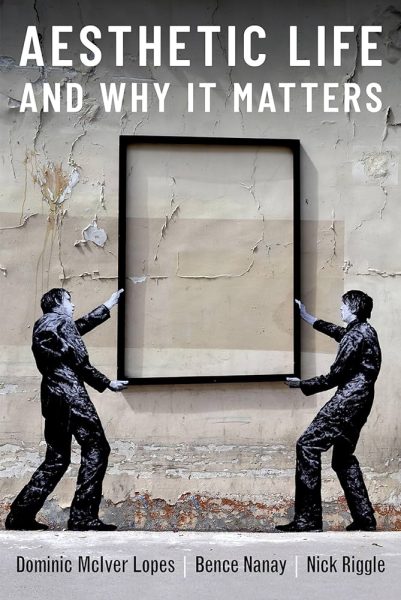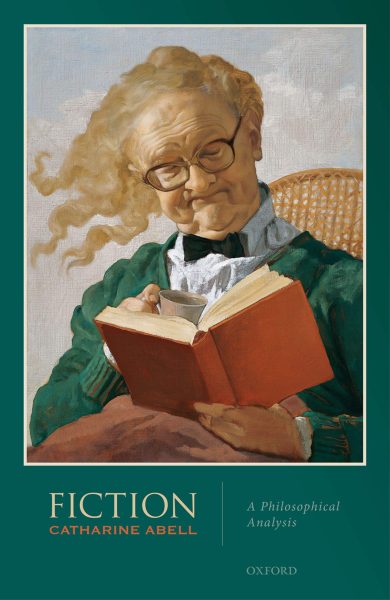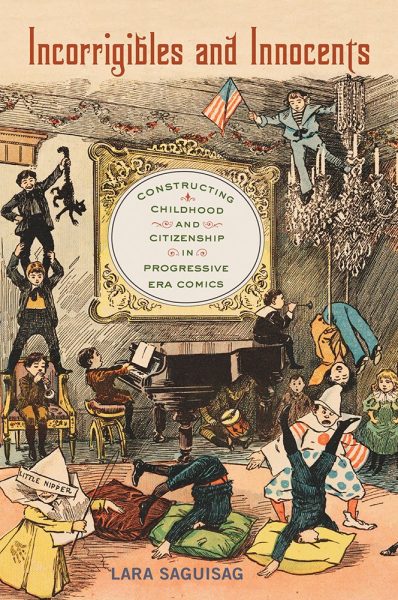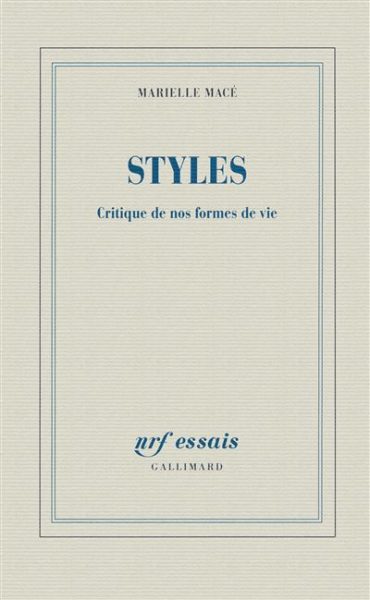2023年日本映像学会第49回⼤会で、本書の著者である⾦素榮[1] は「悲しみが私たちを連れていくところ 哀悼、場所、⼥性史」というタイトルで基調講演を行った。その際彼女が取り上げたのは、自身の学術研究ではなく、映画監督としての代表作である韓国女性史ドキュメンタリー三部作[2]であった。会場内の評者を魅了したのは、彼女の実験的な手法と女性を捉える洞察力のある視点は無論のこととして、何よりも彼女がイメージのなかで再構成を試みた、「居留/去留/巨流」「女性場/葬」「境/鏡/経/景」といった韓国語の同音異義語が織りなす縦横無尽な時空間だった。その時空間は、歴史的痕跡が構築する個人史、家族史、女性史の集合体であり、地政学的視座からみる空間が切り開く現在と未来でもある。金がこのような視座を持つようになったのは、英語圏で長い間韓国映画を研究してきた彼女の経歴と無関係ではないだろう。2003年からの最新論文を収録した本書は、彼女の「韓国映画研究史」を示す、20年にわたる韓国映画の研究成果の集大成を満喫できる一冊である。
イントロダクションでは、著者は「開(openness)」という概念を用い、韓国の西洋近代への開放に高い程度で適応した初期の韓国映画文化の歴史的・認識論的条件を説明する。すなわち、韓国歴史上の「開港」(1876-1897年)と「開化」(1897-1910年)の時代から始まった「開」という過程は、「緊迫感と危機感を即座に呼び起こしながらも、それがわずかな宙ぶらりんの希望と混ざり合ったきわめて両義的なプロセス」であった(p. 13)。また、この両儀性について、著者はそれぞれ「緊急事態(state of emergency)」と「宙づりの近代(modernity in suspense)」として説明している(p. 14)。さらに注目すべきは、ここでいう「開」のメカニズムが、初期の韓国映画から、1910年から1945年までの植民地映画、そして1945年から現在に至るまでの韓国のポストコロニアル映画を貫いていることである。しかし、多くの初期の韓国映画のフィルムが失われたなかで韓国映画に対する学問的探究を行うことは容易ではない。そこで著者は二つの理論的な枠組みを提供する。一つは、映画理論(フィルムの有無に関わらず)と知識生成のポストコロニアルな状況を検討する枠組みである。言い換えれば、「映画そのものだけでなく、その観客、テクスト(text)だけでなく、文脈(context)、そして作品(objects)だけでなく、出来事(events)」に注目する視座である(p. 16)。もう一つは、比較映画研究(comparative film studies)の枠組みである。これは地域・文化横断的な意味を持つ映画自体の特徴を鑑みて、アジア地域間やアジアを超えたトランス・ナショナルな文脈における、韓国映画、台湾映画、香港アクション映画などのアジア映画、そしてハリウッド映画との複雑な歴史的な相互関係を探求する枠組みである(p. 19)。
この二つの枠組みに基づいて、本書は「原初的な映画文化からトランス・シネマへ」と題された第1部と、「トランス・アジアの枠組みにおける韓国映画」と題された第2部から構成され、計11本の論文が収録されている。紙幅の都合上すべてに言及することは控え、いくつかのキーワードに絞って紹介していこう。
初期映画
すでに触れたように、初期映画を研究する上での最大の困難は、重要な作品のフィルムがまだ発掘されていないことである。参考資料が乏しいために幻のような歴史を再構築するには、多分野の知見を総合的に動員することが必要であろう。その優れた例として、第1章「カタストロフィの地図学 植民地以前の調査、植民地以後の吸血鬼、そして韓国近代の苦境」では、1901年に出版されたアメリカ旅行家E・バートン・ホームズ(E. Burton Holmes)の絵入り旅行記を手掛かりに、映画という近代的なメディアが京城の朝鮮人の前にどのように現れ、受け入れられたかを追跡する。興味深いことに、中国、インドネシアのように、映画の前身と考えられる伝統的な影絵芝居が存在するのとは異なり、近代以前の朝鮮にはほとんどスクリーンと関係する実践が存在しなかったため、映画を上映するために掲げられたスクリーンは、人々が公共の場に集まり、目の前で起こっている出来事を見るという新たな鑑賞方法を提供した。また、スクリーンの実践だけではなく、ほぼ同時期に開催された独立協会主催の民衆大会は、近代的なコミュニケーション形態である演説の訓練の場を提供し、社会的相互作用が働く力関係を伴うスピーチの実践も変容させた。さらに、1910 年代に登場した弁士は、これらの変化を受けてストーリーテラーとパフォーマーの伝統を再創造した啓蒙的な講師として再考することができると著者は指摘する。
ここで重要なのは、こうしたアプローチは植民地時代の朝鮮映画が現存しない状況に対応するための対策というよりも、むしろ、朝鮮映画の起源を探ることに固執する韓国の映画史家が採用してきた、植民地時代の知識生産様式に制約された、西洋の概念を援用した歴史学に対抗する戦略であるということである。また、こうした戦略の延長線上で技術革新が進み、とりわけデジタル化の台頭により生じた映画鑑賞の形態の変化を念頭において、著者は「トランス・シネマ(Trans-cinema)」という概念を提唱している。著者によると、トランス・シネマは、映画とデジタル技術を横断し、映画の制度化に伴う観客の規範化のプロセスに挑戦する不安定な混合物であり、具体的にはデジタル・シネマやネット・シネマ、地下鉄、タクシー、バスに設置されたLCDスクリーン、そして巨大な電光掲示板で流れている映像などが挙げられる。このような映画鑑賞の変容プロセスそのものに焦点を当てるアプローチは、初期の映画においても、トランス・シネマにおいても、著者の研究全体にわたって一貫して見られるものである。それは、普遍と特殊、グローバルな支配とローカルな抵抗、さらにジェンダー・ポリティクスなど、様々な問題を検討するための有効な切り口であるにちがいない。
ストップ・モーション
第3章「宙づりの近代 韓国映画におけるフェティシズムの論理」と第4章「私を「私たち」に含めないで 『ペパーミント・キャンディ』と違いの政治差異の政治学」は、どちらも映画表現のストップ・モーションに焦点を当てる。なぜストップ・モーションが注目されるかというと、多くの韓国映画の最後にはストップ・モーションがあり、物語がそこで終わるのが特徴だからである。言うまでもないが、ストップ・モーションのエンディングは、韓国映画に限ったことではない。トリュフォーの『大人は判ってくれない』(1959年)のラストシーンにおける呆然とする少年のストップ・モーションは、劇的な効果をもたらした革新的表現であり、映画史に残るエンディングであることはよく知られている。それでは、韓国映画におけるストップ・モーションにはどのような特異性があるだろうか。
第3章では『旅人は休まない』(イ・ジャンホ、1987年)と『薔薇色の人生』(キム・ホンジュン、1994年)、第4章では『ペパーミント・キャンディ』(イ・チャンドン、2000年)が取り上げられる。『旅人は休まない』におけるストップ・モーションは、理想化された過去や統一されたユートピア国家のイメージへ必ず回帰するというわけではなく、アクションを過去へ向かわせ、結果として主人公を過去に生きるようにさせるフェティシュな要素である。それに対して、『薔薇色の人生』のラストシーンで現れたストップ・モーションは、国家と歴史にかんする両義性から複数の文化的意味作用を生み出すものである(p. 67)。これにより、著者は、ストップ・モーションは「ベンヤミンが言うところの「ひらめき」に似た瞬間において崩壊し、アレゴリーへと変貌し、そして未来へと開かれた歴史とともに観客と出会うのである」(p. 68)と指摘する。
では、『ペパーミント・キャンディ』でしばしば登場するストップ・モーションはどうだろう。それについて、著者は、「冷戦の氷のような冷たさの中に幽閉され、まだ解凍されていない歴史的トラウマのような形で、ヒーローのキム・ヨンホのねじれた、悲鳴のような状況を静止させる。このストップ・モーションでは、1999年の春、1994年の夏、1987年の春、1984年の秋、1979年の春など、歴史のさまざまな瞬間が映し出され、これらの個人的・社会的トラウマが圧縮されている」と説明している(p. 87)。これらのストップ・モーションとともに展開されるのは、国家制度がその被害者を加害者に変えるというストーリーである。しかし、この映画は既存の秩序への批判と抵抗を表す芸術映画であるものの、全体主義的な国家イデオロギーを無意識的に再現しながら、「私たち」を集団的に動員するという一貫した論理によって創り出されたものであることを忘れてはならないと著者は強調する(p. 95)。
このように、ストップ・モーションは単なる映画手法ではなく、植民地主義と民族分断に続いて起こった、急激な産業資本主義的な発展という歴史を生きた人々の経験と深く関係するアレゴリーとして理解できるだろう。しかし、惜しく感じられるのは、著者によるこの重要な問題提起は、具体的な映像分析が行われないままやや観念的な議論に終始した点である。例えば『旅人は休まない』のラストシーンで突然空から降りてきた巨大な手や、子供の戸惑うような曖昧な微笑みが映り出された『薔薇色の人生』について、どのように理解すべきかについてのさらなる分析が期待される。
消えゆく⼥性たち
第2章「緊急事態におけるファンタジーのあり方 韓国映画におけるファンタズマティックな他者」と第6章「グローバル時代におけるローカル・フェミニズム圏の誕生 女性場とトランス・シネマ」はともに、1990 年代末にアジア地域に起こった韓流の台頭と並行して製作された韓国型ブロックバスターが女性キャラクターを多国籍化する戦略を採用した現象について分析している。その重要な例として、北朝鮮女性のスパイの活動を描いた『シュリ』(カン・ジェギュ、1999年)や、殺人事件を解決しようとするスイス系韓国人の検視官ソフィー・E・チャンが登場する『JSA』(パク・チャヌク、2000年)、そして香港のセシリア・チャンが韓国で働く中国の移民労働者を演じる『パイラン』(ソン・ヘソン、2001年)が挙げられる。これらの映画は、韓国で生まれ育った女性を目に見えない存在に追いやる一方で、陸軍や中央情報部、組織化されたギャング団などの男性主導のグループを動員して、ホモソーシャルな社会関係を前景化している。その後、韓国ネイティヴの女性がようやくスクリーンに戻ってきたものの、彼女たちは、『渇き』(パク・チャヌク、2009年)、『母なる証明』(ポン・ジュノ、2009年)、『ハウスメイド』(イム・サンス、2010年)においては吸血鬼、母親、ハウスメイドとして表象されている。これらの女性像は、新自由主義的なグローバリゼーションの下では、国家が社会的ケアを提供できない場合に、女性の登場人物がさまざまな形のケア労働を担わざるを得ないことを象徴している。第5章「シネマニアかシネフィリアか 映画祭とアイデンティティの問題」で論じられるとおり、スクリーン上にジェンダー不平等という構造的な症状が現れるなか、1997年に創立されたソウル国際女性映画祭をはじめとするテーマ別の映画祭は、フェミニストのウェブサイト、既存のフェミニスト出版社や新しく設立されたフェミニスト出版社、街頭抗議行動、パフォーマンスとともに、ハーバーマスの提起した公共圏が確立されていない社会において、「女性場」という代替的な公共圏を提供してくれる(p. 110)。
ここで中国人女優タン・ウェイが主演する『別れの決心』(パク・チャヌク、2022年)を想起してみよう。タン・ウェイが演じるソレは、韓国に中国から密入国者している朝鮮族であるとともに、女性のケア労働者でもある二重の社会的弱者の位置に置かれる女性である。この点を考えると、韓国の女性の不可視化が現在も変わらず続いていることに気付かされ、著者の議論は現在においても有効であると痛感した。警察官のパク・ヘイルを翻弄し、迷宮入りの恋に落ち込ませる彼女のイメージは、韓国型ブロックバスターとは一線を画すところであると思われ、その点については著者によるさらなる議論を期待したい。
トランス・アジアと比較映画研究
第9章「地政学的ファンタジー 冷戦時代の大陸物映画」では、1960年代から1970年代前半かけて製作された大陸物というジャンルが提供するアジアにかんする想像が論じられる。著者は、『荒野の鷲』(イム・グォンテク、1969年)と『鉄鎖を断ち切れ』(イ・マニ、1971年)を取り上げ、地政学的な観点で、大陸物は「満州における冷戦前の日本帝国時代を描いたものであり、反共主義の枠組みの下に設置された現代の政治システムによる地理的な封鎖、それに続くアジアにおける反共主義的な傾向、植民地主義的な感情の刺激を無意識に露呈している」(p. 181)と述べている。その上、著者はベネディクト・アンダーソンの提起した「想像の共同体」に基づいて、批判的な地政学的ファンタジー(critical geopolitical fantasy)という概念を提示する。それが、国民国家(nation-state)と国籍(nationality)の有限の境界を疑い、破壊し、超越するものに関わるものである。この示唆的な概念は、大陸物だけではなく、戦争映画やスパイ映画などのジャンルにも適用することができると思われる。なお、韓国のアクション映画の生成と越境に関しては、李英載氏の『東アジアにおけるトランス/ナショナルアクション映画研究 冷戦期日本・韓国・香港映画の男性身体・暴力・マーケット』(東京大学出版会、2016年)を合わせて読むことをお勧めする。
ほかにも金綺泳の映画に対する分析(第3章)、台湾映画『戯夢人生』(ホウ・シャオシェン、1993年)と『酔画仙』(イム・グォンテク、2002年)との比較(第7章)、初の韓流映画である『猟奇的な彼女』(クァク・ジェヨン、2001年)にかんする論点(第10章)も紹介したいが、そろそろ紙幅が尽きてしまう。最後に、本書を通読して腑に落ちない点について述べておきたい。一つは、批評と論文との境界線が曖昧な点である。本書の所々で触れられた個人的な体験や、映画祭のキュレーターとしての経験は映画が製作された当時の背景や、映画文化の状況を理解する上で役に立っているが、それは論文内容として妥当ではないと感じられる。もう一つは、本書の理論的背景が依然として欧米中心主義に基づいている点である。もちろん、これは英語圏の読者を対象として書かれた本であることに由来するものかもしれない。欧米の理論を用いて韓国映画を分析することや、その用語を用いて新しい概念を提示したことによって多くの示唆を得たこと自体は否定できないが、この理論的背景がなければ、韓国ないしアジア独自の理論的資源を活用して韓国映画を考察できないのか、という問いが浮かび上がる。その問題の答えを探ることは、評者自身の課題にさせていただこうと思う。いずれにせよ、本書は韓国映画の理論的かつ歴史的な理解を深め、その彼方を見極める画期的な著作であることは論を俟たない。
註
-
[1]
「日本映像学会第49回⼤会第三通信」に掲載された彼女の紹介は以下のようになる。映画監督、映画祭プログラム・ディレクター、映画研究者、映画批評家。韓国国⽴総合芸術⼤学校教授、トランス・アジアン・スクリーン⽂化研究所所⻑。韓国映画に関する数多くの著作があり、フランス、⽶国、ドイツなどでも客員教授を務める。2001年の国際交流基⾦による韓国映画プロジェクトにゲストとして来⽇、対談や講演を行った。プログラムディレクターとしてソウル国際⼥性映画祭を、初代共同プログラマーとして全州国際映画祭を立ち上げ、ソウル国際⼥性映画祭の国際諮問委員会のディレクターを勤めている。現在、釜⼭現代美術館「映画の環境 島、地球、ポスト・コンタクトゾーン」展⽰ディレクターを務める。主な著書に『シネ・フェミニズム ⼤衆映画の詳細に読む』(韓国語、1995年)『近代性の幽霊 ファンタスティック・コリアン・シネマ』(韓国語、2000年)『カタストロフィーの地図(韓国という映画的事態)』(韓国語、2014)、共編著に『Electronic Elsewheres: Media, Technology, and the Experience of Social Space』(ミネソタ⼤学出版, 2009年)など。⽇本語に翻訳された論⽂は、「メディア、急進的⺠主主義、そして⼥性場」(安珉花訳『情況』4(8), 2003年、142-151⾴)、「消えゆく⼥性たち──『シュリ』『JSA』『ユリョン』──韓国型ブロックバスター映画」(波潟剛訳『ユリイカ』 33 (13)、2001年11 ⽉、95-107⾴)、「ホラー ファンタスティック映画の時間戦争」(藤井たけし訳『現代思想』29(7)、2001年6⽉、158-168⾴)、「ホラー なぜファンタスティック韓国映画なのか」(同前、148-157⾴)、「宙づりの近代 韓国映画におけるフェティシズムの論理」(齋藤⼀訳『トレイシーズ 別冊 思想』1、2000年 11⽉、294-313⾴)がある。
-
[2]
『居留 南の⼥』(2000年)『恍惚境』(2003年)『本来⼥性は太陽だった 新⼥性のファーストソング』(2004年)。
この記事を引用する
韓瑩「韓国映画の彼方へ──⾦素榮『グローバルなコンテクストにおける韓国映画 ポストコロニアルの幻、ブロックバスター、トランス・シネマ』書評」『Phantastopia』第3号、2024年、99-106ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/korean-cinema-in-global-contexts/。(2024年10月22日閲覧)