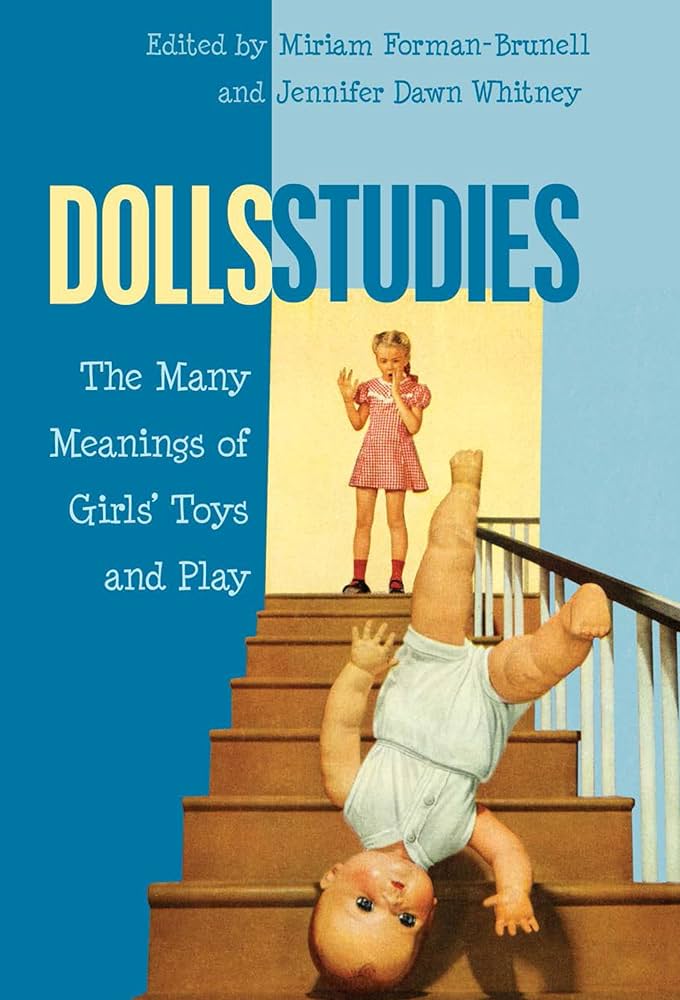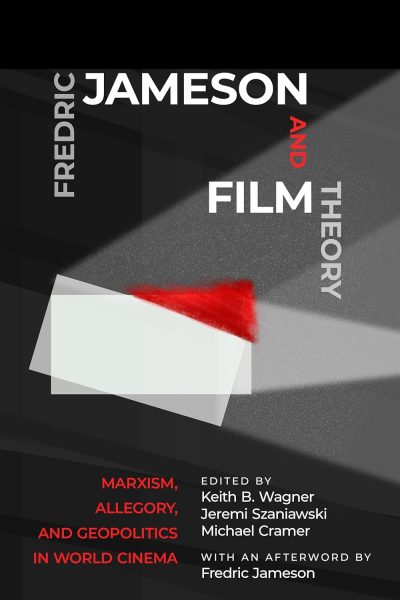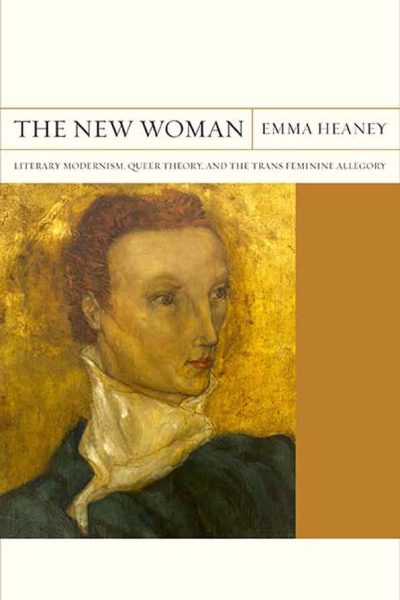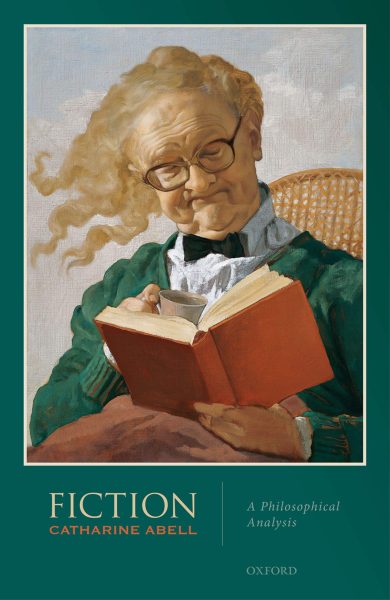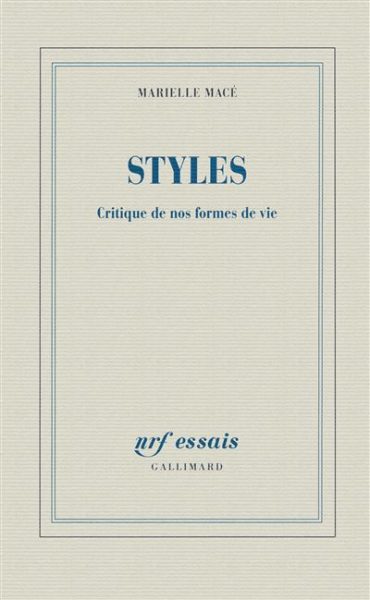はじめに
2023年に公開されたハリウッド映画『バービー』の記録的なヒットは、米国の文化的アイコンたるこのファッション・ドールが有するインパクトの大きさを世界中に知らしめた。同時に、この映画に対しては公開直後から、熱烈な賞賛──エンパワリングなフェミニズムのメッセージへの賛同、多彩な女たちが連帯するバービー・ワールドへの共感、人間社会の家父長制に対するユーモアに溢れた風刺への感嘆──が寄せられた一方で、辛辣な批判──過剰な男性嫌悪であり「ウォーク(Woke)」イデオロギーだという不満、多様性を志向しつつもなお残る白人異性愛中心主義への非難、マテルという米国の巨大玩具会社への拭えない疑念──も数多く表明された。賛否いずれにせよ、さまざまな言語で語られたこれらの膨大なレビューや批評が示すのは、女児の玩具にすぎないプラスティック製の人形が、実はフェミニズムやダイバーシティ、資本主義といった観点からのクリティカルな議論の対象となり得るのだという事実である。
しかし、この映画をめぐる毀誉褒貶の前提として、バービーをはじめとする玩具の人形についてすでに少なからぬ論争や研究の蓄積があることは、日本においてあまり知られてはいないように思われる。実際、少女の玩具としての人形をめぐっては、特に1990年代以降、英米圏におけるジェンダー系の研究者たちのあいだで盛んに議論が交わされてきた。
映画公開の8年前、2015年に刊行された本書『ドールズ・スタディーズ 少女の玩具と遊びの多様な意味(Dolls Studies: The Many Meanings of Girls’ Toys and Play)』は、近年の人文社会科学における女児向け玩具としての人形に対する関心の高まりを象徴する一冊だ。異なる専門分野の研究者による計13本の論考を収めたこの論集は、ジェンダー研究や物質文化論を主軸とした領域横断的なアプローチを通じて、少女たちにとって人形が有する複雑で多彩な意味、可能性を明らかにすることを目指している。
人形に対して全世界的な注目が寄せられたこのタイミングで、人形をめぐる近年の研究史を振り返り、その流れにおいて画期をなした本書を紹介することには意義があるはずである。本記事では、まず第一部で、英米圏において人形に与えられてきたイメージ、人形が学術的な研究対象とみなされるようになった経緯を概略的に辿る。続く第二部では、そのような動向のなか刊行された本書の内容を紹介し、ここで提唱された「ドールズ・スタディーズ」の目的とその実践を確認していこう。
I 研究対象としての人形の位置とその変遷
西洋のアカデミズムの長い伝統のなかで見るなら、人形が学術研究の対象としての地位を得たのは、それほど昔のことではない。玩具としての人形は、同じヒトガタの造形物であっても彫刻作品のように美術史に取り上げられることもなければ、文化史や社会史の分野でも不遇の扱いを受けてきた。1960年刊行のフィリップ・アリエス『〈子ども〉の誕生』の影響のもと児童文化に対する歴史学的関心が高まって以降[1]、玩具には多少の目配りがなされるようになったものの、あくまで「遊び」という営みを構成する付属物として扱われる傾向が強く、モノとしての玩具そのものを正面から扱う研究は乏しかった。なかでも人形は、私的な空間で女児が好む遊び道具にすぎないと捉えられ、まじめに論じる対象だとはみなされてこなかったのだ[2]。
他方で人形は、その主たる遊び手だとされる当の女性たちからも、しばしば疎まれ、ときに憎しみを向けられてきた。その理由はまず、人形が女児に母親や主婦の役割を教育する道具だと考えられてきたことにある。実際、近代以降の西洋社会では、人形を好むことは女性の本能であり、少女は人形を世話することを通じて母性を身につけ、家事や裁縫を習得して理想的な女性へと成長していくのだという主張が、知識人や教育者によって繰り返し語られてきた。さらに人形は、生命のないモノであるというその性質から、無知で主体性を欠き、男性の意のままになる女性のイメージを体現するともみなされ得る。したがって、フェミニズムの観点からも人形は、家父長制社会において少女たちに抑圧的なジェンダー規範を教え込むものだという烙印を押されてきたのである。
バービー人形の誕生と人形への学問的関心の高まり
玩具としての人形に対する学問的関心が一気に高まるきっかけが生まれたのは、学術界の内部ではなく、玩具市場からであった。それこそが、1959年のアメリカにおけるバービー人形の誕生である。当時においては革新的であったファッショナブルでセクシーな女性の人形は、デビューしてたちまち熱狂的な人気を集めたが、同時に多くの激しい非難に晒されることともなった。ウーマン・リブが盛り上がりを見せていた1960年代の米国社会において、バービーの象徴する女性イメージ──極端に細いウエストと大きな胸を持つ「完璧」で「不自然」なボディ、外見至上主義的で頭が空っぽなキャラクター設定──が少女たちに悪影響を及ぼすとして、一部のフェミニズムの理論家や活動家、子どもの保護者たちから糾弾されてきたのだ。
しかしながら1990年代以降、特に子ども時代にバービーで遊んだり、バービーが身近にあった世代の女性たちのあいだで、バービーをポジティヴに捉え直す傾向が目立つようになる。なるほど、バービーの身体やファッション、マテル社のマーケティングを通じて伝播されるメッセージは、西洋白人中産階級シスヘテロ女性の画一的な美の理想を押し付け、ステレオタイプ的なジェンダー役割を強化するものであるかもしれない。しかし、人形を実際に手にする少女たちは、その価値観や規範を素直に引き受け、大企業や大人たちの狙いの通りに人形を扱ってきたのだろうか? こうした問題意識から出発した論者たちは、少女の主体性を重視し、私的領域における女性の文化表現、創造性や抵抗の在り方に着目することで、バービーをめぐる議論を異なる方向から深化させることとなった[3]。
英米圏における「ドールズ・スタディーズ」の成立
世界で最も有名なファッションドールであるバービーをめぐる研究の興隆は、英米圏の学術界において、より広く一般に、女児の玩具としての人形に対する関心を高めることに貢献した。その流れのなかで刊行された書籍のひとつが、本記事で紹介する『ドールズ・スタディーズ』の編者であるミリアム・フォーマン=ブルネルによる『おままごとのために作られた 人形とアメリカの少女時代の商品化、1830-1930年(Made to Play House: Dolls and the Commercialization of American Girlhood, 1830-1930)』(1993)である[4]。近代の米国を対象に、人形産業の発達過程、実業家の男性やデザイナーの女性たちの制作意図、同時代の女性雑誌などの検討を通じて、性別役割規範に少女を馴致させる道具としての人形観に異議を唱えた本書の刊行は、その後の女児の玩具としての人形全般をめぐる研究、すなわち「ドールズ・スタディーズ」の誕生に大きな弾みをつけることとなる。
人形研究の発展がバービーの登場という市場の動きにより促されたことは先に述べた通りであるが、他方でそれはアカデミア内部の趨勢とも密接に連動している。フェミニズムの潮流の変化、およびサブカルチャーや「モノ」を対象とした、人文学における新たな方法論や理論的枠組みの発展である。まず前者に関しては、1990年代以降の第三波フェミニズムのなかで取り組まれた少女文化やガールパワーについての研究を通じて、人形を好む少女たちを家父長制的なメッセージの単なる犠牲者とみなすのではなく、彼女たちのエージェンシーを重視し、人形を通じて能動的に意味を作り出すプロセスが重視されるようになる。続いて、カルチュラル・スタディーズや物質文化研究の発展もまた、サブカルチャーを評価し、モノが人間に対して有する影響力──モノがいかに人の能力を搾取し想像力を劣化させるかというマルクス主義的捉え方のみならず、モノがいかに意味を形成し、どのような人間の思考や行動を可能にするか──を解釈する方法論を提供した[5]。こうした動向が、取るに足らない少女の遊び道具とみなされてきた人形に対する、新たなアプローチの可能性を切り拓いたのだ。
なお、人形におけるジェンダーや人種をめぐる議論が活発化するにつれて、その潮流に応答するように、玩具市場において商品である人形の外見やコンセプト、マーケティングの在り方に徐々に改変が加えられる流れが生まれたという事実もおさえておきたい。バービーの製造元であるマテルは、エスニシティの多様化を図って肌色や髪型、顔の造形にバリエーションを加えたシリーズを販売しており、米国で高い人気を誇る「アメリカン・ガール・ドール(American Girl Doll)」は、1986年よりフェミニズムや多文化主義を前面に押し出したコンセプトの人形の製造と、関連する出版事業を展開している[6]。しかしながら後述するように、これらの人形もまた、規範的な女性像やステレオタイプを再生産しているとたびたび批判されてきた[7]。
II 論集『ドールズ・スタディーズ』の目指すもの
こうして2000年代には、英米圏の人文学において人形をテーマに論じることは決して珍しくはなくなっていた。この人形研究の気運の高まりのなかで2012年、学術誌『ガールフッド・スタディーズ 領域横断ジャーナル(Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal)』において、特集「人形の意味を問う ドール・スタディーズにおける新たな方向性(Interrogating the Meanings of Dolls: New Directions in Doll Studies)」が組まれ、7本の論文と2本のレビューが掲載された[8]。本特集のゲスト・エディターを務めたのが、先述した『おままごとのために作られた』の著者フォーマン=ブルネルであり、その後、2013年にバービー研究で博士号を取得したジェニファー・ドーン・ホイットニーをもうひとりの編者に加え、新たな執筆者陣による論考をまとめて書籍として刊行されたのが、『ドールズ・スタディーズ 少女の玩具と遊びの多様な意味』である。
本書に収められた13本の論考はいずれも女児向けの玩具としての人形を対象とし、人形が少女たちの生やアイデンティティ形成においていかなる役割を果たしているかを、ジェンダー、セクシュアリティ、人種、エスニシティ、階級などの視座から考察するものである。著者の専門分野は教育学や文化人類学、歴史学、文学、映画論、ファッション論、メディア論、児童文化論と多岐にわたるが、イントロダクションによれば本書全体を貫く問題意識は、まず人形を、その制作・製造者、購入者、所有者たちによって構成される多元的な現実、ときに矛盾し合う価値やイデオロギーを表象するダイナミックな「歴史的テクスト」として捉えること。そしてそれらが広く文化的、社会的、政治的に、さらに個人の心理においていかに機能しているか、また企業やメディア、社会から課せられる規範に対して、少女たちがいかに反応し、ときに抵抗し、交渉してきたかを明らかにすることにある[9]。
本書の構成
本書は、第1部「モノ、ナラティヴ、歴史記憶(Objects, Narratives, Historical Memory )」、第2部「パフォーマンスとアイデンティティ(Performance and Identity )」、第3部「遊びのコンテクストを調停する(Mediating Contexts of Play )」、第4部「モダニズムと近代化(Modernism and Modernization )」、第5部「多文化主義、ナショナリズム、レイシズム、ガールフッドを商品化する(Commodifying Multiculturalism, Nationalism, Racism, and Girlhoods)」と全5部から構成されているが、地域や時代、方法論で厳密に分類されているわけではなく、各内容が緩やかに連関し合っている。
イントロダクションで提示された、人形に付与された価値に対して、実際の少女たちがいかに反応し交渉してきたのか、という「ドールズ・スタディーズ」の問題提起に従うなら、各論考の趣旨もおよそ次のように整理することができるだろう。まず、(1)社会において人形をめぐっていかなる規範的な言説が生まれ、意味が付与され、それらが流通し、変動し、固定化されてきたか。そして、(2)人形と実際に遊ぶとされる少女や女性たちが、それらをいかに受け取り、解釈し、あるいはみずから新たに意味を生み出していったか。それぞれの論文は、どちらに重きを置くのかで異なるにせよ、上記の二段階を踏まえつつ議論を展開している。やや強引にはなるが、この図式に基づいて本書を概観してみよう。
(1)人形をめぐる意味、価値、イデオロギーの創出
「人形は家父長制社会において少女に母親や主婦の役割を教育する道具である」、という人形に対する最も強力なステレオタイプは、先述の通り近代以降の西洋において繰り返し語られてきた。本書の論者のひとり、ヴァネッサ・ラザフォードは、19世紀後半のアイルランドにおいて人形やドールハウスがいかに中流階級の少女たちに家庭的な役割を習得させるものと考えられていたかを考察している(第6章)[10]。20世紀以降もその傾向は続き、アレクサンドラ・ロイドが指摘するように、ドイツ第三帝国においては国家社会主義のイデオロギーのもと、少女を次世代の再生産を担う良き母へと育成するために、人形が重要な玩具だとみなされていた(第3章)[11]。他方でキャサリン・ドリスコールは、フリッツ・ラングの映画『メトロポリス』(1927)とイーゴリ・ストラヴィンスキーのバレエ『ペトルーシュカ』(1911)、ハンス・ベルメールの人形の写真とバービー人形を論じながら、西洋近代において人形がテクノロジーと結びつき意味を変容させていったこと、それが強くジェンダー化されたものであったことを示した(第10章)[12]。ただし、人形をジェンダー規範の教育の道具であるとして批判的に捉える言説においては、ジュリエット・ピアーズが取り上げた、19世紀半ばのフランスで名声を誇った女性の人形制作者のような、主流の価値観に縛られないクリエイティヴな女性たちの経験が不可視化されてきたことにも留意しておくべきだろう(第9章)[13]。また、日本のひな祭りがアメリカでいかに紹介されてきたかを検討するジュディ・ショアフの論考は、人形の意味や社会的位置付けは時代や文化圏に応じて異なるという事実に気づかせ、人形をめぐる西洋近代的な固定観念を相対化してくれる(第11章)[14]。
ジェンダーのみならず、人種やエスニシティの問題に関しても、玩具市場に流通する人形には西洋中心的な価値観が浸透しているという批判はかねてから寄せられてきた。先述の通り、玩具会社はそれに応じて有色の人形やさまざまなエスニシティの人形を発売してきたのだが、本書の論者たちもそのうちいくつかの個別事例を取り上げ、批判的に検証している。たとえばエリック・フォックス・ツリーの分析によれば、マテル社が販売した「ネイティヴ・アメリカン・バービー」は、ネイティヴ・アメリカンの女性のバービー人形に自然や生殖と結びつくアクセサリーを与えることで、ハリウッド映画などを通じて広まった紋切り型を再生産し、植民地主義的イデオロギーを永続させているに過ぎない(第12章)[15]。他方、リサ・マーカスは、アメリカン・ガール・ドールが発売したユダヤ系アメリカ人の少女の人形とそれに付属する物語作品が、ユダヤ系の人々のアメリカへの同化の過程をロマンティックでおめでたい物語に仕立て上げることで、現実の差別や迫害の歴史が捨象されていると指摘する(第2章)[16]。また、カナダで販売された「メイプルリー・カナディアン・ガール・ドール(Maplelea Canadian Girl Doll)」の商品の人形に付属した物語作品や、広告、ホームページの宣伝文句などを分析したアマンダ・マーフィヤオとアン・トレパニエの論考では、このブランドにおいて「カナダの少女」が謳われながらも国内のマイノリティであるエスニック集団やケベックの人々の文化が軽視され、主流のナショナリズムが強化されていることが示された(第13章)[17]。こうして本書ではさまざまな角度から、ダイバーシティや多文化主義を声高に掲げる人形の商品が、実は差別的なステレオタイプを伝播したり、歴史の一部を隠蔽してきたという欺瞞が暴かれる。
(2)人形を介した規範への抵抗、交渉、転覆
とはいえ、人形に対して意味を付与するのは、製造元の企業や販売者、メディアだけとは限らない。メーガン・チャンドラーとダイアナ・アンセルモ=セケイラは、1990年代のフェミニズムのサブカルチャー運動であるライオット・ガール(riot grrrl)のアーティストの楽曲、アルバムのヴィジュアルや歌詞、ステージの分析を通じて、少女たちがみずからの身体を「人形化(dollification)」したり、ダークでセクシュアルな人形遊びを演じることによって、無垢で従順、受動的といったイメージが付与されてきた人形のモティーフに新たな意味を与え、家父長制社会におけるステレオタイプ的な女性性に挑戦してきたと主張する(第4章)[18]。ジェニファー・ドーン・ホイットニーの論考では、ポスト構造主義の理論を参照しながら、アフリカ系、インド系のルーツを持つ米国の女性ラッパー、ニッキー・ミナージュが演ずる「ハラジュク・バービー(Harajuku Barbie)」のパフォーマンスを分析し、バービーが体現する西洋的な理想化された白人女性のイメージが、遊び心に満ちた方法で撹乱されていると論じられる(第5章)[19]。
こうして人形は、社会におけるさまざまなアクターによって意味を付与されているのだが、それでは実際に人形と接し、遊ぶ少女たちは、どのようにその意味を受け取り、反応し、対処していくのだろうか? 本書の執筆者たちはそれぞれのアプローチで、この問いに答えることを試みている。たとえば、先述したロイド(第3章)はドイツ第三帝国期のエゴ・ドキュメントの分析を通じて、戦時下において人形が、子どものトラウマに対処するための分身や、離れ離れになった友達や家族の代理的存在ともなっていた事実を指摘し、人形が過去を悼み、未来に希望を託す手段であったと述べている[20]。アメリカの奴隷制度の文脈で黒人の人形と子どもの人形遊びについて考察したロビン・バーンスタインは、西洋近代以降における児童文学と物質文化の密接な繋がりを指摘したうえで、パフォーマンス研究の観点から「脚本(script)」という概念を用いて、人形で遊ぶ行為を批判的に分析するための方法論を提唱する(第1章)[21]。彼女によれば、人形は製作者やメディア、周囲の人々によって脚本を刻まれており、それを前にした子どもたちにいかなる行動を取るべきかを指示するが、子どもたちは舞台の役者と同様に、必ずしもそれに強制的に従わされるわけではなく、みずから抵抗したり、修正を加えたりすることもできる。他方、ナグメ・ヌーリ・エスファハニとヴィクトリア・キャリントンは、ポスト現象学の理論にもとづく参与観察を通じて、オーストラリアに住むイラン系のルーツを持つ少女たちが、アメリカのMGA 社が製造するブラッツ・ドールとどのように遊んでいるかを調査し、彼女たちが人形を使ってイランの伝統的な慣習や文化と西洋のポップ・カルチャーを接続する創意に富んだ遊び方を生み出していると結論づけた(第7章)[22]。また、エリザベス・チンは、YouTubeに投稿された、子どもたちが撮影したと想定されるバービー人形を用いたセクシュアルなビデオの分析を通じて、かれらがビデオ制作を通じて洗練されたナラティヴを考案し、バービーをめぐる規範を転覆するような意味を作り出していることを示す(第8章)[23]。大人は、子どもたちの作品を先入観にもとづく単純な読みに還元してしまうのではなく、真摯に問いを投げかけ、思考や解釈を広げていかなければならないのだと、チンは強く説いている。
おわりに
以上のように、複数の年代と地域における人形と少女について論じた本書は、従来ジェンダー役割の教育の道具として捉えられてきた人形が秘めるポテンシャルを解明していったといえるが、いくつかの問題点も提起しておこう。まず、本記事の前半で確認した、イントロダクションで定義されている「ドールズ・スタディーズ」は、英米圏の議論を中心としており、他の国々で行なわれてきた人形についての研究はほとんど考慮されていない。たとえば、フランスにおいては、児童文化、玩具史研究のミシェル・マンソンや、彼を中心に立ち上げた「人形研究調査センター(Centre d’études et de recherches sur la poupée)」が、1980年代頃より精力的に、子どもの玩具や人形を対象とする研究を展開してきた[24]。人形文化が西洋とは異なる独自の発達を遂げた日本においても、特にジェンダーの観点から人形を考察した論考は、1995年の増淵宗一『少女人形論 禁断の百年王国』を端緒として現在に至るまで複数刊行されている[25]。また、文学や児童文学、美術史においても、個別の作品における人形のモティーフを分析した論考には一定の蓄積があり、これらは人形の意義をより深く探究するうえで新たな視座を与えてくれるだろう[26]。最後に忘れてはならないのが、モノとしての人形をめぐる研究はアカデミズムの内部というよりも、むしろ愛好家やコレクターによって推進されてきたという事実である。19世紀のアンティーク・ドールからバービーなど現代のファッション・ドールまで、学術論文では疎かになりがちなモノそれ自体を大量に扱った、資料的価値の高い書物が数多く刊行されている。
もうひとつの問題点として、本書が対象とする人形の種類、および時代と地域に、一定の偏りがあることも指摘せざるを得ない。本書で扱われる人形の大半は、バービーやアメリカン・ガール・ドールをはじめとして、20世紀以降に西洋の大企業によって大量生産された商品としての人形である。それらが現代の多くの少女たちにとって最も身近なタイプの人形であることは確かにせよ、ヒトガタのモノであるという人形の本来の定義に立ち戻り、異なる時代や地域の人形とその人間との関わりにも目を向ければ、人形が有する別の側面や可能性に光を当てることができるだろう。また、そのことは本書の採る方法論にも再検討を促すのではないか。人形を「歴史的テクスト」として考察するというアプローチは、その人形が実在した個々の時代、地域の社会に特有の少女たちの生へ迫ることを可能にする一方で、ともすれば議論を、〈人形に与えられた意味や規範〉-〈少女による抵抗や交渉〉という単純な対立図式へと還元しかねない。古今東西に存在するさまざまな人形の様態を考えることは、人形と少女の関係性により多角的な解釈を与えることにもなると思われる。
人形というモノの遍在性ゆえに事例の不足や偏りを指摘することは容易いが、「ドールズ・スタディーズ」をタイトルに掲げた本書が、学術界で長らく軽視されてきた玩具としての人形に対する注目の高まりを捉え、研究対象として確立させる重要な一歩となったことは間違いない。イントロダクションで述べられているように、人形についての研究は、ポップカルチャーや少女文化、消費文化や教育をめぐる研究と密接に連関し合うし、本書の寄稿者たちが行なったように、人形というテーマを取り入れた考察は人文社会科学の諸分野にも一定の貢献を果たすだろう。さらにそれらは、アカデミズムの枠を超えて、玩具としての人形の制作や製造の現場へフィードバックされたり、映画『バービー』のような人形をテーマとした文化表現の創出を促し、社会に批判的な問いを投げかけることへも繋がり得る。人形について、あるいは人形を通して思考することで、わたしたちは人間を、世界を、今よりも少し豊かなものにすることができるかもしれないのだ。
註
-
[1]
Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, Paris, Seuil, 2014 (1960)(フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生 アンシァン・レジーム期の子供と家族生活』杉山光信・杉山恵美子訳、みすず書房、1980年。).
-
[2]
Miriam Forman-Brunell. “Interrogating the Meanings of Dolls: New Directions in Doll Studies,” Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal, vol. 5, no. 1, 2012, p. 3. Michel Manson et Annie Renonciat, « La culture matérielle de l’enfance : nouveaux territoires et problématiques », Strenæ, no 4, 2012. https://doi.org/10.4000/strenae.750 [2023年12月31日閲覧]. アカデミズムにおいて人形と女児の関係を主題とした先駆的な著作のひとつが、19世紀末に刊行された、児童研究のムーブメントを作った米国の心理学者G. Stanley HallとA. Caswell Ellisの共著A Study of Dollsであるが、本書が刊行されて以降、玩具としての人形についての研究は再び影を潜めることとなる。G. Stanley Hall and A. Caswell Ellis. A Study of Dolls. New York & Chicago: E.L. Kellogg & Co, 1897.
-
[3]
たとえば次の論考など。Erica Rand. Barbie’s Queer Accessories. Durham: Duke University Press, 1995. Louise Collins, April Lidinsky, Andrea Rusnock and Rebecca Torstrick.“We’re Not Barbie Girls: Tweens Transform a Feminine Icon.” Feminist Formations, vol. 24, no. 1, 2012, pp. 102-126. Kim Toffoletti. Cyborgs and Barbie Dolls: Feminism, Popular Culture and the Posthuman Body. London: I.B. Tauris, 2007. Jennifer Dawn Whitney. Playing with Barbie: Doll-like Femininity in the Contemporary West. PhD Thesis, Cardiff University, 2013. 次の記事も参照のこと。Nicole Froio. “Teaching Barbie: Scholarly Readings to Inspire Classroom Discussion,” JSTOR Daily, 2023. https://daily.jstor.org/academic-barbie-scholarly-readings-classroom-discussion/ [2023年12月31日アクセス]
-
[4]
Miriam Forman-Brunell. Made to Play House: Dolls and the Commercialization of American Girlhood, 1830-1930. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1998 (1993).
-
[5]
フローランス・ラウルナ 「〈書評論文〉モノで人間を知る──物質文化研究の新たな試み ダニエル・ミラー編Material cultures: Why some things matterを手がかりとして」『現代民俗学研究』第2号、2010年、57-70頁。1990年代以降は、子どもと物質文化を対象とする著作も複数刊行されている。たとえば以下など。Karin Calvert. Children in the House: The Material Culture of Early Childhood, 1600-1900. Boston: Northeastern University Press, 1992. Joanna Sofaer Derevenski. Children and Material Culture. London: Routledge, 2000. Megan Brandow-Faller, ed. Childhood by Design: Toys and the Material Culture of Childhood, 1700-Present. New York: Bloomsbury Visual Arts, 2018.
-
[6]
アメリカン・ガール・ドールについては次の文献に詳しい。Emilie Zaslow. Playing with America’s Doll: A Cultural Analysis of the American Girl Collection. New York: Palgrave Macmillan, 2017.
-
[7]
バービーにおける多文化主義のマーケティングに対する批判として代表的なものに、たとえば次の論文がある。Ann DuCille, “Dyes and Dolls: Multicultural Barbie and the Merchandising of Difference.” Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, vol. 6, no. 1, 1994, pp. 47-68.
-
[8]
Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal, vol. 5, no. 1, 2012. 本特集は2021年に単行本として刊行された。Miriam Forman-Brunell, ed., Deconstructing Dolls: Girlhoods and the Meanings of Play. New York: Berghahn Books, 2021.
-
[9]
Miriam Forman-Brunell and Jennifer Dawn Whitney. “Introduction,” Dolls Studies: The Many Meanings of Girls’ Toys and Play. New York: Peter Lang, 2015, p. X.
-
[10]
Vanessa Rutherford. “Technologies of Gender and Girlhood: Doll Discourses in Ireland, 1801-1909.” Ibid., pp. 103-118.
-
[11]
Alexandra Lloyd. “Dolls and Play: Material Culture and Memories of Girlhood in Germany, 1933-1945.” Ibid., pp. 37-59.
-
[12]
Catherine Driscoll. “The Doll-Machine: Dolls, Modernism, Experience.” Ibid., pp. 185-204.
-
[13]
Juliette Peers. “Adelaide Huret and the Nineteenth-Century French Fashion Doll: Constructing Dolls/Constructing the Modern.” Ibid., pp. 157-183.
-
[14]
Judy Shoaf. “Girls’ Day for Umé: Western Perceptions of the Hina Matsuri, 1874-1937.” Ibid., pp. 207-225.
-
[15]
Erich Fox Tree. “The Secret Sex Lives of Native American Barbies, from the Mysteries of Motherhood, to the Magic of Colonialism.” Ibid., pp. 227-256.
-
[16]
Lisa Marcus. “Dolling Up History: Fictions of Jewish American Girlhood.” Ibid., pp. 15-35.
-
[17]
Amanda Murphyao and Anne Trépanier. “Canadian ‘Maplelea’ Girl Dolls: The Commodification of Difference.” Ibid., pp. 257-280.
-
[18]
Meghan Chandler and Diana Anselmo-Sequeira. “The ‘Dollification’ of Riot Grrrls: Self-Fashioning Alternative Identities.” Ibid., pp. 63-83.
-
[19]
Jennifer Dawn Whitney. “‘It’s Barbie, Bitch’: Re-reading the Doll Through Nicki Minaj and Harajuku Barbie.” Ibid., pp. 85-102.
-
[20]
Lloyd. “Dolls and Play: Material Culture and Memories of Girlhood in Germany, 1933-1945.” Ibid., pp. 51-52.
-
[21]
Robin Bernstein. “Children’s Books, Dolls, and the Performance of Race; or, the Possibility of Children’s Literature.” Ibid., pp. 3-13.
-
[22]
Naghmeh Nouri Esfahani and Victoria Carrington. “Rescripting, Modifying, and Mediating Artifacts: Bratz Dolls and Diasporic Iranian Girls in Australia.” Ibid., pp. 121-132.
-
[23]
Elizabeth Chin. “Barbie Sex Videos: Making Sense of Children’s Media-Making.” Ibid., pp. 133-154.
-
[24]
Michel Manson, Jouets de toujours. De l’Antiquité à la Révolution, Paris, Fayard, 2001. マンソンは1983年に、人形の研究史をまとめた論考を発表している。Manson, « La poupée, objet de recherches pluridisciplinaires. Bilan, méthodes et perspectives », Histoire de l’éducation, no 18, 1983, p. 1-27.
-
[25]
増淵宗一『少女人形論 禁断の百年王国』講談社、1995年。ほかに、人形とジェンダーの問題に焦点を当てたものには、たとえば次の論考などがある。吉良智子「「人形」をつくること、おくること 近代日本における「少女」と「人形」」『千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書』294号、2015年2月、151-159頁。山崎明子「リカちゃん人形の身体表象への欲望 着替える身体から着替えない身体へ」武田佐知子編『着衣する身体と女性の周縁化』思文閣出版、2012年、402-419頁。
-
[26]
たとえば次の著作など。Lois Rostow Kuznets. When Toys Come Alive: Narratives of Animation, Metamorphosis, and Development. New Haven: Yale University Press, 1994. Leslie Reinhardt. “Dolls, Dress, and Female Virtue in the Eighteenth Century,” American Art. vol. 20, no. 2, 2006, pp. 32-55. 川崎明子『人形とイギリス文学 ブロンテからロレンスまで』春風社、2023年。
この記事を引用する
谷口奈々恵「人形を「歴史的テクスト」として読む──ミリアム・フォーマン=ブルネル、ジェニファー・ドーン・ホイットニー編 『ドールズ・スタディーズ 少女の玩具と遊びの多様な意味』書評」『Phantastopia』第3号、2024年、120-130ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/dolls-studies/。(2026年02月27日閲覧)