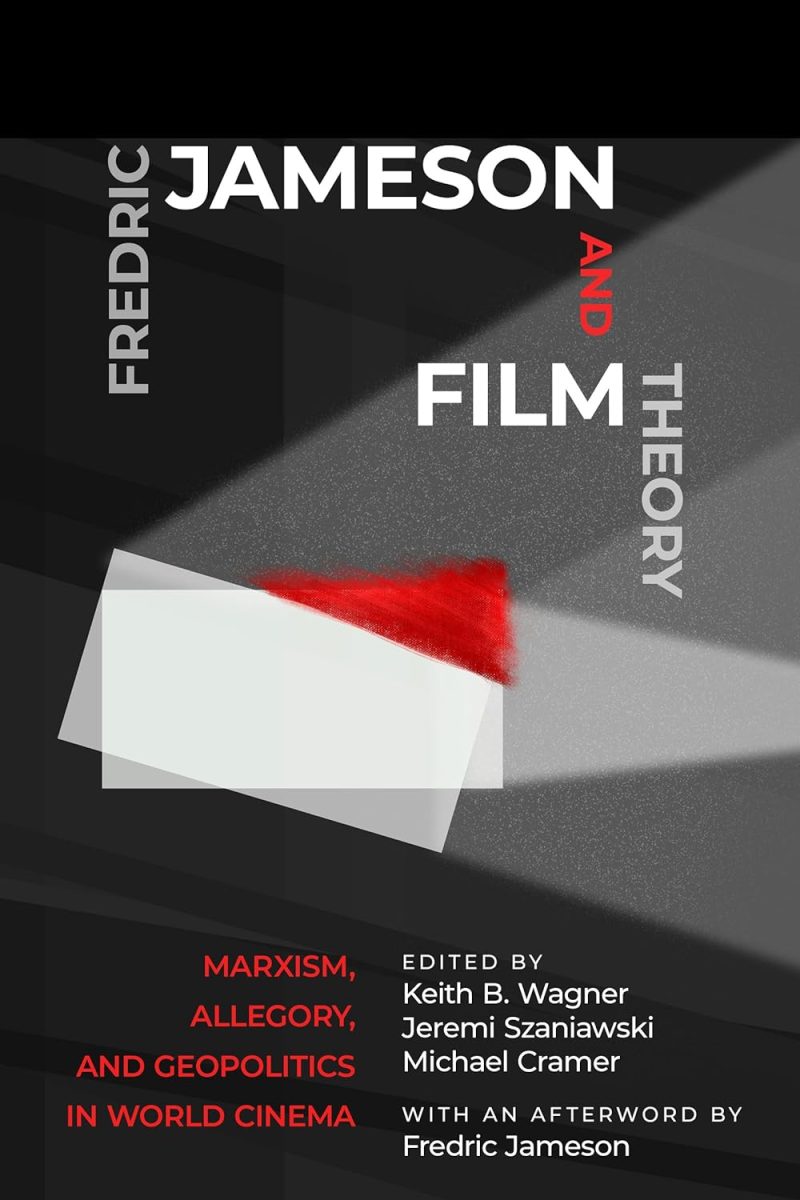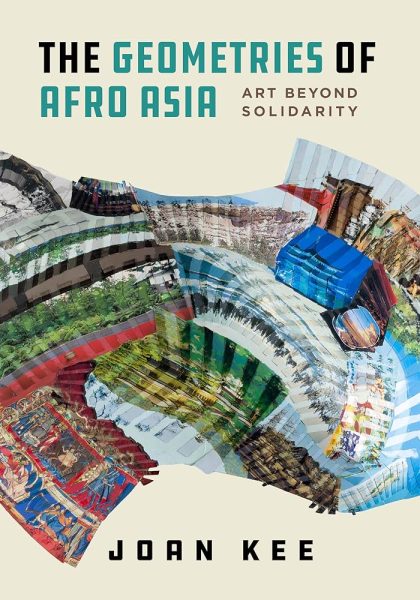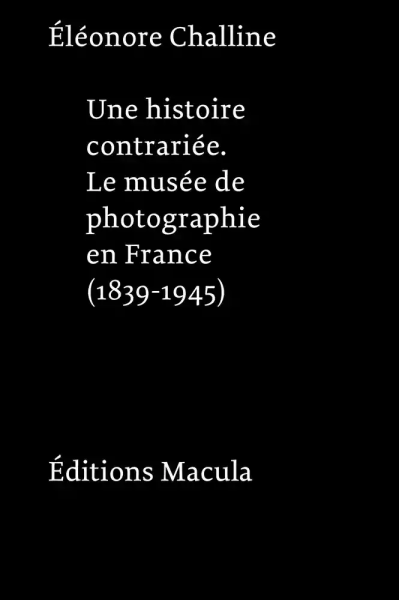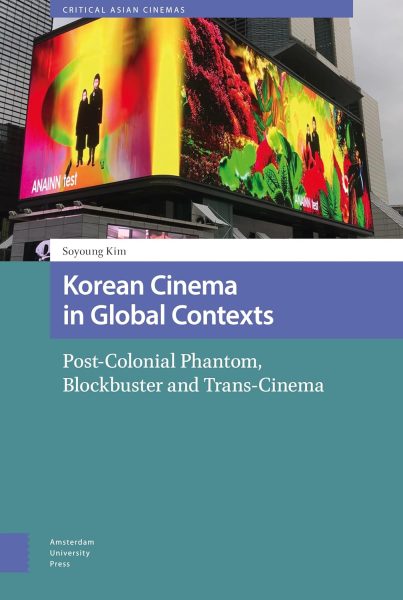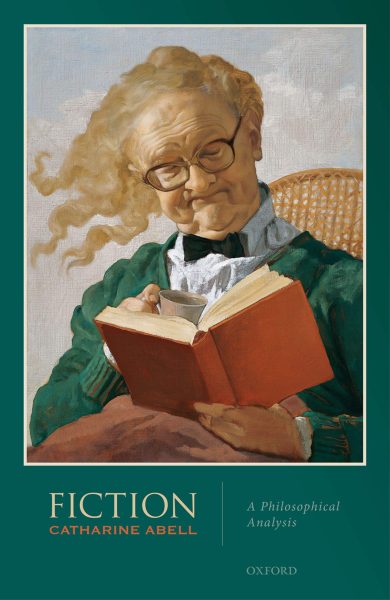鍵括弧つきで、あるいは引用符を付けて表記せねば恥ずかしくて書けない(口に出せない)類の言葉があるとしたら、少なくとも現在の日本では、専門的な議論の場においては言うまでもなく、日常会話の水準においてすら、いわゆる〈映画理論〉がその条件を満たしているのは確かなことだと思われる(そうした諸々の言葉のうちの筆頭とは言わないにせよ)。
フレドリック・ジェイムソン、スラヴォイ・ジジェクやテリー・イーグルトンのような──日本が誇る柄谷行人はスマートに、ややくぐもった調子で──現役のマルクス主義批評家たちはある確信──それが何についての確信であるのかは言うまでもあるまい──のうちにありつつ、人文学における「理論」の失墜という状況に対して粘り強い抵抗を続けてきた。これらのマルクス主義的な創造的取り組みは、ゆるやかに言説上の共同体を形作り、その一団だけがもたらし得る特産物を提供している。グローバル資本主義に対する、より控え目な批判的態度を取る大半の人々も有益極まりないこの特産物を求めている(物象化した書き方ではあるが、市場経済に慣らされた我々にとっては、今のところそのようにイメージするしかないのだ)。そこで大勢の読み手が、この論集を手に取り、マルクス主義的な言説上の領域へとますます(密)入国することを期待したい。入国税は無し、適度に脱中心化されていて抑圧的な独裁もなし、国土は限りなく広く変化に富んでいる(ジェイムソン曰く「マルクス主義の思考法は…無限に全体化できる[1]」)。ただし過度な一般化には気をつけ、即座の有用性を期待することは慎むべし。そうすれば、実り豊かで平和な、刺激に満ちた旅ができ、お土産もたくさん持って帰れるはずだ。そしてその過程での驚きや絶望といった情動をともなう経験こそが、知ることが決してかなわない後期資本主義の全体性に対して、それでもなお我々が向かい合うために不可欠になる(収録されたパンジー・ダンカンの素晴らしい論文「ミディアムショットの理論」をふまえるとそのように言える)。
本書は、批評家フレドリック・ジェイムソンの映画研究に対する寄与について、映画を主な研究対象とする12人の書き手が検討し、その理論の適用、問い直し、発展や修正を様々な角度からおこなった論集である。巻末には、それ自体が理論的な検討をさらに進める上で有益と思われるジェイムソン本人からの応答が掲載されている。編集はマイケル・クレーマー(サラ・ローレンス大学)、ジェレミー・シャニャフスキ(マサチューセッツ大学アマースト校)、キース・B・ワグナー(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン)の三名が担当している。それぞれ映画研究、比較文学、国際的なメディアと文化を専門的に扱っている英語圏の研究者である。
1934年にアメリカ合衆国オハイオ州で生まれたジェイムソンは、高齢ながら現在もなお旺盛に執筆を続けており、新たな著作が待たれる現役の書き手である。マルクス主義文学批評の記念碑的著作『政治的無意識』(1981)をはじめとして、文学を主要な対象としているが、文化の諸相を扱って『ポストモダニズム あるいは後期資本主義の文化的論理』(1991、邦訳未出版。この点については後述のように本書収録の論文で山本直樹が問題としている)など後期資本主義の批判とりわけポストモダニズムの分析と理論化を展開しており、頻繁に参照されている。映画を対象とした批評として『目に見えるものの署名』 Signatures of the Visible, (1990). と『地政学的美学』The Geopolitical Aesthetic, Cinema and Space in the World System, (1992). の二冊を出しており(前者は2015年に邦訳が出版されている)、本論集の編集者たちは、巻頭でジェイムソンの紹介とともに、映画研究の分野に与えた衝撃とその問題機制について記述しながら、被引用数を調べて(編者達はグーグル・スカラーを利用した集計方法が合理的で物象化された、「ジェイムソン的でない」方法であることを自覚しつつ、プラットフォーム資本主義の文脈での評価が可能だと述べていて面白い)、映画研究においてはエドワード・ブラニガンやトマス・エルセサーのよく参照されるテクストと互角の被引用数をジェイムソンの著作が誇っていることを示している。
マルクス主義者として彼が前提とする諸条件をどうしても受け入れられないという読者は別として、我々はその多彩な批評を横断することで多角的なアプローチやテクストを分析するための強力な枠組みを学び、書くことを触発されるだろう。先述の被引用数はそれを物語るものではあるが、しかしながらジェイムソンの理論は壮大かつ緻密な反面、ややもすると実証的な研究との折り合いがつきにくく──弁証法的な媒介の必要性をマルクス主義者なら明快に指摘するだろう──その独特の文体(本書収録の論文でポール・コーツはジェイムソンの息の長いうねるような文章をアンゲロプロスの長回しと並置している)もあいまって、人文学の研究者や批評家にとって使い勝手が悪く、持てあましてしまうこともまた想像できる(少なくとも評者はそういった契機に必ず直面する)。さらに、より具体的には、リアリズム-モダニズム-ポストモダニズムというジェイムソンの文化理論の根本に据えられている時期区分に関して、文学や建築の分野と異なる映画の歴史的な軌跡ゆえにジェイムソンの問題機制と映画研究がうまく嚙み合いにくいという問題も横たわっている。
それゆえ個別の地域や国家単位の社会経済を対象とする研究、映画を専門とした学問的蓄積(主に英米圏のフィルム・スタディーズ)による検証を経て、ジェイムソンの理論を応用する試みがこのように様々な角度で提示されることは映画学徒として非常に悦ばしいことであるし、また映画のみならず目下のところ新自由主義としてあらわれている後期資本主義の諸相を批判するにあたって幅広い視野と根源的な問題機制を引き出すことを可能にするだろう。本論集に収録された順番に沿って各論を紹介していこう。
最初に、アンドレ・バザンの研究でよく知られるダドリー・アンドリューは「ポストモダン的状況の律動として映画を感じる:ジェイムソンの「ディーバについて」について」で、1981年に公開されたジャン=ジャック・ベネックス監督の『ディーバ』に関するジェイムソンの批評を取り上げている。アンドリューはジェイムソンの議論におけるconjuncture すなわち社会、経済と文化の歴史上の結合、関連を意味する概念に着目しながら、『ディーバ』をフランス国内の映画の製作と受容の状況に位置付け直し、画面の肌理を精査している。conjunctureは、邦訳では「関連」といった語でさりげなく訳されるため日本語で読む読者は見落としがちだと思われるが、アルチュセールから引き継いだこの概念はジェイムソンの批評を読むうえで文化テクストと社会経済の物質的な文脈を結びつけるにあたり決定的な役割をしばしば果たすため、注意深く扱われねばならないのだという。この点は、いわゆる「社会反映論」などと称して粗雑に一蹴しにかかってくるような見解に対して、ジェイムソン的なアプローチを擁護する上で重要な論理的手続きを示唆している。アンドリューは、『ディーバ』とミッテラン政権の実現、ポストモダン的な状況がいかに結合しているのかを示し、フランスの映画史における特異点のようなものを見出しつつ、1981年に公開された同作についての批評を手がかりにジェイムソンの思考の軌跡の転換点をもそこに探り当てている。
ジョン・マッケイは「アレゴリーと商品化:スターリン主義的映画としてのヴェルトフの『レーニンの三つの歌』(1934)」で、ジガ・ヴェルトフの忘れられた傑作について、その不透明な再編集過程も含めて製作過程を実証的に明らかにし、ヴェルトフはスターリン主義を忌避しようとしていたとする従来の好意的(?)評価を覆し、この作品がどのような意味でスターリン主義的であるのかを明らかにした。突出して名高い『カメラを持った男』(1929)に寄せられた評価をもって映画黎明期の「作家」として列聖されてきた感のあるヴェルトフを、スターリン主義の実践者として闇に突き落とすかのような手つきは実にスリリングであるのだが、ジェイムソンが『政治的無意識』で提示した四つのカテゴリーによるアレゴリーと解釈に関するモデルが、議論の終盤に参照され、スターリン主義が、レーニンというスターリンに対してより高位のアレゴリーによって駆動されており、その意味でヴェルトフがスターリン主義に沿って映像作品を構成していたことが明らかにされる。
これに続くシャニャフスキの「ノスタルジア、メランコリーそしてポーランド映画におけるスターリンの永続」でもスターリンとその表象が問題とされる。この論文においてスターリンがポーランド人にとってのトラウマであり、語り得ない何かとして未だに機能していることが主張される。取り上げられている映画はパーヴェル・パヴリコフスキの『イーダ』(2013)と『コールドウォー』(2018)なのだが、驚くべきことにこれらの国際映画祭で高い評価を得た映画は、スターリン体制の経験の両義的な性質を利用し、ノスタルジアを巧妙に喚起しながら、グローバル経済と新自由主義の美学を体現しているのだという。特に『イーダ』を近年まれな美しい作品だと高く買っていた評者は戸惑いを覚えながら、シャニャフスキの議論に深く納得させられた。ここで述べられているように、評者も視覚的なまやかしに騙された、全世界の観客の一人ということになるのだ。
山本直樹は、「ジェイムソンと日本のメディア理論:仮想対話」で大澤真幸および東浩紀の議論とジェイムソンを関係づけることで、日本のポストモダンに関する言説において、ジェイムソンがそれらとどのように重なり合い、またすれ違っていったのかを明らかにする。ジェイムソンの代表的著作『ポストモダニズム あるいは後期資本主義の文化的論理』が1991年に英語で出版されたのち、いまだに邦訳が出されないことが何を意味しているのかを明晰に論じるとともに、ジェイムソンの理論が特定の地域すなわち北米や一部の西欧を対象としてモデルを組み立てる過程で、それらと第三諸国の間の微妙な位置にある日本のような地域がうまく位置付けられない契機を含んでいることが指摘される。こうした問題意識は、続くアーヴィン・K・ウォンの「ジェイムソンがクイア理論と出会うところ:1990年代の中国語圏映画におけるクイア認知地図化」でも共有されている。ウォンは、『地政学的美学』におけるジェイムソンの『恐怖分子』(エドワード・ヤン監督、1986)についての議論が台北のローカルな情報を捨象していることを指摘したうえで、ツァイ・ミンリャンの『青春神話』(1992)と『河』(1997)を取り上げ、ジェイムソンが提示した認知地図化[2](cognitive mapping)のプロセスが、台北に生きる男性のクイアな欲望を通して作中でどのようになされているのかを明らかにする。
ワグナーの「『パラサイト』(2019)をジェイムソン的に読むこと:ソウルの家、不動産投機そしてバブル市場」では、韓国のソウルにおける不動産バブルという個別的な現象が全世界で進行する新自由主義的な不動産投機の一環であることをふまえながら、バブル市場の破滅的な崩壊への恐怖を『パラサイト 半地下の家族』の空間設計と演出に読み取っている。ポストモダンに関するジェイムソンの理論を参照しつつ、そこで「家」について言及されていないことにも触れ、個別的な議論を通して理論を補完している。この論文を通じて我々はポン・ジュノの演出の戯画的な印象を温存しながら、焦燥感を伴った認識を与えられるだろう。
新自由主義の進展は、日常生活のあらゆる側面がプライヴェート化(私有化)されることによっても特徴づけられる。メルセデス・ヴァスケスの「メキシコとブラジルの中流階級映画の包摂の戦略」は『パラサイト』論とともに住まうということに関して着目しており、ラテンアメリカにおいて新自由主義的な政策がもたらした豊かな中流階級の出現という文脈のもと、カルロス・レイガダスの『闇のあとの光』(2012)とアンナ・マイヤートの『セカンドマザー』(2015)における階級構造のあらわれが明らかにされる。ヴァスケスは、ジェイムソンが『政治的無意識』で提出した概念「包摂の戦略」を通してやはり空間と登場人物の関係などに着目し、自閉した文化テクストが社会経済の全体性に対する想像力をどのように締め出そうとするのかを例証している。ここから導き出された議論によると、アルフォンソ・キュアロンなどとともにレイガダスは新自由主義的な価値に方向づけられた演出の主体であり(シャニャフスキの論文でも、パヴリコフスキと共にキュアロンが同じように批判されていた)、その反面マイヤートの演出の転覆的な性質が明らかにされる。論全体の図式に関しては平板な印象を受けるが、『イーダ』同様にレイガダス作品のような、画面それ自体の美しさを強調し、瞑想的な雰囲気をまとった、繊細な手つきの凝った映画が、タルコフスキー作品を範例としてある種の映画好きからほぼ無条件に支持される傾向を思えば、そうした作品における富裕な中流階級の登場人物とその世界のみに限局された、他の階級の集団を他者化する語りの構成と、そこに全体性を損なわせようとするイデオロギー的性質を見出すヴァスケスの論文は意義深い。
クレーマーの「新自由主義的陰謀:ジェイムソン、ニューハリウッドそして『大統領の陰謀』」およびマイク・ウェインの「陰謀映画、ハリウッドの文化的パラダイムと階級意識」はともにジェイムソンが『地政学的美学』で論じた「陰謀映画」conspiracy filmと認知地図化の概念を軸にしながら、『大統領の陰謀』を再考し、後者は『シリアナ』(2005)、『カンパニー・マン』(2002)などの現代的なブロックバスター映画による陰謀映画の概念の更新について論じている。クレーマーの議論は古典的ハリウッド映画とニューハリウッドの関係を歴史的に再検討しつつ、ウォーターゲート事件でニクソン大統領の辞任の火付け役となった実在のワシントンポストの新聞記者(ロバート・レッドフォードとダスティン・ホフマンが演じる)が、ニクソン陣営の「陰謀」とは異なるもう一つの陰謀すなわち新自由主義的なエージェンシーとマネージメントの原理に沿っていることを明らかにする。他方で、古典的な映画の語りが、現代的な陰謀映画によってどのように打破されていったのかをハリウッド映画の歴史的記述を通じて跡付けながら、ジェイムソンが応用したことでよく知られるグレマスの意味の四角形[3]を活用し、ジェイムソンの議論の過度な一般化を指摘しつつそれを鮮やかな手つきで修正している。
ジェイムソンは、『アメリカのユートピア―二重権力と国民皆兵制』(初出2016年、邦訳2018年。編者はスラヴォイ・ジジェク)において、全国民を徴兵し軍隊を主権国家内におけるもうひとつの権力とすることで、アメリカ合衆国の破綻した公共セクターや福祉、教育政策を再編成し、国民が共同体的な感覚を取り戻すという途方もない提案をおこなった。ダン・ハスラー=フォレストは、「「アメリカのユートピア」とミリタリーSFのポリティクス」」においてこの議論の持つ問題点と可能性を考えるにあたり、ハリウッド製のSF映画がいかに軍隊の階級と親和的であり続けたのかを確認したうえで『スターシップ・トゥルーパーズ』や中国の劉慈欣の小説を原作とした『流転の地球』などを取り上げて、集団的な(準)軍事的行為がもたらす社会的平等の可能性と、ファシズム的な権威主義の主体に軍隊が陥る可能性の双方を真剣に読み取ってみせる。これは『政治的無意識』の結論部分でネアンの『英国の解体』から引用された「すべてのナショナリズムは、健全であると同時に病的なのである」という省察の延長線上に位置し、同時にアジア的専制のSF的な検討とも言え、実に面白い。
ここまで、論集に収められた順に各論を紹介したが、最後に二本の論文を取り出して紹介しておく。本書の4番目に収められたポール・コーツの「ジェイムソン、アンゲロプロスそしてユートピアの精神」は、高度な修辞を駆使し、詩句の引用を織り交ぜた文章が読みにくく、評者の理解がおぼつかなかった。とはいえ、アンゲロプロスの映画に、そうした書き方によってしか言葉にできない契機があることは確かであり、ジェイムソンが一貫して問題としてきた「ユートピア」が、いかなる意味合いで未知と不在の対象について考える営みであるのかを映像的に組み立てていく論の運びは魅惑的であると同時に必然性を伴っていると感じた。
ジェイムソンが巻末で「唖然とした」(stunned)と述べているパンジー・ダンカンの「ミディアムショットの理論」は、明快な論立てで、映画研究が明らかにしてきたミディアムショットの一般的な特徴を簡潔にまとめたうえで、認知地図化にあたりミディアムショットが発揮する有効性を述べ、ジェイムソンの『地政学的美学』の陰謀映画に関する議論がいかにミディアムショットに拠っているのかを、情動(affect)に着目しながら説得力豊かに論じている。とりわけ、ジェイムソンが同書の陰謀映画についての章で掲載した映画のスチル写真のほとんどすべてがミディアムショットであることの指摘は──ジェイムソン自身意識していなかったのだろう──驚くべき洞察である。
掲載されている各論はおおむね共通して、個別の作品の属する地域や国の映画の編年的な歴史的記述や、ジャンルの文脈などと、ジェイムソンの理論を参照して得られる枠組みを接続し、理論による一般化と個別性の均衡を探りながら、理論の修正、拡大をはかろうとしている。それはかなりうまくいっているように思われる反面、解釈を可能にする、映像の意味作用についての議論抜きにJamesonianつまりジェイムソン的な議論が積み重ねられていくことに対して評者は疑問を抱いた。また、フィクショナルな映画のみが対象とされていることは本論集のひとつの限界でもある。『政治的無意識』でジェイムソンは、法律といった類のテクストすらも分析の俎上に載せることが可能であると結論部分で述べていた。今回の論文集ではもっぱら虚構の映画のみがとりあげられており、いわゆるドキュメンタリーに属するのはジガ・ヴェルトフの構成的映像ぐらいしか見当たらない。今後の課題として例えばドキュメンタリー映画をジェイムソン的にどう解釈するかといった議論にも大きな可能性があると思われる。もちろん、ハスラー=フォレストのように、ジェイムソンの法外な『アメリカのユートピア』を真剣に論じるといった試みにおいては、想像力を飛躍させる一見荒唐無稽な映画テクストを論じることこそが、ジェイムソンの主張の核心に触れるのに有効な企てになるのだろう。また、認知地図化という政治的プロジェクトが想像力の問題であることをふまえると、フィクショナルなものがまず検討される契機に必然性が認められるのではあるが、今後こうした取り組みの対象をフィクショナルなテクストから拡張していくことも大いになされるべきであろう。
ジェイムソンの理論を受け継ぐうえで、本書に収録された各論は諸カテゴリー間の様々な媒介を考案し、また種々の概念に最大限の可能性を宿すべくその意味を再編成に努めている。認知地図化について主観的な情動の問題として捉え直しているダンカンの議論は、それが「認知地図」(cognitive map) ではなくあくまでも地図化(mapping)すなわちプロセス的なものであり、しかも捉えがたい後期資本主義の全体性の把握を試みては失敗する運命にありながら、そこでの情動的な経験が、止まることのない批判的な知の営みをもたらすことを言明する。本書に収録された他の陰謀映画や認知地図化に関する議論と共鳴することでその妥当性を読み手に実感させるだろう。
本書を読むことを通して、理論の復権、などと大上段に構えることなく、映画理論という未だ実体不明の言葉を臆面もなく使うことに対する確信を評者は抱くに至った。この論集は、書き手たちから「知り得る、知り得ない、そして未だ見出されていない、私たちの共同体へ[4]」手渡された贈り物であり、そこに込められた希望と願いが、個性的な各論を通じて様々な道筋で読み手に届くこともまた、評者の確信するところである。
註
-
[1]
フレドリック・ジェイムソン『政治的無意識』大橋洋一ほか訳、平凡社、2010年、87頁。
-
[2]
後期資本主義の世界においてその中で生きる主体(つまり我々)は、高度に複雑化した社会構成体の全体を把握できない。その前提のもと、ジェイムソンはケヴィン・リンチが『都市のイメージ』において明らかにした、広がりと複雑さを有する現代の都市を人々が認識する過程と、ルイ・アルチュセールのイデオロギー論を接続し、後期資本主義の地球規模の全体性を想像する、政治的な営みを認知地図化cognitive mappingと名付けた。The Jameson Reader. (Eds. Michael Hardt and Kathi Weeks, Oxford: Blackwell Publishers, 2000.) 所収のFredric Jameson, “Cognitive Mapping” (初出は1988年)を参照のこと。
-
[3]
『政治的無意識』546頁を参照のこと。
-
[4]
本書エピグラフ(Fredric Jameson and Film Theory, Eds. Keith B. Wagner, Jeremi Szaniawski and Michael Cramer, New Jersey and London: Rutgers University Press, 2022, p.ⅴ.)。
この記事を引用する
藤田奈比古「映画理論の共同体──キース・B・ワグナー、ジェレミー・シャニャフスキ、マイケル・クレーマー編 『フレドリック・ジェイムソンと映画理論 マルクス主義、アレゴリーそして世界映画における地政学』書評」『Phantastopia』第3号、2024年、107-114ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/jameson-film-theory/。(2024年10月22日閲覧)