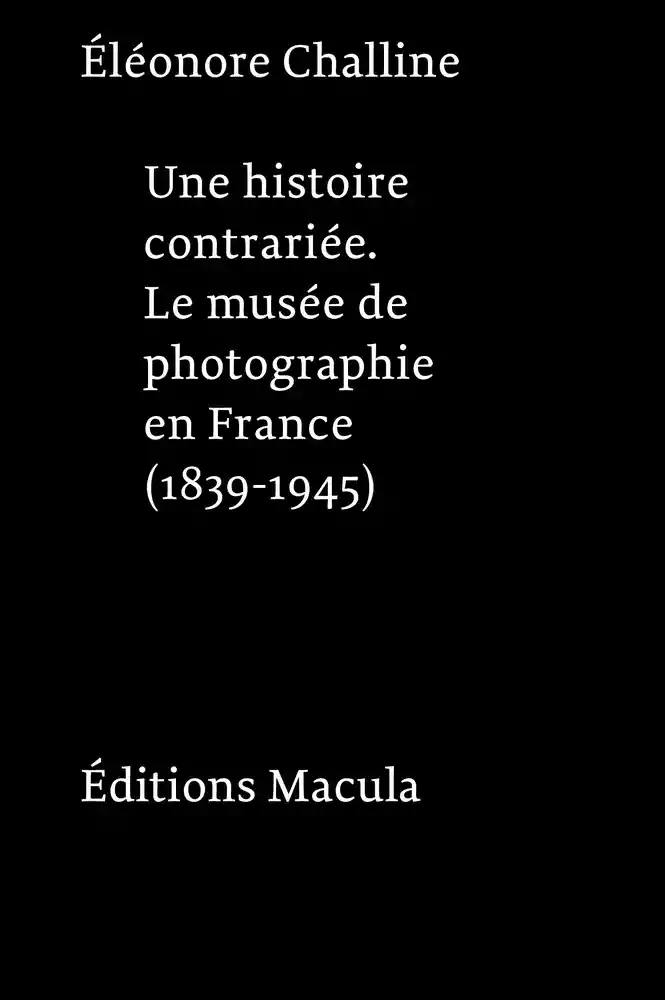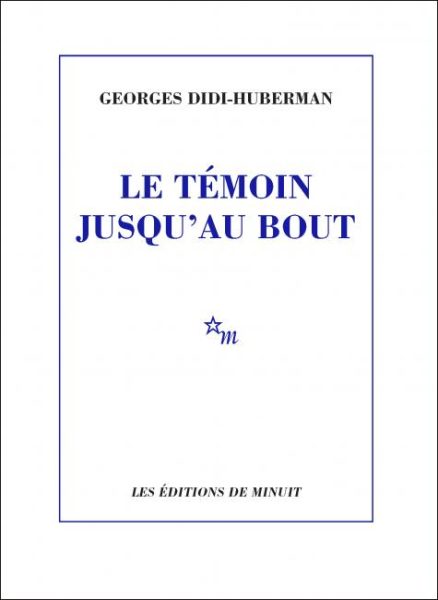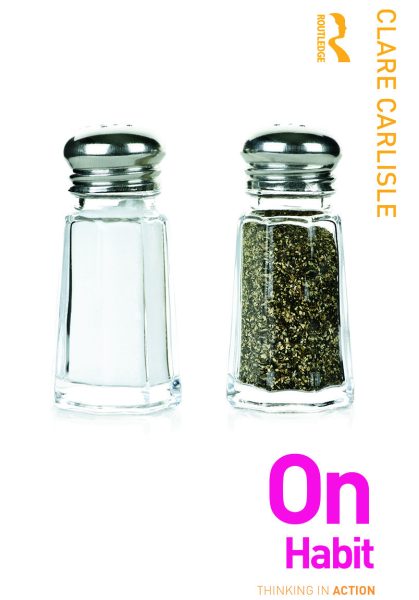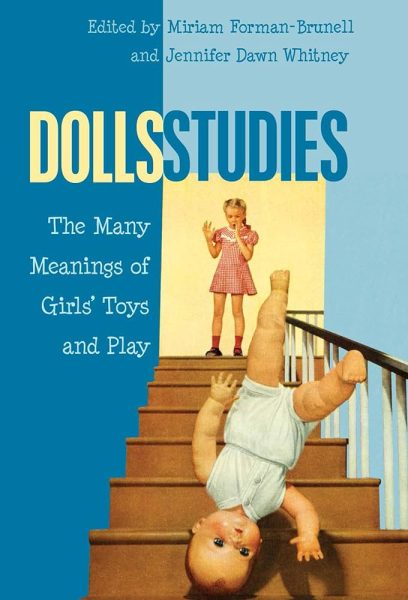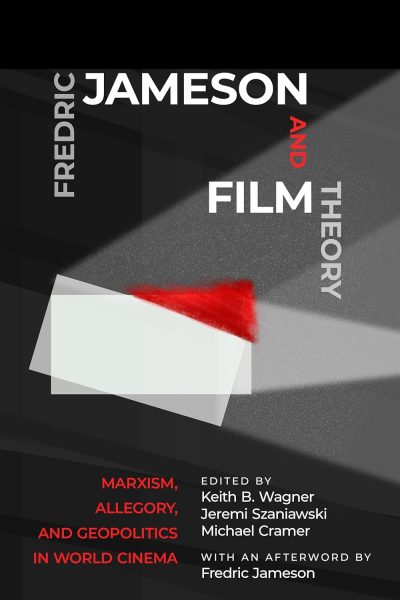p.300日本国内の写真美術館設立の流れを振り返ると、1985年のつくば写真美術館の開設を嚆矢として、1988年に川崎市市民ミュージアムが、1989年に横浜美術館が相次いで開館し、写真部門を持つ美術館が拡大していく動きがあり、翌年の1990年には東京都写真美術館が一次開館することになる。一見すると、これらはある時代の流れのなかで自然発生したかような印象を与えるものの、民間の設立活動が先だって存在していたことが知られている。実際のところ、生まれて間もない新しい芸術ジャンルが、公的な後ろ盾を得て一つの制度=美術館となるためには、その運動に関わる人々の願いや実際の行動のみならず、それぞれの時代が課す政治的、経済的因子、蓄積された実践、批評言説、制度化への欲望がある時に結晶化するのを待たなければならないのだろう。
p.301『妨げられた歴史──フランスの写真美術館(1839-1945年)』(2017年)は、フランスの写真美術館設立運動の歴史を、一次資料調査に基づいて提示したものである。物理学者フランソワ・アラゴ(François Arago)によって「最初」の写真技法ダゲレオタイプが公表された1839年から、美術批評家レイモン・レキュイエ(Raymond Lécuyer)が著した1945年の『写真の歴史』までの期間を分析対象とする本書は、幾度も試みられたパブリックな写真美術館設立運動がいかにして頓挫したのか、その詳細な歴史を500頁にわたって論じている。
日本の場合と同様、フランスにおいても民間の写真協会が中心となって進められた写真美術館設立運動の歴史は、困難な歴史を辿った。ダゲレオタイプは公表直後の1841年に自然史博物館へ収蔵されている事例があり、写真作品は自然なかたちでパブリック・コレクションの一部となっており、大きな混乱は生じていなかった。新しいイメージ・メイキングへの純粋な関心から始まった美術館と写真との関係は、写真美術館設立運動が始まるや否や困難な局面を迎えることとなった。シャリーヌが提示するさまざまな事例をここに列挙することは控えるが、1894年、写真界の有志によってパリに開設された資料写真美術館(Le Musée des photographies documentaires de Paris, 1894-1907年)の失敗は、象徴的な出来事として詳細に論じられている。当時、高等装飾美術学校で写真術を講じていたレオン・ヴィダル(Léon Vidal)を中心として進められたこの写真美術館の開設にあたっては、プロヴァンス地方資料写真美術館、ベルギー資料写真美術館、スイス資料写真美術館など国内・周辺国の資料写真美術館と協調しながら、コレクターの寄贈によって作品収集が進められた。科学的な側面において写真を専門としていたヴィダルは、資料写真美術館の設立以前から写真が「証言による証拠の価値(valeur de la preuve testimoniale)」を持つとし、自動的に生成されたグラフィック資料としての価値を見出していたため、写真とは世界の忠実なコピーであるというイデオロギーに突き動かされ、資料写真美術館はヴィダルのイニシアティブのもと年々所蔵作品点数を増加させていく。1903年には6万5千点であった所蔵点数は、1904年には8万点、1905年には10万点に達する。その抑制の効かない、無差別的な収集活動によって、作家の手が介在する美術としての写真の性質は矮小化されてしまい、単なる複写写真の資料館と化してしまったこの新しい美術館は、1907年、前年のヴィダルの死を機に、短い歴史に幕を閉じることとなる。
ここで問題となるのは、写真の資料的価値と美術的価値の双数的関係である。すなわち、新たに設立される美術館は写真技術による複製あるいは複写を展示する美術館(musée des photographies)となるか、あるいは写真の歴史、技術、芸術的性質を展示する美術館(musée pour la photographie)となるかという点で、批評空間の分裂が避けられなかったのである。
フランスの美術館設立運動は、写真を制度化するための明確な批評基準をもたないまま突き進むことになった。シャリーヌが提示する写真美術館史において決定的であったのは、1939年にコレクターのガブリエル・クロメール(Gabriel Cromer)が収集した膨大な古写真コレクションの大半がアメリカ合衆国の企業コダックの手に渡り、新設のジョージ・イーストマン・ハウスに収蔵された出来事であった。フランスでは1930年代に行政の支援のもと、クロメールのコレクションを基盤に、1937年の万国博覧会での写真美術館開設が発表されるものの、財政上のp.302問題から計画は15回に渡って修正を加えられ、当初の予定より大幅に規模が縮小されて仮設の「写真・映画・音響館(Pavillion Photo-Ciné-Phono)」が開設され、美術館開設は見送られたことで写真界に失望が広がっていた矢先の事件であった。これ先立ってベレニス・アボットがウジェーヌ・アジェの写真を購入し、作品がニューヨークに流出していたことから、フランスの写真界は一連の苦い経験を味わうことになったのである。
シャリーヌの議論は美術史の流れだけでなく、理論的パースペクティブをも提示する、示唆に富んだ内容になっている。フランスの先行する写真研究(例えばオリヴィエ・リュゴン『ドキュメンタリー・スタイル アウグスト・ザンダーからウォーカー・エヴァンズへ』(2001年)[1])においてしばしば問題となる、写真の資料としての価値=ドキュメンタリー的価値が美的価値へと転換される美術史の流れや批評理論をめぐる議論が、美術館設立に併せて行われた写真批評基準の確立においても作用しているのである。フランスに先立って写真作品を積極的に制度化したアメリカ合衆国の場合、ニューヨーク近代美術館がウォーカー・エヴァンズの写真作品を評して、客観的な装いをした写真の資料性ゆえに、超越性が帯びるというドキュメンタリー写真に関する言説空間を展開し、1938年の初の写真家による個展「アメリカン・フォトグラフス」の開催に大きな影響を与えるのだが、フランスにおける資料性重視の言説の流行による制度化の「失敗」の事例を見ると、ニューヨーク近代美術館の論理が非常に戦略的な効果を帯びていたことが明らかになるのではないだろうか。
本書は初期コレクターらのテキストや略歴など、巻末資料として付されたテキストの資料性も高い。本書を通読して気付かされるのが、美術史家セルジュ・ギルボーが『いかにしてニューヨークは近代芸術の概念を盗んだのか』(1983年)[2]で描き出したように、近代芸術のヘゲモニーがフランスからアメリカへと移ったことに対する、大西洋を挟んだ二国間の文化的交渉の複雑さである。本書は、フランスの写真美術館建設運動の歴史だけでなく、写真というジャンルにおける批評価値の変遷や、フランスの写真コレクションの一部を利用したアメリカにおける写真コレクション形成の歴史を見通すことも可能であろう。
この記事を引用する
桑名真吾「写真が辿った困難な道のり──エレオノール・シャリーヌ『妨げられた歴史 フランスの写真美術館(1839-1945年)』書評」『Phantastopia』第2号、2023年、299-302ページ、URL : https://phantastopia.com/2/une-histoire-contrariee/。(2025年07月16日閲覧)