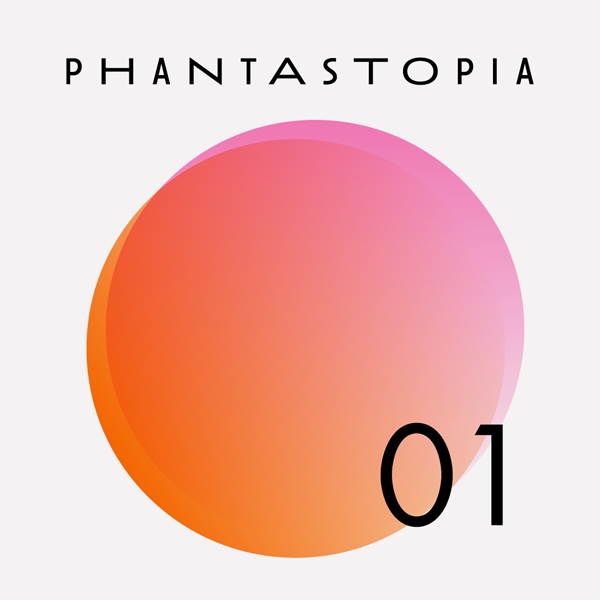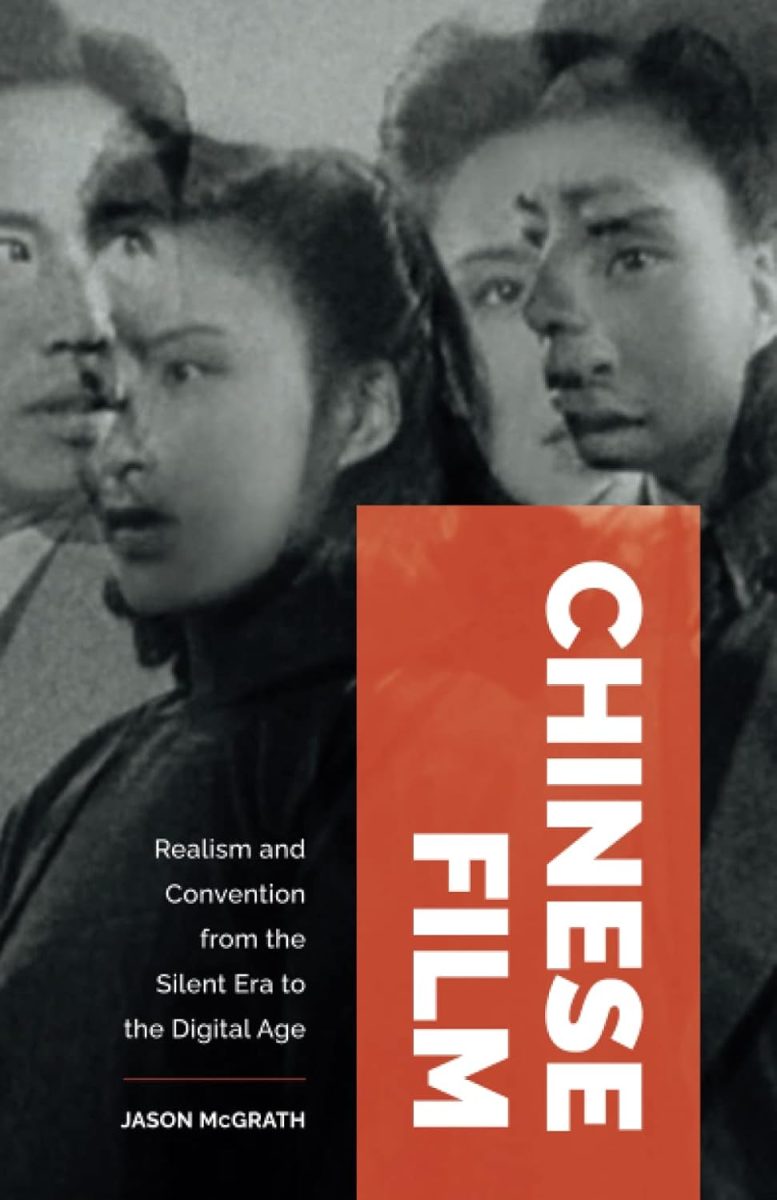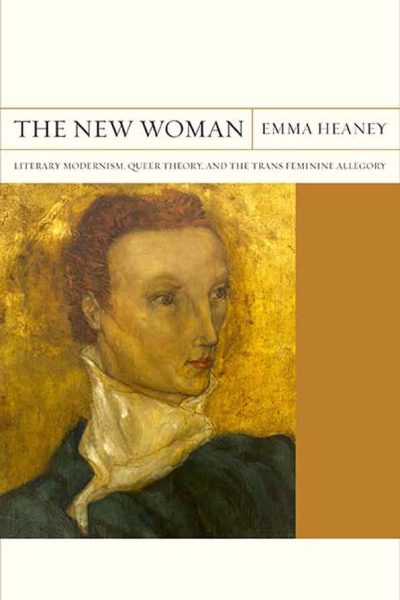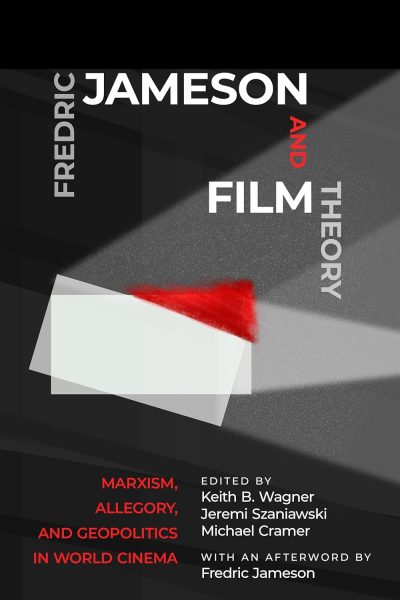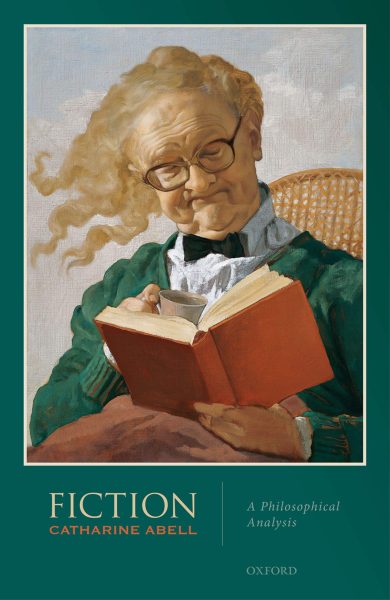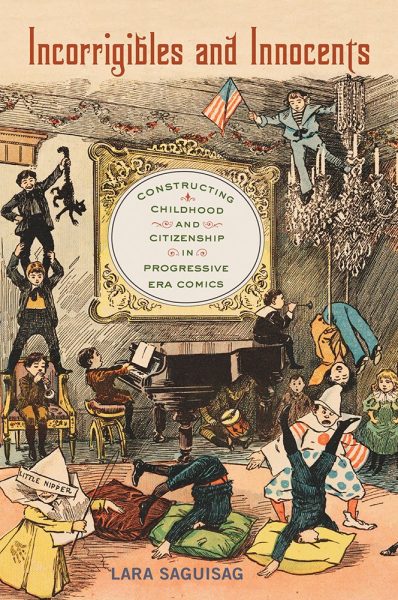アメリカの科学哲学者のアーサー・ファインは、1984年に「リアリズムは死んだ」[1]と宣言していた。にもかかわらず、リアリズムへの関心は人文科学の諸分野において活発な議論を引き起こしている。特に今日、我々の目の前に現れるのは、現実の基準を無視し、個人の率直な感情や意見に訴えかける「ポスト・トゥルース」という現象である。リアリズムの擁護者は、知識によって指し示される事物が、人間の存在から独立して実在すると唱える。一方で、リアリズムの反対者は、知識が世界を説明する一つの手段に過ぎず、事物の本質を特別に解明しているわけではないと主張する。結局、知識は特定の目的や視点に応じて世界を切り分けるための、選択可能な言葉を提供するものとして捉えられる。リアリズムの概念を巡る論争は、現実的な変革を導くことを目指し、特定の時期で独自の発展を成し遂げていた中国映画にも痕跡を辿ることができる。ジェイソン・マグラスの『中国映画 サイレント時代からデジタル時代までのリアリズムと慣習』は、まさに中国映画の枠組みで上述のリアリズムの諸課題をテーマにした学術書である。
シカゴ大学で博士号を取得し、現在ミネソタ大学ツインシティーズ校で教鞭をとるマグラスは、ポスト社会主義期における中国映画と文学に関する数多くの出版物を執筆している。その業績は多様な資料に基づく綿密な調査と堅実な理論の枠組みによって知られ、リアリズムに関して常に鋭い洞察を提供している。前作『Postsocialist Modernity: Chinese Cinema, Literature, and Criticism in the Market Age』(ポスト社会主義者のモダニティ:市場経済時代における中国の映画、文学と批評)は前衛文学や商業文学、独立映画や娯楽映画といったグローバル化の文化的産物を中心に据え、ポスト社会主義期(1990年代初頭から2000年代まで)の現代性を批判的視点で探究するものである。この本が出版されたのは2008年、すなわち北京オリンピックが開催された時期であり、中国が世界貿易機関(WTO)に加盟して以降、米中関係が比較的良好だった時期でもある。その後、世界金融危機やパンデミックを経て、米中関係は冷戦時代を彷彿とさせるほど悪化してきている。十数年ぶりの新刊『中国映画 サイレント時代からデジタル時代までのリアリズムと慣習』は、この地政学の変化を踏まえ、サイレント時代からデジタル時代までの中国映画史を振り返るとともに、中国映画におけるリアリズムの独自の特徴と、それが欧米の知識体系とどのように関連するかを探求する試みとしても、非常に読み応えのある一冊となっている。
本書は序章から結論まで全九章で構成される。著者は、リアリズムが中国映画史を理解するための不可欠な概念であり、中国の文化的・イデオロギー的背景や現代化への追求を理解するためにも重要であると序章で主張する。工筆画や写意画など、伝統的な知識人による芸術には、事物をありのままに描写する客観性や写実性が見当たらない。逆に、意味、感情、観念、意図といった抽象的な要素が強調され、芸術はそれを通じて私たち自身や周囲の環境に深く刻み込まれるものとされ、外部の現実へと導く技術的手段としての役割を持つと考えられる。この特徴を前提とし、「実体論的にではなく、あくまで関係論的に構成されてきたのだ」[2]という言語学者であるロマン・ヤコブソンのリアリズムに関する言説を軸に、古今東西のリアリズムの言説を渉猟したうえで、著者は芸術と現実の関係をめぐり、中国映画のリアリズムを六つのパターンに分類する。以下に、これらのパターンを簡潔にまとめる。
- 本質的リアリズム:撮影技術は物理的現実に対して独自の親密さと直接的関連性を提供する。構成された物理的現実は実際の離散的物体である。その証拠に、それは少なくとも記録や測定が可能で、カメラなどの機械を通じてある程度理解できる。
- 知覚的リアリズム:映像と既存の現実との本体論的関係を強調せず、動的な映像によって観客の注意を惹きつける。現実と幻覚の間と、人間の五感によって構成される感性と映像の人工性によって構成される理性の間で、絶え間ない折衝と衝突が繰り広げられている。
- 虚構的リアリズム:物語世界への没入を促す傾向があり、虚構の世界は一時的に現実として捉えられる。観客は登場人物に対して積極的または消極的に感情移入しながら、物語を楽しんでいる。ここで、虚構世界が現実世界と似ているかどうかは重要ではない。
- 社会的リアリズム:あらゆる社会問題を容赦なく精確に反映し、社会批判の機能を暗示するとともに、社会進歩の基盤を築くことにも貢献する。ただし、この描写が必ずしも暗黙の改革やその過程に奉仕する必要はない。
- 規範的リアリズム:映画が表現しようとするのは、単なる現実そのものだけではなく、表面の下に隠れている、あるいはまだ完全に実現されていない、より深い現実である。映画はそれを抽象的な形式や理想として提示することで、観客により高次元かつ深層の現実を意識させ、その実現へと導くことを目指している。
- 否定的リアリズム:現実はリアリズムという表現形式で説明できるものをはるかに超え、計り知れない複雑さと豊かさ、多層性と神秘性を備えている。そして、表象を超越する何かの存在こそが重要である。この何かはシステムを脅かす一方で、システムからの解放を約束する可能性をも内包する。
著者によれば、これらのパターンは互いに分離されることなく、状況によっては結合と転換を繰り返している。それは、普遍性の概念を再検討するほか、時代性や社会性といった外部の環境に重点を置き、映画がどのように現実と複雑に関わっているのかをも探求するためである。このように、著者は想像力と整合性を維持しつつ、さまざまなパターンを広い歴史的な文脈の中で検討し、それぞれの時期に流行している政治と文化の潮流と対話することで、急進的な構成主義者が抱えている問題─自然や歴史といった物理的現実を恣意的に解釈する姿勢に対処しようと試みる。続いて著者の各論点を時系列に沿って簡潔に紹介する。
20世紀初頭、中国が世界の歴史の地殻変動に巻き込まれているうちに、映画は新たな芸術として登場し、その記録性と写実性の魅力から伝統的な舞台芸術とは異なる地位を築いている。映画に見られる科学主義の教化作用が、文化闘争の主戦場として中国現代化の初期段階と緊密に連動している様子は、サイレント時代の伝説的女優の阮玲玉の写真に対する著者の分析から窺える。光と影による科学の検証に基づいた本質的リアリズムは、映画の芸術的価値を最大限に高めるばかりでなく、現代技術の概念として旧来のイデオロギーに挑戦することも提示する。現代性の象徴である映画は、身体的・感情的なレベルで経験されることなく、欧米社会の価値観や生活様式を丸ごと取り込めるユートピア的なものとして、五・四新文化運動など社会運動の影響を受けた当時の知識人に受容されたのである。
1920年代から30年代のファシズムの台頭とプロレタリア運動の展開に伴い、アメリカを皮切りに世界は深刻な経済恐慌と政治不安定化の時期に突入した。明星、聯華など上海を拠点とした映画会社のもとで、左翼映画運動が展開され、短い期間ながらも中国映画の黄金時代が到来した。著者によれば、これらの映画には、低層社会の人々が直面する絶望的な貧困や失業の問題への描写に加え、技術の進化を成し遂げるビジュアルの慣例やステレオタイプも随所に見られる。具体的な例として、『女神』(呉永剛、1934年)、『街角の天使』(袁牧之、1937年)、『十字街頭』(沈西苓、1937年)など左翼映画と、『第七天国』(フランク・ボーゼイギ、1927年)や『南海の劫火』(キング・ヴィダー、1932年)など上左翼映画に多大な影響を与えたハリウッド映画が取り上げられ、対照的に分析される。ハッピーエンドといったハリウッド映画の紋切り型の物語構造に余白を生じさせ、物語の制約を回避することを可能にする左翼映画は、反帝国主義、反植民地主義、資本主義批判といった主流の言説と批判的に統合することで、革命的衝動を具現化し、小市民に新たな統一社会の可能性を強く想起させようとする。著者は、未完の可能性や未解決の対立を暗示する物語を通じて、観客が表面的な娯楽性を超え、危機に瀕した社会の中で革命の主体として生まれ変わると論じる。そのため、左翼映画はハリウッド映画の慣習を積極的に借用・模倣したものの、ハリウッド映画の東洋版にはならなかったと考えられる。
日中戦争の終結後、批判のための社会的リアリズムから国家建設のための社会的リアリズムへの形式的転換を示し、映画は資本主義から社会主義への移行という歴史の転換期において、新たな革命の可能性を曖昧化にしたと考えられる。著者は、歴史の不可逆性を描きながら戦争のトラウマを癒す『春の河、東へ流る』(蔡楚生・鄭君里、1947年)、時間性の崩壊により生命が現実の虚無に囚われ、前向きになれなくなったかのように感じさせる『田舎町の春』(費穆、1948年)、そして歴史の必然性と出来事の偶然性が融合し、新たな秩序の誕生を暗示する『からすとすずめ』(鄭君里、1949年)を取り上げ、この時期の社会的リアリズムが美学的表現の追求にとどまらず、政治的行動と社会的実践をも促していると分析する。つまり、映画を通じて感情の混乱と停滞のプロセスを体験することで、当時の観客は現代性の回復と現代化の運動への参加を暗黙のうちに促されたのである。
建国後の十七年時期において、1942年の毛沢東による「延安文芸座談会における講話」の精神を発展させる文化芸術の制作理念の下で、芸術家は社会の病巣を暴露したうえで、進行中の革命的未来を讃えることが求められる。『白毛女』(王浜・水華、1951年)、『青春の歌』(崔巍・陳懐皚、1959年)、『紅色娘子軍』(謝晋、1961年)などの革命映画は、革命闘争や英雄譚、半植民地や半封建社会の神話を覆す歴史的物語を繰り返し語ることで、観客に一定の解釈や消費の余地を許容しつつ、国家の想像力を育み、新たに確立された政治権力を支える役割を果たしている。ここで、著者は言語学の「規範文法」という概念を借用し、革命映画を規範的リアリズムという広範な概念に組み込むことで、映画が表層的な現実を超えて抽象的なイデオロギーの真理を描き出すことを最優先し、より深い現実や未来の投影を認識させる役割を担っていることを明らかにする。
1970年代に入ると、革命映画に代わって模範劇が社会主義体制下の形式主義の頂点に達し、未完成の状態や批判的思考を表現していた過去のリアリズムとは大きく異なっている。著者は、その違いについて次のように論じる。模範劇において、革命はもはや曖昧な可能性でも、結末が開かれたものでもなくなる。これらの作品は、プロレタリア革命の最終的な勝利への願望を壮大かつ完結した形で表現している。また、厳格な基準のもとで俳優、芸術家、音楽家が達成した高い芸術的品質によって広く人気を博し、永続的な美的魅力を保ち続けようとする。こうして、模範劇の持続的な遺産は、革命の過程をないがしろにしてしまい、勝利の結末を永続させるものとなる。模範劇は現状から乖離しているように見えるかもしれないが、本質的リアリズムの観点から見ると、これらの作品に真の価値があるとすれば、それはパフォーマンスを徹底的かつ忠実に記録するという行為に秘められている、という著者の洞察は実に意味深い。
改革開放政策下の中国映画のリアリズムについて、著者は従来の世代論という枠組みを超え、この時期の中国映画の製作を、総合的かつ包括的な歴史的課題や感情的構造、さらに政治経済システムにおける美学的実践として捉えている。初期の第四世代および第五世代の監督たちは、歴史的課題をリアルに描写するためにドキュメンタリーの撮影手法を取り入れ、芸術と政治の自律性を高めながら、脱政治化されたイデオロギーを表現している。1990年代に入ると、周縁化された人間に焦点を当てる第六世代の監督たちは、中国がグローバルな新自由主義の経済秩序に再統合される動きに対し、批判的な立場をとるようになる。彼らは偉大な英雄像の描写を拒否し、人間性を回復させると同時に、政治経済システムが内包する資本主義の諸問題を容赦なく暴き出している。ここで、文化芸術領域の開放政策によって確立されたリアリズムの撮影方法は、アンドレ・バザンのワンシーン・ワンカットの美学から影響を受け、ある程度で1930年代の上海の左翼映画を想起させる。これらの方法が様式化されると、制約を打破しようとする映画製作者たちは、硬直した構造を反芻しながら変形させていく。第四世代から第六世代までの代表作を整理し、直線的な歴史概念に疑問を投げかけ、さらにそれを解体する著者の試みには、この時期の映画形式の多様化を動的に継続する過程として捉えようとする姿勢が感じられる。
芸術映画の議論に加え、著者の分析は商業映画の領域にも及んでいる。CGIなどのデジタル技術と大量の資本流入に支えられた商業映画が、ハリウッド映画と同等のレベルで競争する力を持ち、重要な地政学の変化とともに新たな規範的リアリズムへと向かう傾向は、巨大化し続ける2010年代の中国映画産業の特徴である。映画がもはや写真のような本質的リアリズムに基づくものではなくなり、仮想的リアリズムという人工的な映像に依拠するようになるこの時期において、デジタル技術の造形的アプローチへの試行錯誤は、中国映画におけるリアリズムの歴史的地図を完成させることにもつながる。ここで、著者は同じく地球滅亡の危機をテーマにし、大ヒットしたSF映画『インターステラー』(クリストファー・ノーラン、2014年)と『流転の地球』(郭帆、2019年)を取り上げて説明する。カメラが固定された状態で写実性を提示する前者とは異なり、仮想的リアリズムの特徴と伝統文化の慣習を巧みに融合する後者は、現実には不可能なアングルや運動で構成された長回しショットを駆使することで、観客に崇高さや驚きを体験させる。『流転の地球』のような商業映画は、ハリウッド映画のノウハウを積極的に吸収すると同時に、ハリウッド映画もまた、直ちにこれらの映画に見られる慣習を取り入れつつ、世界の映画興行市場における特権的地位を維持しようとする。米中の政治的対立が依然として存在しているものの、少なくとも映画の世界ではそれに柔軟に対応する可能性があると信じつつ、著者は前向きな姿勢で論述を締めくくる。
以上の分析を通じて、サイレント時代から今日のデジタル時代に至るまで、映像の最も重要な本質は運動であると認識するとともに、運動感の欠如や希薄さは長年にわたる中国映画のリアリズムの病理であり、さらにそれが現代化の過程で苦闘する中国社会の縮図でもあると、著者は鋭く指摘する。さらに言えば、現実世界の出来事の記録や真実らしさの効果の追求から解放され、実質的な変化に応じて、監督、観客、そして映画自体が、絶え間ない運動と変化の中で、適切なタイミングと内なる力をもって合理的な伝達方法を模索していくことが求められる。言い換えれば、特定の歴史的段階においてリアリズムの効果がどのように達成されたのかを理解するためには、鑑賞のプロセスそのものを、科学的かつ想像力豊かに構築することが重要である。メディアミックスが急速に展開しているデジタル時代において、映画がどのように現実を表現するのかに関する議論がいまだ結論に至っていないように、映画というメディアの創造力は進化し続け、リアリズムへの探求も尽きることはないだろう。
最後に、本書を通読してインスピレーションを受けたもう一つの点について述べておきたい。著者は中国映画におけるリアリズムを六つのタイプに分類しているものの、否定的リアリズムに関する論述は極めて少なく、本書の表紙を飾った『田舎町の春』という一作のみに焦点が当てられている。否定的リアリズムに対応しているように見えるが、移行期の中国映画における否定の美学は、閉鎖性と意味への抵抗を示しつつも、「春景を恋しく思いながらも、それを引き留めることができない(无可奈何花落去)」[3]という心情を表しており、あらゆる確実性と座標を見失う傾向も暗示している。その後の歴史の展開が示すように、否定の可能性は新たな主体性を生むことなく、時代の流れに埋没していく。歴史発展の不可逆性に囚われ、現状への不満や他者への不信感に苦悩するという自壊の病理と、その治療の試みは、『山河ノスタルジア』(ジャ・ジャンクー、2015年)や『サタデー・フィクション』(ロウ・イエ、2019年)など、かつて主流社会の思想に断固として抵抗してきた第六世代の大衆向けの作品にも垣間見える。形式的には現代美学と伝統文化の融合を示しつつも、実際には戦後の現代社会を生きる人間の無力感や虚無感を再び体験させるこれらの映画とは異なり、著者は結論の部分で、『凱里ブルース』(ビー・ガン、2015年)をはじめとする映画が、ポスト社会主義期の容赦ない現代化の過程から取り残され、既存の中国映画のリアリズムの枠組みにも回収されないと述べている。脱中心化や脱領土化による新たな主体性を意味する否定的リアリズムの真髄として、このような映画に関する発掘調査は、中国映画研究のもう一つの重要な方向性であるに違いない。
註
-
[1]
Arthur I. Fine, The Natural Ontological Attitude, The Philosophy of Science, Richard Boyd, Philip Gasper, J. D. Trout(eds), MIT Press,1984, pp.261.
-
[2]
北村直子、「リアリズム小説の換喩的性格」、『人文學報』第103号、京都大學人文科學研究所、2013年、103頁。
-
[3]
『田舎町の春』の政治性については、中国語圏の研究者であるDavid Der-Wei Wang(The Lyrical in Epic Time : Modern Chinese Intellectuals and Artists Through the 1949 Crisis, Columbia University Press, 2015, pp.332-343.)やZhen Zhang(An Amorous History of the Silver Screen, University of Chicago Press, 2005, pp.89-117.)は、否定の美学を創造的な自己変容の試みや感情の実践として論じる。しかしながら、マグラスはこれらの論述に潜む文化本質主義的な傾向を指摘した上で、否定の美学は観客に動揺をもたらすことなく、周期的に個人の欲望の衝動と、それが抑圧されることで生じる虚無感の間を行き来するに過ぎないと批判的に検討する。ここではひとまず、この論述を通読する際に頭に浮かんだ、北宋時代の婉約派の小令作家である晏殊の詞を引用し、懐古趣味を持ちながら固定された自己イメージを作り上げるという『田舎町の春』の否定の美学が、個人の感情に訴えかけるポスト・トゥルースの現象と接続する可能性を強調する。
この記事を引用する
王宏斌「冷徹な時代を生き抜くこと──ジェイソン・マグラス『中国映画 サイレント時代からデジタル時代までのリアリズムと慣習』書評」『Phantastopia』第4号、2025年、74-81ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/chinese-film-realism-and-convention-from-the-silent-era-to-the-digital-age/。(2026年02月27日閲覧)