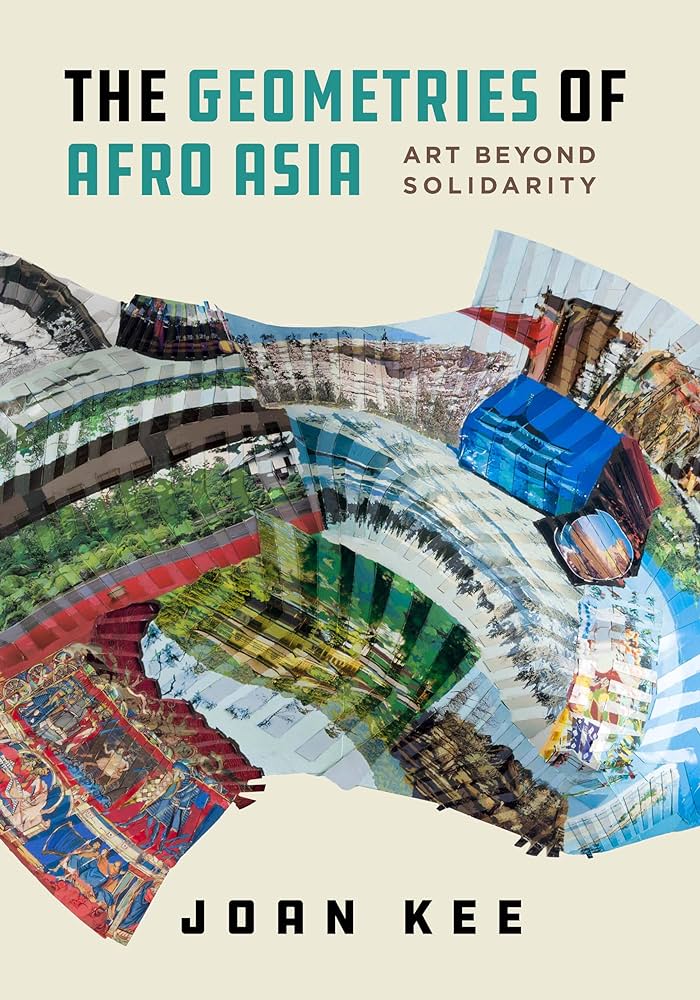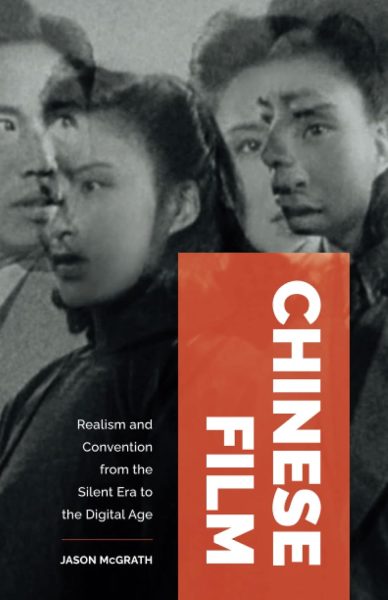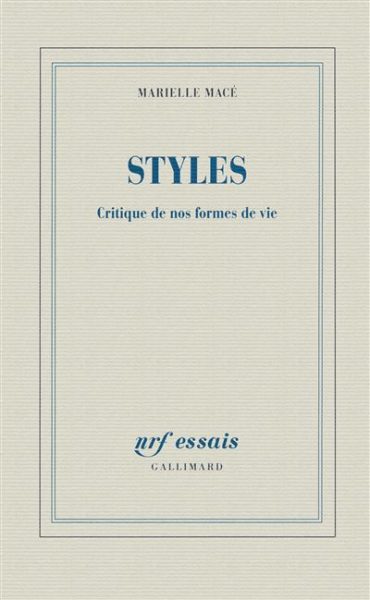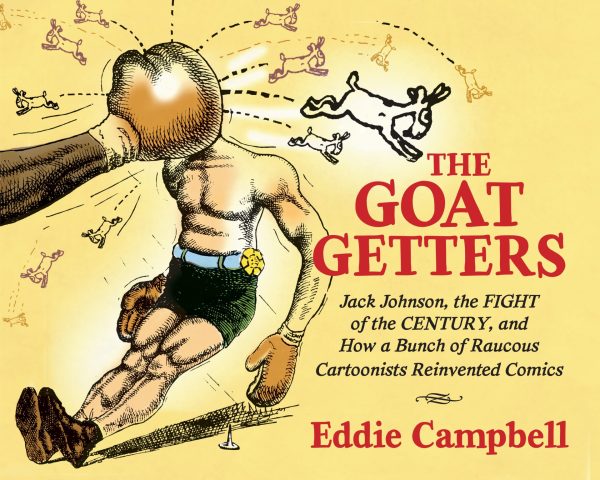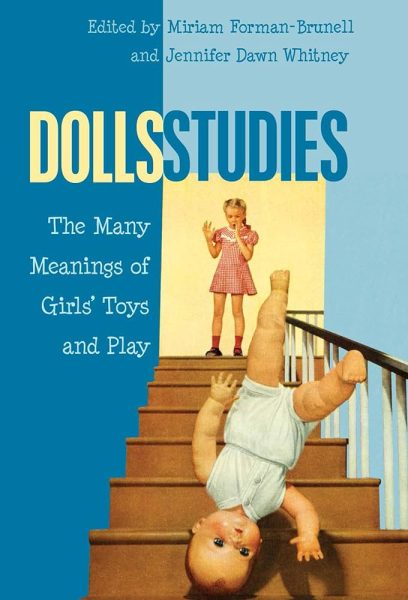ソーシャルメディア、オンラインサービス、航空輸送といったトランスナショナルな流通ネットワークの進展は、いずれも現代のグローバル社会の基本的な条件として、ここ数十年のうちに人類の生活様式を大きく変容させた。その構造的な転換は、他方で、美学的な生産物の歴史を伝統的に扱う美術史という学問分野の方法にも、少なからず反省の契機を与えてきたように思われる。例えば、国家という枠組みの自明性が問われる今日、一体どこの誰が(何が)、どのように語られるべきなのか? あるいは、人種や民族、ジェンダー、地域の歴史が互いに重なりあうなかで、作品や作家の「つながりconnection」や「めぐりあいencounter」はいかに把握されるのか? こうした歴史学的な問いは、今日のいわゆる「グローバル・アート・ヒストリー」や「ワールド・アート・ヒストリー」といった関心に連なるものと考えられるが、その肝心の答え合わせは、現代のこれからの美術史が直面すべき根本的な課題といえる[1]。
ジョアン・キーによる本書『アフロアジアの幾何学 連帯を超える美術』(2023)が焦点を当てるのもまた、その「めぐりあい」の一つ、第二次世界大戦後の国際社会におけるグローバリズムの文化的錯綜である。著者のキーは『アートフォーラム』や『サードテクスト』などで執筆するアメリカの美術史家で、すでに韓国の「単色画」に関する研究や戦後アメリカ美術と法の問題を扱う著作で知られている[2]。また、2015年には日本での国際シンポジウムに参加しており、そこでの講演が記憶に新しい読者も多いかもしれない[3]。彼女の3冊目の単著となる本書では、ロサンゼルス、ソウル、沖縄、ケープタウンなどを舞台に、1960年代から2010年代までの作品や言説が、全5章にわたって論じられている。各章が分析する個別の作品群は、互いにその制作背景や文脈、表現媒体を異にするが、本書ではいずれも「連帯を超える」アジアとアフリカの文化的協働の可能性を明かすものとして期待される[4]。
異なる地域や民族同士の多層的な関係を考察する本書の理論は、二十世紀後半のグローバルな文脈として、アジアとアフリカを含む、第三世界やグローバルサウスといった地政学的な区分、およびバンドン会議以後の非同盟運動における中立主義を重視する。だが、その画期となる着想の背景には、「アフロアジア」なるものを、時間的にも空間的にも「活気に満ちた幾何学」とみなす態度がある[5]。アフロアジアとは「アジア」に「アフリカ系の、アフリカ風の」を意味する「アフロ」を附与した合成語であるが、本書はそれを各地域に由来する作品やその形式の異種混淆性ではなく、個別の形象が互いに擦れ違う瞬間に生じる時空間的な関係の諸相として使用する[6]。「横断性transversality」、「入射角angles of incidence」、「隣接adjacency」、「同時発生coincidence」、「位相topology」といった幾何学の概念が散りばめられた各章では、作品の表象に加え、周辺で発生した社会的かつ文化的な諸要素間の接触が幾度となく議論され、その明瞭な分析と主張は本書の醍醐味である[7]。芸術実践を単なる形式ではなく、人種的、国家的、イデオロギー的に複雑な状況が畳み込まれた幾何学として把握する著者の手つきは、一方では詩的な隠喩に満ちつつも、全体として対象の歴史的な厚みを鮮やかに描きだす。
例えば、第1章のメルヴィン・エドワーズとロン・ミヤシロに関する分析は、本書の白眉と言ってよい。エドワーズとミヤシロは共に1960年代のロサンゼルスを拠点に活動した作家で、彼らの作品はこれまで同時代のミニマリズムやフィニッシュ・フェティッシュといった美術動向との比較から考察されてきた(あるいは、等閑視されてきた)。本書はそれに対して、二人の作品を周縁的なものとして積極的に同期させることで、両者に共通する人種的な身体経験の痕跡を抽出しようと試みる。作品が互いの存在理由を補強しあう相補的な関係に注目する本書の方法を、著者は法学の用語に倣い「傍証的比較corroborative comparison」と呼ぶが、その論証の根底には従来の比較分析における様式の中心性に対する批判を認めることができる[8]。ほかにも本書では、大戦後のソウルと沖縄で共に人種的な多層性を見つめたジュ・ミョンドックと石川真生の写真(第2章)や、現代アフリカにおける中国の存在感を反映した「アフロチャイナ」の表象(第5章)などが紹介され、いずれも独立した個別の批評として興味深い。
そのうえで、本書を読み解くために重要だと思われるのは、著者の主張するアフロアジアの「連帯を超える」協働のあり方である。注目すべきことに、本書で言及される数々の芸術実践が同時代の社会的結束に対して直接に関与することはほとんどない。むしろ著者は、例えばエドワーズとミヤシロが1965年のワッツ暴動に作家として関心を示しつつも「組織された政治運動」には消極的であった事実を指摘することで、アイデンティティに基づく連帯の政治と彼らの実践の間にある明確な距離を示唆する[9]。「連帯を超える美術」という本書の副題は、著者の立場を端的に伝えるが、その主張はとりわけ、第4章におけるバイロン・キムとグレン・ライゴンの協働関係に託されている。共にニューヨークを拠点とする両者の協働制作では、多くの場合、どちらか一方の作者性が強く意識され、著者はその関係を他者の自律性を尊重しつつ自己陶冶を促す「非取引的関係nontransactional relationship」として高く評価する[10]。たしかに本書が考察する作品や作家は、キムやライゴンの場合のみならず、基本的に明確な抵抗運動を行使しない。しかし、このように全編を通して著者が頻りに強調するのは、まさにアフロアジアの非取引的関係に内在する新しい可能性に向かう推進力である。
以上のように、本書の中心的な主題は、特定の作家や作品の分析というよりもむしろ、その周囲の多層的な文脈から形成される影響関係の布置であったといえる。しかし他方で、その考察は総じて、アフロアジアの生産的な側面を強調しすぎるあまり、議論の対象に含まれる抑圧や権力関係の作用を低く見積もる傾向がある。例えば、第3章のデイヴィッド・ハモンズとフェイス・リンゴールドの掛け軸型の作品に関する分析では、作家の明白なオリエンタリズムがほとんど問題とされないまま議論が進められている[11]。また、同様の問題は、同じ章で扱われるホワルデナ・ピンデルの場合にも指摘できる。ピンデルは日本での疎外感から後に「自伝」シリーズを制作することになるが、本書において彼女が経験した視線の現実的な攻撃性は、単なる生産的なものとして過小評価されてしまう[12]。このような一方的な論述は、結果として、第3章後半の文化の盗用に関する著者の主張の説得力を奪っているようにすらみえる。
さらに、本書で扱われる作品や作家の選定にも疑問が残る。すでに述べたように、本書の理論的な背景には、バンドン会議以後の非同盟運動がある。第4章のキムとライゴンの関係にも少なからず、その政治モデルが投影されているのだろう。だが、このように第三世界やグローバルサウスの政治状況を前提とするにもかかわらず、その主要地域の作品や作家に対する議論は驚くほど少ない。そもそもアフロアジアという抽象概念と第三世界やグローバルサウスという地域区分がどれほど一致するのかは本書において曖昧であり、仮に著者の議論が第三世界のなかでも特にアジアとアフリカの関係に注目するものであったとしても、本書のアジアの事例は圧倒的に東アジアが多く、かつアフリカの事例も北アフリカのアラブ地域をほとんど含まないことから、地域的な偏りを認めざるをえない[13]。もちろん、研究の射程が著者の専門に制限されることは仕方ない側面もあるが、もし本書がアフロアジアのトランスナショナルな可能性を主張するのであれば、より広範な地域を視野に入れた分析が求められて然るべきである。
著者は本書を通じて、アフロアジアを「ただ人種的、国家的、イデオロギー的、知的な所属に基づくのみならず、感情、認知、感覚の拡散と循環に基づく新しいグローバル・マジョリティの形成を先取りする」ものであると主張する[14]。たしかに本書の幾何学は、西欧中心的で単線的な美術史を再検討する試みの一つとして脱中心的な議論の可能性を示唆する。しかし、すでに述べた理由から、それは研究の方法や対象の選定に関する課題もいくつか提示している。また、アフロアジアの問題は今日、本書の想定よりもさらに展開しているようにみえる。例えば、これまでグローバル社会の多層性に考察の場を与えてきた国際展や芸術祭は、長距離輸送の環境リスクを考慮する脱成長の流れに伴い、開催方式が見直されつつある[15]。したがって、これからのアフロアジアを検討するためには、本書における議論の射程を超え、現在の文化的協働が依拠する制度基盤やその持続可能性を考慮する必要があるだろう。ほかにも、仮想空間やバーチャル・リアリティといった領域との関係も興味を惹く。本書で提起された著者の主張は、このような将来の可能性を踏まえることで、より強固なものとなるはずである。
註
-
[1]
グローバルな文脈からの美術史の再構築は、すでに様々な立場から試みられている。しかし、全体として認識の共有が十分になされているとは言いがたい。ゆえに、本稿では以下に代表的な論集を挙げるにとどめ、その理論的な整理は今後の課題とする。James Elkins ed., Is Art History Global? (New York: Routledge, 2007); Kitty Zijlmans and Wilfried van Damme eds., World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches (Amsterdam: Valiz, 2008); Hans Belting and Andrea Buddensieg eds., The Global Art World: Audiences, Markets, and Museums (Ostfildern: Hatje Cantz, 2009).
-
[2]
Joan Kee, Contemporary Korean Art: Tansaekhwa and the Urgency of Method (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013); Models of Integrity: Art and Law in Post-Sixties America (Oakland: University of California Press, 2019).
-
[3]
Joan Kee, “The Scale Question in Contemporary Asian Art,” The Japan Foundation Asia Center: Art Studies 02, eds. Yasuko Furuichi and Aki Hoashi (Tokyo: The Japan Foundation Asia Center, 2016), 34-41. [ジョアン・キー「アジア現代美術におけるスケールの問題」(松浦直美訳)古市保子、帆足亜紀編『The Japan Foundation Asia Center: Art Studies 02』(国際交流基金アジアセンター、2016年)、124-131頁]
-
[4]
本書の副題より引用。なお、同様の表現は本文中でも繰り返し使用される。
-
[5]
Joan Kee, The Geometries of Afro Asia: Art Beyond Solidarity (Oakland: University of California Press, 2023), 10.
-
[6]
英語圏において「アフロアジア」は、アフリカ系とアジア系の政治的連帯を推進する戦略的な標語として使用されることがある。例えば、近年では以下の論集がある。Fred Ho and Bill V. Mullen eds., Afro Asia: Revolutionary Political and Cultural Connections between African Americans and Asian Americans (Durham: Duke University Press, 2008).
-
[7]
各概念の用法ついては本書の序論に詳しい。ただし、その言説上の有効性は今一度吟味する必要がある。
-
[8]
この「傍証」という概念は、著者の説明によると、作家であるエドワーズの発言に由来する。しかし、それと同時に本稿では、著者自身が美術史の博士号とともに法務博士の学位を取得している事実を指摘しておきたい。
-
[9]
Kee, Afro Asia, 80.
-
[10]
Ibid., 209.
-
[11]
もっとも、日本文化に対するハモンズの関心に、一定のオリエンタリズムが含まれる可能性を著者は認める。だが、特定の地域文化に対する彼のステレオタイプな認識は、本書ではほとんど問題とされないままである。
-
[12]
なお、著者はピンデルの作品を論じるにあたり、ロラン・バルトの『表徴の帝国』(1970)を参照するが、ピンデルとバルトの日本での経験の差異を踏まえると、両者の比較には議論の余地があるように思われる。
-
[13]
作家の地域的な偏りについては、著者自身も自覚的であった可能性がある。その証左として、本書の序論では、本論の内容を補足するかのように、インドやシンガポール、タイ出身の作家が言及されている。
-
[14]
Kee, Afro Asia, 10.
-
[15]
地球環境に対する配慮から国際展の開催を制限する可能性はすでに議論されている。例えば、2023年12月に森美術館が主催した国際シンポジウム「美術館のサステナビリティとは?」においても同様の議題が提出された。シンポジウムの登壇者は、ニューヨーク近代美術館館長のグレン・ラウリィ、南オーストラリア州立美術館館長のラーナ・デヴェンポート、ナショナル・ギャラリー・シンガポール館長のユージン・タン、森美術館初代館長のデヴィッド・エリオット、テート・モダン名誉館長のフランシス・モリス、M+館長のスハーニャ・ラフェル、森美術館特別顧問の南條史生、および館長の片岡真実である。
この記事を引用する
青木識至「めぐりあいの角度──ジョアン・キー『アフロアジアの幾何学 連帯を超える美術』書評」『Phantastopia』第3号、2024年、93-98ページ、URL : https://phantastopia.com/book-review/the-geometries-of-afro-asia/。(2026年02月17日閲覧)