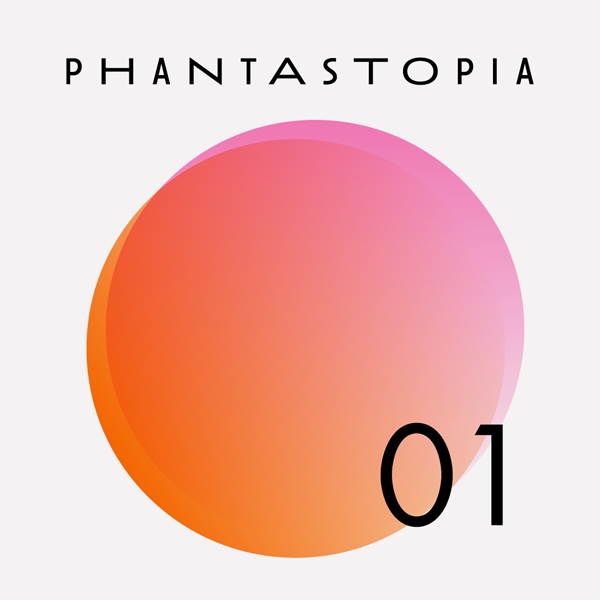当時ひとりあたり1日12トンだった作業量を、科学的マネジメントの適用により47.5トンまで向上させ、作業効率を飛躍的に向上させた──1899年にある製鉄会社で実施された銑鉄運びの実験は、フレデリック・ウィンズロー・テイラーの理論を説明するもっとも有名な事例のひとつである。1911年に発表された『科学的マネジメントの諸原理』(The Principles of Scientific Management)で、現代社会を統べる原理となった「マネジメント」の礎と、いまでこそ世に膾炙した「コンサルタント」という職業形態の原型を築きあげたテイラーは、その功績から「科学的マネジメントの父」と称されて久しい。テイラー主義ないしテイラー・システムと呼ばれるかれの理論の射程は、いかにして労働生産を合理的かつ効率的に再組織化するかという問いに向けられており、それは定量評価や科学的人事制度の導入といったハウ・ツー的な次元から、管理者/労働者という分業体制の構築、さらには労働者と経営者がともに協働するヴィジョンの提示といった組織的な次元にまで広がっている。そしてテイラーの目論見は、マネジメントが「工学の基本的諸原理のような、厳密かつ明確な法則をともなうひとつの技術[1]」であると提示することにあった。だから銑鉄運搬実験は、テイラー主義を説明するひとつのケーススタディであり、かれの企図を読者や聴衆に理解させるための、もっともシンプルなエピソードでもある[2]。
本稿はこの銑鉄運搬実験を出発点として論じるが、しかしそれが上記のような一事例の枠を超え、テイラー主義において、さらにはマネジメント思想史というより大きな枠組みのなかで、特権的な徴を帯びることを明らかにする。あらかじめ見通しを立てておくならば、まずもってこの実験はフィクションであるとの説があり(少なくとも「科学的マネジメント」を標榜するにはかなり非科学的である)、だからテイラーの科学的マネジメント、およびそれを継承するさまざまなマネジメント思想は程度の差はあれ「神話的」である、という主張がある。しかしわたしたちが論証するのは、「マネジメント」(ないしそれを支える科学原理主義)はそもそも神話として制定されなければならないのであり、テイラーの銑鉄運びの「物語」はそれを定礎するものだったということである──ひるがえって以下のことにも注意しておこう。すなわちテイラー主義を取り出してその非合理性を指弾しようとするとき、逆説的に自身が立脚する立場は合理的であるのだという素朴な信仰が開陳されてしまうのであり、本稿はそうした無自覚性を批判することにもなる。繰り返しになるが、テイラー自身がいうように、この実験はテイラー主義の全貌を解き明かすものではけっしてない。しかし重要なのは、本人の認識よりもむしろ、それがどのように周囲へ伝達され継承されていったかということだ。その点「後世になってもテイラーは、自身の論文やボックスリーの自宅で繰り返しおこなわれた談話、全国各地をまわった講演のなかで、自身がこれら銑鉄の運び屋たちと成し遂げたことを、科学的マネジメントの有用性を証明するものとして用いていた[3]」という伝記の一文は、銑鉄運搬実験の意義をあらためて強調するものである。まずはこの実験が、どのようにおこなわれたのかを見てゆくこととしよう。
⒈ 銑鉄運搬実験の概要
1893年にコンサルタントとして独立したテイラーは、6年後の1899年、ベスレヘム・スチール・カンパニー[4]に科学的マネジメントを導入すべく銑鉄運びの調査をおこなった。その経緯を『科学的マネジメントの諸原理』の記述を辿りながら概観してみよう。テイラーはまず「工数の見積もりと算出」を実施した。もともと75人ほどの作業者が従事していたこの仕事について、テイラーは、かれらが1日に運ぶ銑鉄の量をひとりあたり12.5トンと算出した。しかし実際に検証したところ、腕利きの作業者であれば1日に47トンないし48トンを運ぶことが判明したという。
次にかれは、作業にあたる労働者の「科学的人選」に着手する。数日にわたり75人の作業者たちを観察し、まずは1日に47トンを運ぶ体力がありそうな4人に目星をつけた。さらに各人について、過去の実績や性格、生活習慣、モチヴェーションなどを調べあげ、あるひとりに白羽の矢が立った。それがシュミットと呼ばれる人物である。テイラーの筆によれば、シュミットは「並外れてけち」であり「頭の鈍いタイプ」である[5]。しかし「この仕事は本質的にきわめて粗野かつ初歩的なものであるため、知能の高いゴリラを訓練できればどんな人間よりも効率的な銑鉄運びになると強く信じている[6]」というかれの見立てに則れば、シュミットの採用は適切な人事戦略の結果ということになる。テイラーはこのシュミットに、新しく定められた1日あたり47.5トンというタスクを課すにあたって、インセンティブを上げる代わりに朝から晩まで指示されたとおり働くこと、管理者にはいっさい口ごたえをしないことなどを高圧的に言いわたした。そして結果としては、所期の数字を達成したというのが、本実験の顛末である。
⒉ 銑鉄運搬実験の虚構
しかしこの銑鉄運びの実験は、事実というよりもむしろ創作に近い、という指摘もまた、多かれ少なかれすでに共有された見方である。嚆矢となったのは1974年に発表されたレッジおよびペローニの論文「フレデリック W. テイラーによる銑鉄運搬実験の歴史的分析[7]」であるが、かれらの分析は、1899年にベスレヘム・スチール・カンパニーでおこなわれた銑鉄の積み込みに関する報告書の原本に基づいている。1963年より上述の逸話の登場人物であるシュミットの捜索に着手した著者は、かれを見つけ出したのみならず、同社の社員ギレスピーとウォル(James Gillespie and Hartly C. Wolle)によって作成された「ベスレヘム製鉄・サウスベスレヘム工場における銑鉄積み出し作業における出来高制導入についての報告書」を発見したという(以下、ギレスピー=ウォル・レポートと表記)[8]。そしてこの「事実」と、学術的にもっともよく引用される「1911年ヴァージョンの銑鉄物語[9]」を突き合わせるかたちで、8つの論点が議論される。以下では両者のあいだの齟齬が際立つ部分に限って、この論文の内容を見てゆくことにしよう。
まずはそもそもこの実験がおこなわれた背景について、テイラーは①米西戦争直前の1898年には銑鉄価格がひじょうに低く、ベスレヘム製鉄社はその売却で利益を得ることができなかった②ゆえに同社はペンシルヴェニア州にあるサウス・ベスレヘム工場に8万トンの銑鉄在庫を抱えていた③しかし戦争が始まると銑鉄の価格が上昇し、それらの在庫が一掃されたと述べている。けれどもレッジらによると、たしかに米西戦争直前の銑鉄価格が低かったのは事実であるが、その後も価格の低下は続き、実際に上昇の兆しを見せ始めたのは米西戦争終結後の同年の9月くらいからであったという。そしてギレスピー=ウォル・レポートによれば、ベスレヘム製鉄社が余剰銑鉄を売却したのは、テイラーが主張する1898年ではなく1899年の春であり、銑鉄の総量は1万トンだった。だから「テイラーは単純に、積み込む銑鉄の総量を7万トン水増しした[10]」とレッジらは指摘している。
『工場のマネジメント』(Shop Management)では5人から20人程度と言及されていた作業グループの規模は、『科学的マネジメントの諸原理』では75人になっていた。ギレスピー=ウォル・レポートの内容は前者と対応しており、テイラーにおいて数字の誇張があるというのがレッジらの見解である[11]。
銑鉄の積み込み方法については、ギレスピー=ウォル・レポートのなかで当時の一般的なやり方が示されている。それは貨車に立て掛けた厚板の上を通って運搬をおこなうというものであるが、板の高さの調節が難しかったり、板の上を複数の作業員が通ったりすることで効率が悪くなったりもする。そのためギレスピーらは、板の片方を貨車の側壁に引っ掛ける金具を開発したのだが、「これらの金具を使うことによって節約された時間にテイラーはまったく言及しなかった[12]」。この点も、テイラーの記述に根拠が乏しいとされる要因である。
積み込まれる銑鉄の総量に関して、テイラーがはじめに観察した「ひとりあたり1日平均12.5トン」は、「ひとりあたり1日10時間で12.8トン、1トンあたり9セント」というギレスピー=ウォル・レポートの報告と一致する。そしてテイラーが「腕利きの作業者なら1日あたり47トンから48トンを運べるはずだ」と見込んだとき、かれはこの数字を正当化する脚注を添えているが、レポートのデータには触れていない[13]。一方ギレスピーらはかなり詳細な実験内容を記載しつつ、一流の作業員は「最大限のスピードで1時間あたり7.5トン、ということはそのスピードが維持できれば10時間で75トンを積み込める」ことを発見し、ここから「休憩と必然的な遅延として40%を差し引いて、一流の作業者によって積み込まれる量を1日あたり45トンとした」。この数字はテイラーらに伝えられ、かれは1トンあたり0.0375ドルの賃率を決定したという[14]。のちほど言及されるが、こうした計算方法も科学的とは言いがたいものである。
さて、テイラーが「科学的人選」のもとに選び出したシュミットなる人物であるが、かれはたしかに、ヘンリー・ノル(Henry Noll[ベスレヘム・スチール・カンパニーの記録ではKnoll])という名前で実在していた。しかしギレスピー=ウォル・レポートでは、かれが「科学的人選」を受けたことは一言も触れられておらず、ただ10人程度が選ばれて、翌日から1トンあたり0.0375ドルで銑鉄積み込むよう指示されたことだけが記されている[15]。
銑鉄の積み込み方法はたびたびアップデートされ、作業グループの構成も変わっていったが、ノルははじめからずっとそのメンバーであった。ギレスピーとウォルはレポートの最後でかれに賛辞を送っており、レッジらもなぜシュミット役にノルが選ばれたのかが理解できると書いている。そして「かれの尽力に最大限の賛辞を送ったギレスピーとウォルとは異なり、テイラーは、心理学者に委ねるべきなんらかの理由により、侮蔑的な口調でかれに言及するのである[16]」とテイラーを批判する。
こうした点を踏まえて、哲学者であり、自身もコンサルティングファームで勤務した経験を持つマシュー・スチュアートは、テイラーの計算方法のみならず、問題へのアプローチじたいもまったく非科学的だったと主張する[17]。実験の背景や扱う銑鉄の量といった事実上の曖昧さももちろん問題であるが、それ以上に考慮すべきなのは、かれが1日の銑鉄運搬量として設定した47.5トンという基準値であるという。
労働者が一日中こんなペースで銑鉄運搬の仕事の日々を続けることができると想定することは、マラソンランナーのタイムを、100メートル競争の結果を外挿して見積もることと同じくらいばかげたものになることは言うまでもない。労働者には休憩とトイレの時間が必要であることはテイラーもわかっていた。[…]つまり、47.5トンという基準値は、不適切で、管理もされていない実験観測に、ものすごく巨大なごまかしを掛け合わせた結果なのである。[18]
テイラー主義の十八番である「科学的人選」も実際にはおこなわれておらず、そもそも検証可能性がものをいう科学分野において、他人が自分の結果を再現して検証できるようなデータも方法も提供しなかったテイラーは「科学のパロディ」を提供しただけであり、「ストップウォッチや長徐法といった研究に必要な道具を、研究そのものと取り違えていた[19]」。スチュアートは、テイラーの非科学的態度やその物語の虚構性、さらにはテイラー・システムを完全かつ忠実に導入した工場はひとつもなかったという事実などに言及した先行研究[20]に触れたのち、次のようにいう。
科学的マネジメントというテイラーのアイデアには、科学の本性とマネジメントの本性に関する重大な誤解が埋め込まれている。まず、科学的態度と科学それ自体をはっきりと分けることができていない。科学的態度が制御された観察によって仮説を事実に突き合わせる行動傾向を意味する限りで、こうした態度を、あらゆる種類の活動と同じように、マネジメントから発生することがらに対しても適用させることは、完全に可能であるし、大変望ましいことも間違いない。科学的態度でスーパーマーケットに買い物に行くことは可能であろう。しかし、だからといって「スーパーマーケットでの買い物についての科学」が存在することにはならないし、そもそも、科学的態度を適用できるすべての対象について、科学の名に値する知識の体系が存在することにもならないのである。[21]
それでもテイラーは、マネジメントに対して科学的態度をとることを提唱するのみならず、効率性に関する普遍科学を確立させようと試みた。しかしそのような普遍科学は実際には存在せず、というのも「こうした科学が支配する活動の種類が特定されていないので、効率性についての科学を確立させる試みは、効率性の定義をひたすら再確認することしかもたらさない[22]」からだ。だから「科学的マネジメントとは、個々のマネジメント経験から一般法則に至る妥当な一般化ではなく、マネジメントの一部分をマネジメント全体と混同する換喩という壮大な営みであった[23]」。スチュアートはイギリスの哲学者ギルバート・ライルが『心の概念』のなかで提示した「カテゴリー錯誤(category-mistake)」という考え方を援用しながら[24]、「換喩」という修辞によっていわんとするテイラーの推論の誤りを指摘する。そしてマネジメントについての一般科学を確立しようとするテイラーの試みが、「ドグマ」によって機能不全に陥っているとして、以下の例を挙げている[25]。
①効率性というドグマ
本来であれば、マネジメントが追求する目的は多岐にわたる。しかしテイラーのアプローチの根底には、マネジメントはつねに(労働生産性として理解された)効率性というただひとつの目的のみを目指すという考え方がある。
②単一の基準というドグマ
マネジメントについての普遍科学というテイラーのアイデアは、マネジメント活動のすべてがたったひとつの基準によって判定されるというスカラー関数的なモデルに基づいている。しかしこのようなモデルが機能するのは、未来に関する情報のレヴェルと確実性がありえないくらいに高いという極端な状況下においてのみである。
③厳格さというドグマ
テイラーは、銑鉄運搬のマネジメントが正確な計時の問題でしかないという考えに固執したため、文化的要素や心理学的感受性が労働者にもたらす影響をほぼ無視してしまったといってよい。
④機能的社会階級というドグマ
テイラーは、計画することと実行することは異なるという論理的命題と、これらふたつの機能は異なる教育歴や服装、話し方を持つふたつの異なる階級によってもっともよく遂行されるという経験的主張とを混同していた。すなわち前者はあきらかに真であるが、計画するひとと実行するひとを分けたほうがうまくいく、というのは、つねに真であるというわけでもない。
ここでスチュアートは、カントの『純粋理性批判』を引きながら、テイラーの主張における論理的欠陥を取り出している。だからかれが「ドグマ」というとき、そこには「充分な反省と根拠なしに自説を主張する独断的なさま」といった一般的な意味以上のものはないだろう[26]。しかしこの用語は慎重に検討されなければならない。スチュアートは自著を『マネジメント神話』と題し、マネジメント理論の神話的側面を強調しながら、それが「ポピュラー化」ないし「教祖ビジネス化」していくさまを描いている。しかしわれわれは、そこから進んで次のように主張する必要がある。すなわち、マネジメントは神話でなければならない──少なくともその起源においては──と。そして「神話」と密接な関係をもつ「ドグマ」という語も、たんにその否定的な一面でのみ捉えられるのではなく、それが本来有する豊かな意味的次元に立ち戻って考察されるべきである。結論を先取りしてしまえば、マネジメントには「ドグマ」性が不可欠なのであり、むしろそれによって、こんにちに至るマネジメントの系譜が賦活され続けている。このことを論証するために、一本の補助線を引くこととしよう。
⒊ テイラー主義の「ドグマ」
フランスの法制史家であり精神分析家のピエール・ルジャンドルは、中世法制史を出発点とし、精神分析の理論も踏まえながら切り拓いたみずからの研究領野を「ドグマ人類学」と呼んだ。「西洋的規範空間」の解明を掲げ、産業社会に谺する「ドグマ的なもの」を拾いつつ現代のマネジメント主義にも言及するかれのテクストは、本稿において重要な参照項となるはずだ。だがまずは、その研究全体に冠されている「ドグマ」その語について、しばし掘り下げてみたい。はじめに、そのギリシア語源から辿ってみるのがよいだろう。
ドケオーという動詞から派生した名詞ドグマは、わたしの研究の土台ともいえるのだが、ひじょうに複雑で豊かな意味的準拠である。いってしまえば、それはきわめてみごとな意味の場なのだ。この語がわたしたちに連想させるのは、見えるもの、現れるもの、それらしいもの、そう見させるもの──見せかけも含めて──である。夢や幻覚について語るために、あるいは意見、さらには決定や票決を述べるために、この語は用いられるはずだ。時としてその意味は二つの側面から捉えられ、法的なものはしばしばその両面に言及し、またあらゆる権力はそれらを同時に動員する。その両面とはつまり、公理、原理または決議としてのドクサの側面と、名誉、美化、装飾としてのドクサの側面である(ラテン語に取り入れられたdecus, decor, decetなどの語を参照するとよい)。美学を欠いたドグマ学は存在しないのだ[27]。
重層的な意味の次元が圧縮された一節である。「ドグマ」の語源である動詞ドケオーから同じく派生した名詞「ドクサ」にはまず、「公理、原理」という意味があり、これが現代の日本語辞書で「ドグマ」を引いたときにまず目にする「教義、教理」と通じていることは想像に難くない。次に語釈としてあてがわれる「反論する余地のないものとされた宗教的真理」、さらに進んで「独断、独断的な説」といった負の側面は、「ドクサ」が通例として「臆見」と訳されることに照らせば、これまた容易に理解できることである。しかし「ドグマ」と「ドクサ」を並列することによってルジャンドルが強調するのは、むしろその第二の意味、すなわち「名誉、美化、装飾としてのドクサの側面」である。そしてその理由は、なにかを「決定」するものとしてのドグマに与えられた機能と表裏をなしている。
どのような社会においても、ドグマ機能とは〈真理〉を流通させること、学知によって権力を操作し、その権力が語り、真理を告げるように仕向けることである。[…]ドグマ性とは、あたかも権力が実在するかのように、それが口をそなえた一個の身体であるかのように、そしてそのようなフィクションをつうじて、この存在が、それに期待される唯一の効果を生むように仕向けることである。その効果とは、真理を告げるかのようにするということである[28]。
〈真理〉とは別の箇所で、「〈書かれた理性〉(Ratio Scripta)[29]」とも言い換えられる。これはスコラ学以来ローマ法を定義するために用いられてきた表現であるが、〈真理〉の性質を確かめるにあたっては格好の入り口である。まず「理性」とは「理由(raison)」でもあり、理性原理とは突き詰めれば、根拠をめぐる問いかけによって維持されている。しかしこの因果の連鎖は、無限に遡れるわけではない。「なぜ?」を問い続けたあとの最終的な説明因子、すなわち「真理」は「書いてある(c’est écrit)[30]」ことによって保証される。西洋社会についていえば、古代では神話に、キリスト教社会では聖書に世界の起源が「書かれている」。そして世俗化したといわれる社会においても法が、まさしく「書かれた理性」として絶対的な参照項となり、真理を「定礎する(fonder)」のである。ルジャンドルが「書かれたもの」ないし「テクスト」に特権的な意味を見出すのは、まさしくそこに真理が書き込まれているからであって、それらを指して「書いてある」と語ることこそが〈準拠〉の身振りだからである。「真理とはまさにテクストのなかに住まう」のであり、「書かれたものという軛を参照することなしには、産業も、近代の官僚制も、管理経営もマネジメントも考えようがないのだ[31]」。
〈準拠〉という用語もルジャンドルにおける鍵概念であるが、さしあたりそれは、真理を根拠づけるための地点と理解すればよいだろう。概念としては無限に遡及できる因果律の、現実的な最終地点である〈準拠〉は、その性質上論理的な説明を求めることができず、「ドグマ的」に──「説明の情熱を撥ねつけ[…]なによりもまず美的に顕れる[32]」のみである。ここでいう「美的に」とは、ひとつまえの引用に見た「フィクションをつうじて」と重なるが、ほかにルジャンドルが好んで用いる表現にあたれば、「上演(mine en scène)」ないし「劇場化(théâtralisation)」と言い換えることもできるだろう(付言しておけば、この具体的相として、歌や音楽、演劇、詩篇、コレオグラフィーなど、諸芸術の実践が挙げられる)。もはやこれ以上の合理的な説明を求めることができず、ただ審美的に顕現することで真理を通達する──そのような〈準拠〉の機能なくして真理が真理として共有されることは不可能なのであり、こうした定礎的言説を集約的に表現し主体に社会的真理を直観的に把握させるイメージのことを、ルジャンドルは「エンブレム」と呼ぶ。
スチュアートは「科学の条件は反証可能であること」というカール・ポパーのテーゼを引きながら、効率性の定義をひたすら確認するというテイラーの理論が「あまりにも真」であるがゆえに、かえって自身の擬似科学性を露呈させたと主張する[33]。テイラー主義は反証可能性を寄せつけない、まさにその「あまりにも真」であるというステータスによって、みずからを至高のテクストたらしめることに成功した。それはひとつの〈準拠〉として〈真理〉を通達するというドグマ機能を、すでに充分に果たしている。
ただしこの事実以上に注目すべきなのが、テイラー主義におけるドグマ機能のもうひとつの側面、すなわち美学的=感性的な次元である。
おそらく、銑鉄物語のもっともおぞましい側面とは、テイラーが何年にもわたってそれを何度も繰り返し語ったという事実だ。物語を一度盛るだけでもちょっとした違反とみなされるだろう。しかし、事実にこだわり続けたことで歴史上もっとも悪名高い一人という世間が持っているイメージを洗練させつつ、何度も嬉しそうに嘘をつき、自分のキャリアをその嘘の上で築くためにはキャラクターが必要だ。テイラーが制御マニアだったことは簡単にわかる。しかし、テイラーの性格が持つより重要な側面とは彼の演劇性だろう。つまり、ものまねの才能、よい物語の情熱、そして、最後のシーンで鳩を飛ばして空を横切らせるという細かい演技に対する狂信的なこだわりである。偉大な俳優のように、テイラーは自分の物語の中に住み、たまたま売ることになった物語であればどんな物語でも、その真実を目でわかるものにするという途方もない能力を持っていたのだ。このように、一見すると誠実そうに自分の確信を表すことで、テイラーは自分の顧客にいとも簡単に確信を呼び起こしたのだ。要するに彼は、ペテン師であった。[34]
ここには「真理の劇場化」に必要な要素がふんだんに盛り込まれている。みずからが主人公となるようキャラクターを作りあげ、細やかな演出をあてがい、銑鉄物語を〈真理〉として繰り返し上演する──この複数性も重要な点である。なぜなら「言語への信は反復の儀礼によって獲得される[35]」からだ。
かくして銑鉄物語はテイラー主義を「定礎する神話」となり、そのドグマ機能を十全に発揮する。テイラー主義はひとつの「ドグマ」となり、効率性ないし合理性を共通の信とする制度的な建造物が建ち上がる。あらためて確認しておかなければならないのは、マネジメントに関する諸技術を適用し、合理的な身振りをとるためには、合理性の信仰が前提として必要なのであり、その信託は、まったくもって非合理的になされるほかないということだ。
「定礎」され、そして「上演」された真理に対してわたしたちが切り結ぶ関係性を、ルジャンドルは「粘着」と呼ぶ。「わたしたちが真理を語る〈テクスト〉の生きた症候であることをいうために、糊づけの思考や粘着性の思考、エンブレム的思考などの、ほかの表現を用いていたこともあった[36]」。粘着とはすなわち、誰かに、誰かの思想に、〈真理〉とされるものに文字どおり「貼りつく(adhérer)」ことである。科学的マネジメントの成立は、テイラーの思想に糊づけされることを必要とする──「テイラーはルターと比べられることもあったし、彼を「救世主」と呼ぶ者もいた。「この運動において、テイラーは全能の神だ」と言う者さえいた。墓碑銘に記されているように、テイラーが「科学的マネジメントの父」であることに誰もが同意しているのだ[37]」。ルジャンドルは別のテクストで、こうした「粘着性の思考」にかんする諸技術がマネジメントにおいても不可欠だと指摘している。
産業社会におけるマネジメント(gestion)はこうした技術を体系的に利用しており、この技術は神話の信仰や典礼の奇蹟、権威がもつ宗教的な原理の利用を必要としている。マネジメント的理性はみずからがそうした土台の上に築かれていることを知らないが、無意識を歩ませる野蛮なくしてそのような理性はありえないのである[38]。
*
文明ないし文化(culture)は、語源を辿ればラテン語の動詞colere(耕す、崇拝する、配慮する)、およびそこから派生した名詞cultus(崇拝)とつながっている。ルジャンドルは『グラティアヌス教令集』に収められたある法文を引用し、文化とは他者たち、すなわち非キリスト教徒たちの野蛮のことだと強調する[39]。そして「抑圧されてきたこの意味、つまり羞恥に結びつけられた意味をこんにち復権させることで、[…]困難を極める諸問題の研究に有害なある種の人種差別的思い込みを取り除く[40]」と述べているのだが、それはつまり、儀礼やダンスなどプリミティヴなドグマ機能のモードを持つ社会を「野蛮」というのなら、現代の産業社会も同様の機構に基づいて作動しているという点で同じだけ「野蛮」であるということに、わたしたちの目を啓かせるためである。「産業システムは文化=崇拝(culture)を動かし構築する。それはこの語のもっとも強い意味において野蛮そのものなのであり[…]宗教的で野蛮な方法にしたがうのだ[41]」。
だからテイラーが発明したのはひとつの宗教だというとき[42]、このことは皮肉としてではなく、真摯に受けとめられなければならない。それは繰り返しになるが、〈マネジメント〉という名前で示されるものがひとつの制度的構造体だからであり、なんらかの〈真理〉を製造して上演を施し、そこに人々を粘着させることなくしては機能しないからである。そしてこの見方に立つとき、一般的なマネジメント研究がこれまで黙殺してきた身体的・情動的次元が拓かれ、そこを貫く新たなマネジメントの系譜が陰画として浮き彫りになるはずだ。この身体はまず、科学的マネジメントという「エンブレム」に魅了されるテイラーの信奉者たちのものとして現れる。それはやがて、テイラー・システムのもと工場で一定のリズムを繰り返す労働者の肉体のうちに、変奏されたイメージとして、あるいは「エンブレムのエンブレム」として見出されるだろう[43]。
ダンスにまつわる古代の教訓(morale)のうえに、踊り手ではない人々にとっても、産業的服従の一部が構築されている。たとえば、工場奴隷は姿勢と動作が法にかなっていることから利益を得たのだ[44]。
ここでルジャンドルが「ダンス」と呼ぶものは、上でも触れたように、制度のドグマ機能の半面をなす審美的次元における、ひとつの社会的実践としてみなされなければならない。「ダンスによって主体の身体に〈法〉が響きわたるのであり、それがこのテクスチュアリティの外に書き込まれることはありえない[45]」といわれるように、ダンスを含めた美的なエクリチュールは、〈法〉に端を発するひとつの「規範」に身丈を合わせる──なにが「よい」ダンスでなにが「悪い」ダンスかという「教訓」があり、それに適う身振りを模倣することがおのおのの主体に要請される──ための手段として機能する。そして「諸身体はシステムのエンブレムとなり、そこにおいて信仰が組み立てられる[46]」のだ。
「過去においては人間が第一であった。未来においてはシステムが第一とならねばならない[47]」──テイラー主義が効率性の旗印のもと推し進めた労働の非人間化は、ヘンリー・フォードが開発した組み立てラインを持つ工場での大量生産(いわゆる「フォード方式」)のかたちをとって具現化した。そこで働く労働者の身体は、一方ではマネージャーの指示に従い、一定のリズムで動くことを強制され、文字どおり賃金としての利益を得る。他方でそれは、一種のダンスとして〈マネジメント〉という真理を再演し、そのドグマ性を賦活することで、そのような制度的建造物の強度を高めているという点も見逃してはならない。
本来であればある逸話の思想史的意義について、系譜的連関を問わずしてそれを論ずることに意味などなく、したがって本稿は、議論がはじめられる地点を指し示して閉じられる。そしてこのとき、銑鉄物語は〈マネジメント〉の、いわば創始の言説として響くのであった。
【参考文献表】
Copley, Frank B., Frederick W. Taylor: Father of Scientific Management, v. II, New York, Harper & Brothers, 1923.
Kanigel, Robert, The one best way: Frederick Winslow Taylor and the enigma of efficiency, New York, Viking, 1997.
Legendre, Pierre, L’Amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Seuil, 1974 (nouvelle édition, 2005).
–––––, La Passion d’être un autre. Étude pour la dance, Paris, Seuil, 1978 (nouvelle édition, « Points », 2000).
–––––, Leçon I. La 901e conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, Fayard, 1998.
–––––, Leçon II. L’Empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels,
Paris, Fayard, 1983 (nouvelle édition, 2001)[『真理の帝国』西谷修・橋本一径訳、人文書院、2006年].
–––––, Paroles poétiques échappées du texte. Leçon sur la communication industrielle, Paris, Seuil, 1982.
Nelson, Daniel ed, A mental revolution: Scientific Management since Taylor, Columbus, Ohio State University Press, 1992[『科学的管理の展開 テイラーの精神革命論』アメリカ労務管理史研究会訳、税務経理協会、1994年].
Taylor, Frederick W., Shop Management, Scientific Management, New York, Harper & Brothers, 1947.
–––––, Testimony Before the Special House Committee, Scientific Management, op. cit.
–––––, The Principles of Scientific Management, Scientific Management, op. cit.
Wrege, Charles D. and Perroni, Amedeo G., « Taylor’s Pig-Tale: A Historical Analysis of Frederick W. Taylor’s Pig-Iron Experiments », The Academy of Management Journal, vol. 17, no.1, 1974.
Wren, Daniel A., The History of Management Thought, 5th edition, New York, Wiley, 2005.
カント、イマヌエル『純粋理性批判』熊野純彦訳、作品社、2012年。
ヴェイユ、シモーヌ『工場日記』冨原眞弓訳、みすず書房、2019年。
スチュアート、マシュー『マネジメント神話 現代ビジネス哲学の真実に迫る』稲岡大志訳、明石書店、2024年。
トゥーリッシュ、デニス『経営学の危機 詐術・欺瞞・無意味な研究』佐藤郁哉訳、2022年、白桃書房。
ライル、ギルバート『心の概念』坂本百大ほか訳、みすず書房、1987年。
Notes
-
[1]
Frederick W. Taylor, Shop Management, Scientific Management, New York, Harper & Brothers, 1947, p. 18.
-
[2]
「わたくしはいつも、銑鉄運搬工の説明から話し始めています。なぜなのか正確にはわかりませんが、どういうわけかこの例がとてもよく話題になり、じつのところ、科学的マネジメントの全貌はこの銑鉄運搬のなかにあると思っているようなひともいます。しかしながらわたくしがいつもこの例を挙げる理由はただひとつで、それは銑鉄運搬が、人間がおこなう労働のうちでもっとも単純なものであるからです」。Frederick W. Taylor, Testimony Before the Special House Committee, Scientific Management, op. cit., p. 48.
-
[3]
Frank B. Copley, Frederick W. Taylor: Father of Scientific Management, v. II, New York, Harper & Brothers, 1923, p. 38.
-
[4]
もともとベスレヘム・アイアン・カンパニー(Bethlehem Iron Co.)という名称だった同社は、1899年にベスレヘム・スチール・カンパニー(Bethlehem Steel Co.)へと社名を変更した。会社の詳細については以下を参照。Ibid., p. 3-14. 本稿ではベスレヘム・スチール・カンパニーと表記を統一して記載する。
-
[5]
Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management, Scientific Management, op. cit., p. 44-46.
-
[6]
Ibid., p. 40.
-
[7]
Charles D. Wrege, Amedeo G. Perroni, « Taylor’s Pig-Tale: A Historical Analysis of Frederick W. Taylor’s Pig-Iron Experiments », The Academy of Management Journal, vol. 17, no.1, 1974, p. 6-27.
-
[8]
Ibid., p. 8. 背景を補足しておくと、1899年3月、ベスレヘム・スチール・カンパニーの副社長R. ダヴェンポート(Robert W. Davenport)とテイラーは、銑鉄の積み込み作業を日給制から出来高制へ切りかえるために、ギレスピーとウォルの両名に実験と観察を指示した。この内容をまとめたのがギレスピー=ウォル・レポートである。
-
[9]
レッジ=ペローニの論文によれば、テイラーが語った銑鉄運搬実験には1903年、1907年、1911年の3つのヴァージョンがあり、それぞれのあいだで段階的な変化の徴が見られるという。1903-1911年にかけて、テイラーはフィラデルフィアの自宅ボックスリーでの講演でこの実験を幾度となく取りあげ、1907年に録音された講演をベースとするメモが、『科学的マネジメントの諸原理』に盛り込まれている。以下を参照。Ibid., p. 8-11.
-
[10]
Ibid., p. 12.
-
[11]
Ibid., p. 13.
-
[12]
Ibid., p. 13.
-
[13]
Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management, Scientific Management, op. cit., p. 60.
-
[14]
Charles D. Wrege, Amedeo G. Perroni, « Taylor’s Pig-Tale: A Historical Analysis of Frederick W. Taylor’s Pig-Iron Experiments », art. cit., p. 14.
-
[15]
Ibid., p. 15-16.
-
[16]
Ibid., p. 17.
-
[17]
ところで、なぜ急にこのような文献が参照されるのかと思われる向きもあるかもしれない。マネジメント研究の潮流を概観しておくと、1980年代後半からヨーロッパやオーストラリアにおいて、「批判的経営研究(Critical Management Studies)という手法が採られはじめる。これはアメリカを中心としたメイン・ストリームをなす経営学に対し、理論的、思想的、あるいは方法論的な展開をもたらそうとするものであった。しかしこの批判的経営研究は、往々にして借り物の哲学用語を弄ぶだけで、本質的な研究になっていないという指摘もある。上記のような一連の(批判の批判も含めた)経営学批判の文脈に、スチュアートの著作も並べることができるだろう。以下の訳者解説を参照。デニス・トゥーリッシュ『経営学の危機 詐術・欺瞞・無意味な研究』佐藤郁哉訳、白桃書房、2022年、394-395頁。
-
[18]
マシュー・スチュアート『マネジメント神話 現代ビジネス哲学の真実に迫る』稲岡大志訳、明石書店、2024年、76頁。
-
[19]
同上、76頁。
-
[20]
代表的なものをいくつか挙げておく。Robert Kanigel, The one best way: Frederick Winslow Taylor and the enigma of efficiency, New York, Viking, 1997. Daniel A. Wren, The History of Management Thought, 5th edition, New York, Wiley, 2005. Daniel Nelson ed, A mental revolution: Scientific Management since Taylor, Columbus, Ohio State University Press, 1992(『科学的管理の展開 テイラーの精神革命論』アメリカ労務管理史研究会訳、税務経理協会、1994年).
-
[21]
マシュー・スチュアート『マネジメント神話』前掲書、82頁。強調は原文による。
-
[22]
同上、83頁。
-
[23]
同上、84頁。
-
[24]
「カテゴリー錯誤」とは、ライルがデカルト的心身二元論を批判するために提示した概念で、端的にいえばカテゴリー間の相互関係を見誤ったときに生じる錯誤である。たとえばある大学を訪れたひとが、図書館や運動場、学部棟などを見学したあとに「ところで大学はどこにあるのか」と尋ねたとしたら、そのひとは個々の構成要素である各施設と、その上位概念である「大学」とを並列に置いてしまっている。こうした錯誤は「われわれの言語の語彙の中のある種のものを適切に使いこなすことができなかったということから生じるものである」。以下を参照。ギルバート・ライル『心の概念』坂本百大ほか訳、みすず書房、1987年、p. 11-15頁。
-
[25]
マシュー・スチュアート『マネジメント神話』前掲書、85-87頁。
-
[26]
『純粋理性批判』第二版序文では、独断論(dogmatismus)とは「じぶんに固有な能力を先立って批判することのない、純粋理性の理説的な手つづきのとりかたである」とされる(イマヌエル・カント『純粋理性批判』熊野純彦訳、作品社、2012年、27頁)。さらにコンテクストを踏まえれば、ここでスチュアートがいう「ドグマ」に響いているのは、デカルト的心身二元論が心の本性とその位置付けに関する「公式教義(the official doctrine)」となっていると指摘し、それを「機械の中の幽霊のドグマ(the dogma of the Ghost in the Machine)」と形容したライルの語法(『心の概念』前掲書、5-11頁)である。
-
[27]
Pierre Legendre, Leçon II. L’Empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels [1983], nouvelle édition, Paris, Fayard, 2001, p. 36-37(『真理の帝国』西谷修・橋本一径訳、人文書院、2006年、56-57頁).
-
[28]
Ibid., p. 23(邦訳40頁).
-
[29]
Ibid., p. 158(邦訳208頁). 強調は原文による。
-
[30]
Ibid., p. 58(邦訳85頁). 強調は原文による。
-
[31]
Ibid., p. 28(邦訳46頁).
-
[32]
Ibid., p. 61(邦訳88頁).
-
[33]
マシュー・スチュアート『マネジメント神話』前掲書、83頁。
-
[34]
同上、92-93頁。
-
[35]
Pierre Legendre, Leçon I. La 901e conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, Fayard, 1998, p. 26. 強調は原文による。
-
[36]
Ibid., p. 29(邦訳47頁)
-
[37]
マシュー・スチュアート『マネジメント神話』前掲書、60頁。
-
[38]
Pierre, Legendre, Paroles poétiques échappées du texte. Leçon sur la communication industrielle, Paris, Seuil, 1982, p. 19. なおgestionはラテン語の動詞gerareに由来し、英語のmanagementに対応するフランス語である。
-
[39]
Pierre Legendre, L’Empire de la vérité, op. cit, p. 26(邦訳44頁). ただしこの表現には、ルジャンドルによるかなり強い解釈が込められていることに注意すべきである。ここで詳述することはできないが、かれは別のテクストのなかで、くだんの法文(『グラティアヌス教令集』事例26、設問2、第9法文)をみずから以下のように訳している。「文化(culture)とは、予兆を観察したり、星の動きを調べたりすることである。そのことは聖ヒエロニムス[現在ではオリゲネスとされている]が述べている:さらに以下のことにも注意すること。姦淫をおこなう者はみずからの身体において、それは神の社となった自身の固有の身体においてのみならず、われわれが教会と呼ぶもうひとつの身体、すなわちキリストの身体においても罪を犯している。[…]これこそまさにエジプトの恥である。[…]予兆を観察したり、未来を探るために星の動きを調べたりして、ついにはこのたぐいのあらゆる迷信に身を絡め取られてしまう。なぜならエジプトは偶像崇拝の母だからである」。ここでは性的放埒と偶像崇拝が同一のレヴェルで論じられているが、このことをふまえてルジャンドルは「異教徒についての学知である文化は、男根的な罪に関連するこうしたあらゆる実践をまとめあげている」と指摘する。すなわち当該法文において「文化」は、キリスト教の信仰から見ると非難の対象となる、異教徒のさまざまな慣習とひとまずは理解できる。以下を参照。Pierre Legendre, L’Amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique [1978], nouvelle édition, Paris, Seuil, 2005, p. 263-264. 強調は原文による。
-
[40]
Pierre Legendre, L’Empire de la vérité, op. cit, p. 26(邦訳44頁).
-
[41]
Pierre, Legendre, Paroles poétiques échappées du text, op. cit., p. 229.
-
[42]
マシュー・スチュアート『マネジメント神話』前掲書、123頁。
-
[43]
たとえばシモーヌ・ヴェイユは『工場日記』のなかで、自分たちは機械のように扱われているのだというひとりの女工のことばを、テイラーの名前に言及しながら記している。そして機械が労働者に押しつけるものを「一様のリズム=達成率(rythme ininterrompu)」と呼んでいる。以下を参照。シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』冨原眞弓訳、みすず書房、2019年、171頁、178頁。
-
[44]
Pierre Legendre, La Passion d’être un autre. Étude pour la dance [1978], nouvelle édition, Paris, Seuil, « Points », 2000, p. 76. 強調は原文による。
-
[45]
Ibid., p. 58.
-
[46]
Ibid., p. 68. 強調は原文による。
-
[47]
Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management, Scientific Management, op. cit., p. 7. ここでテイラーが、明らかに心身二元論的な考え方を持っていたことは強調しておいてよい。実際に銑鉄を運ぶのに適した人材は、逆に銑鉄運びの科学を理解することができず、もっと教養のある人物がそれを担うべきだとされる。一方で、実際に作業にあたるのは「多少知能のあるゴリラ」でよいわけで、つまり労働者は精神を持たない身体であり、管理者は身体を持たない精神とみなされる。なお、テイラー主義化した工場で課される非人間的な労働を、チャップリンが『モダン・タイムズ』で風刺したことはよく知られている。
この記事を引用する
大岩可南「創始の言説──テイラー主義とそのドグマ性について」『Phantastopia』第4号、2025年、20-35ページ、URL : https://phantastopia.com/4/the-inaugural-discourse/。(2026年02月12日閲覧)