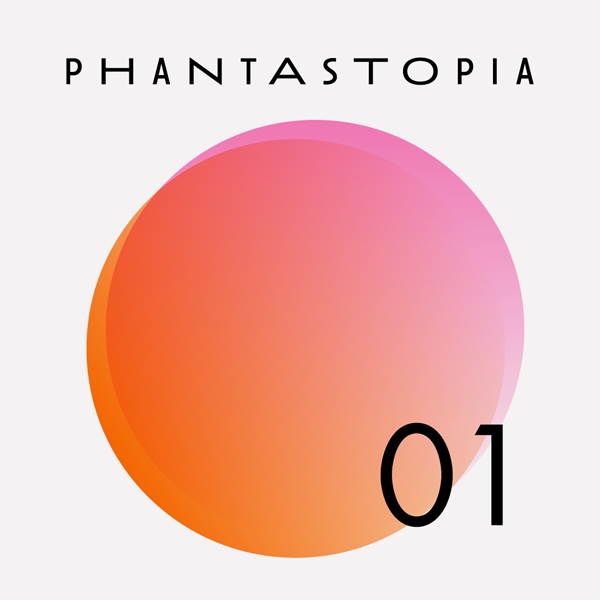吉田喜重監督作品『BIG-1物語 王貞治』(1977年)は、当時読売巨人軍の野球選手だった王貞治が、1977年9月3日にメジャーリーグの記録を抜く756号の本塁打を達成したことを記念して作られたドキュメンタリー映画である。吉田が構成・監督を担当し、製作は読売映画社/東京読売巨人軍、配給は東映、編集は浦岡敬一[1]、音楽は一柳慧および読売日本交響楽団が担当している。1977年12月1日に全国公開され、本作は文部省選定、映倫青少年映画審議会推薦、優秀映画鑑賞会推選の作品となっている。
1973年に『戒厳令』を公開した吉田は、1986年に『人間の約束』を発表するまでの13年間、一度も長篇劇映画を完成させていない。1974年には大江健三郎の小説『万延元年のフットボール』の映画化企画[2]を、そして1978年から1982年の間にはメキシコへ旅立ち、『侍・イン・メキシコ』の映画企画を構想、シナリオまで書き残していたものの、完成することはなかった。とはいえ、彼は映画監督の仕事を放棄したわけではない。1974年から1977年の間にはテレビ・ドキュメンタリー番組『美の美』シリーズで90本以上の番組を製作し、本作において『人間の約束』に先駆けて商業的な映画まで完成させてしまっている。彼はアルチュール・ランボーのように、創作に決別を告げたわけでは決してない。
本作はドキュメンタリー映画ではあるものの、タイトルが示唆する通り、限りなくフィクションに近い。そこには王貞治に関する「ドラマ」が物語られているからだ。BIG-1「物語」。しかし、いかに「物語」を仮構したらよいのか。吉田には「ストーリー主義批判」というテクストがある。「近代的自我の喪失」以後を生きる20世紀において、19世紀の「近代文学」に見られた「物語る私」は自明ではなくなった。素朴に「物語」を語ることで、作者と読者、映画製作者と観客を安易に結び合わせることは、彼にとって状況に対する主体的な関わりの放棄を意味する。吉田がそこで戦略として選ぶのが、「物語」を単に拒絶するのではなく、それを「バネ」として利用することで、「ストーリー主義」を内側から崩すことだという[3]。では、どうやって?
吉田喜重には、評伝作家的な側面がある。ルドルフ・ヘスを描いた小説『贖罪』(2020年)。小津安二郎を論じた著書『小津安二郎の反映画』(1998年)、およびドキュメンタリー『吉田喜重が語る小津さんの映画』(1994年)。ガブリエル・ヴェールを論じた記録映像『夢のシネマ 東京の夢』(1995年)、および彼をモデルとして失敗した映画企画「薔薇のリュミエール」(1992年)。狂言師・三宅藤九郞を扱った記録映像『狂言師 三宅藤九郞』(1985年)。中岡慎太郎を描いた記録映像『幕末に生きる 中岡慎太郎』(1987年)。安倍晴明を扱った現代能『陰陽師 安倍晴明』(2001年)。北一輝を描いた映画『戒厳令』。大杉栄と伊藤野枝の倒錯的な評伝映画『エロス+虐殺』(1969年)。『美の美』シリーズで取り上げられる多くの美術作家たち。そして、王貞治を描いた本作。
本作公開時に販売されたパンフレットには、吉田本人によるテクストが寄せられている。そこでは次のように書かれてある──
王選手の背番号「1」ほど、象徴的なものもない。
バッターボックスに向う王選手の後姿、その背番号「1」を眼にしただけで、私たちは王選手の表情を想像することができる。これから起るであろうドラマを思い浮かべてしまう。[4]
王貞治の背中に書かれた「1」から、我々は容易に彼の「表情」、「ドラマ」、言い換えれば「物語」が浮かんできてしまう。しかし、それは吉田にとって、「ストーリー主義」への危険極まりない誘惑だったのではないか。
そこで彼は、ある口実をつくる。このテクストのタイトル「見てはならない 幻のあの一球」が示す通り、吉田にとって、王貞治の756号ホームランの球は、「幻のホームラン」であり、「幻のように存在しなかった」、と。バットとボールがぶつかり合う瞬間は1/1000秒だとされ、それは1/24秒で切り取られる映画のフィルムでは捉えることができない。その瞬間は、我々の肉眼でははっきり見えるものの、フィルムのひとこまになれば消えてしまう。驚くべきことに、彼は王貞治のホームラン・ボールに、表象不可能性を見てとるのだ──
私は冗談を云っているのではない。王選手だけが知っているこれまでの彼自身の歴史を思い合わせれば、誰があの一球を見る権利があると云うのだろうか。王選手にはかぎらない。背後にあって支えた人々、両親や奥さんたち、その人々のためにも、あのホームランは容易に見てはならない、幻のホームランだったのだと思う。[5]
こうして吉田は、苦しまぎれの口実をでっち上げつつ、「BIG-1物語」を作り上げる。
本作はほとんど封印されたに等しい作品である。吉田喜重全集DVD-BOXには収録されておらず、いかなるソフト化もされず、彼の回顧上映でもほとんど上映されることがない[6]。筆者は、国立映画アーカイブの特別映写室を利用し、当館に保管されていたこの「幻」のフィルムを目撃することに成功した。
本作において際立って特徴的な場面が、吉田本人による王貞治やその関係者へのインタビュー・シーンである。彼は、『美の美』で散見されるショットのように、フレームの中にその背中を映し込ませる。彼の長い髪の毛、肩飾りのついた黒いシャツ、細い体躯、訛りのある声。顔がはっきりと映し出されることはないが、まぎれもなく吉田である。彼が生身の人間を相手に、マイクを向けてインタビューをする映像は、管見の限り本作以外で確認したことはない。彼は生身の人間とも会話のできる映画監督であったのだ。
もっとも、その顔は、入念にフレームの外部へと追いやられる。単なるインタビューであるにもかかわらず、カメラアングルは、『告白的女優論』や『戒厳令』、『美の美』を思わせるポジションで撮影され、彼の顔は小道具や銅像、建物の柱などによって覆い隠される。無頭人(アセファル)の彼は、しかし、それゆえに彼の作家性を逆説的にもフィルムに強く刻印することになる[7]。
インタビュー中、決してカメラはインタビュアーの方へと切り返されない。そのかわり、インタビュイーの顔を、右から、左から、あるいは斜めから、さまざまな角度で捉える。野球の試合は8台のカメラで同時に撮影されていたとのことなので、インタビュー中も複数のカメラがインタビュイーたちの顔を捉えていたのだと思われる。そんな不自然な撮影環境にもかかわらず、インタビュイーたちはすらすらと質問に答える。まるで『告白的女優論』ラストでの女優たちのインタビューのように。
吉田は王貞治の両親と会話をする。貞治の父・仕福は、現在の中国浙江省で生まれ、1922年に日本に渡る。富山県出身の母・登美と結婚。貞治は5人兄弟の末っ子である。両親は1923年9月1日の関東大震災を経験し、1945年3月の東京大空襲では、当時4歳だった貞治もそれを経験している。吉田は、中国国籍としての王の出自や生い立ちを殊更に強調して質問を投げかける。スクリーンからは、関東大震災や東京大空襲の記録映像が流れ出す。現・墨田区で育った貞治には、幼少期の原光景として東京の下町の風景が広がっているはずだという確信のもと、カメラは貞治もまた見たであろう下町の工場や隅田川の風景を捉え、そこにインタビューのオフの声が挿入される。吉田は世界記録を持つ野球選手としての王貞治に、人間としてのアイデンティティを与えなおそうとするのである。「物語」を仮構するために。
はたして、その試みは成功したであろうか。王貞治は、吉田が仮構して投げかける中国国籍としての彼のイメージ、下町育ちとしての彼のイメージを、するりとかわしていく。「スポーツしているときは関係ないですからね」。王は、756号ホームランを打ったときですら、「わりかし冷静でしたね」と語る。「物語」を駆動させるための「出来事(événement)」を期待する吉田、および製作者、メディア、聴衆たちを拍子抜けにさせる彼の応答。吉田はそこからいかに「物語」をつくればよいのか。
不思議なことに、吉田は王に756号ホームランを打たせてしまった投手・ヤクルトスワローズの鈴木康二朗にも取材を行う。茨城県北茨城市出身である彼の故郷へ赴き、なぜか茨城の浜辺で、打ち捨てられた廃船を背に吉田と鈴木は2人スクリーンに映し出される。言うまでもなく、廃船は『女のみづうみ』に映し出される特権的なモチーフであった。ホームランを打たれてどう思ったかと訊く彼の恩師からの、かくも残酷な質問に対し、鈴木投手は答えにくそうに、「光栄でした」と返す。
なぜ本作において、わざわざ廃船のある茨城の浜辺を選んでまで、敵対する選手にも律儀に取材が行われるのか。それは、この「物語」を、決闘(duel)の物語にするためである。決闘とは、二者によって闘われる。そこに、第3者の介入はない。そして野球ほど、決闘のイメージが容易に喚起されるスポーツもなかっただろう。鈴木投手が浜辺でインタビューを受けるのは、したがって、巌流島の浜辺で宮本武蔵を待つ佐々木小次郎と同等の身分を与えるために違いあるまい。
本作では、王貞治の「一本足打法」の誕生秘話が語られる。とある和室で、「一本足打法」の指導をする王の師匠と、彼のサポートを受けながら素振りをする王の姿が映し出される。彼の師匠は言う。「一本足打法というのは、武道であり、一種の剣術、居合である」。すなわち、王は師匠から、決闘の作法を教わっていたのである。
映画史において、これまで多くの決闘が描かれてきた。「古典的ハリウッド映画」における西部劇は言うまでもなく、さらに遡れば、ガブリエル・ヴェールがメキシコで撮影したリュミエール映画社の作品『ピストルによる決闘(長さ12m)』(1896年)にも決闘は登場する[8](図1)。にもかかわらず、映画にとって決闘は相性が悪い。決闘が行われるためには、2人は相対する必要があり、カメラは両者の顔を同時に捉えることができない。決闘者の背後に鏡を置くか、ショット/切り返しショットの編集を施すか、カメラをパンするか、大胆に空間を歪めて、非ユークリッド幾何学上で決闘を行わない限り、適切な距離のもと両者の表情をカメラが同時に捉えることはできない。

(図1)『ピストルによる決闘(長さ12m)』(ガブリエル・ヴェール撮影、1896年)
野球場のマウンドとバッターボックスとの間に隔てられた18.44メートルは、一台のカメラでピッチャーとバッターの顔のクロースアップを同時に捉えることを不可能にさせる。ゆえに、真に表象不可能なのは、「幻のホームラン」などではなく、相対する決闘者2人の顔を同時に捉えることだと言ってよい。
バッターボックスに立つ王貞治を、本作のカメラはしばしば一塁側から捉える。それは、王の両親が普段座っている観覧席からの視線に等しい。左打者である王は、したがって、一塁側に背を向けている。彼の顔の表情は見えず、背中に書かれた数字の「1」のみが、彼を王であるとしるしづけている。「王選手の後姿、その背番号「1」を眼にしただけで、私たちは王選手の表情を想像することができる」と吉田は語るが、それはあくまでも「想像」されたものでしかない。
野球場という表面において、人は、純粋な数字となる。そこに国籍やアイデンティティが入り込む余地はなく、人間は非人称化される。本作ラスト近くでナレーターは、王の身体の測定値を並び立てる。身長177cm、体重79kg、上腕の長さ、前腕の長さ、手の長さ、視力、動体視力、etc……。そこで肉体は、純粋に数値化される。
医師である彼の兄へのインタビューシーン。彼の背後にはなぜか誰かの身体のX線写真が貼られてある。写真からは皮膚や血管、脂肪、肉塊が削ぎ落とされ、その奥に見出された骨の表面が写し出されている。この映画において、肉体は、異なる表面の次元において再発見されるのである。
映画のラスト、鏡の前で素振りの反復練習をする王貞治。野球場において捉えられなかった彼の顔のクロースアップを、ここでカメラは思う存分捉える。しかし、そのことによって、今度は鏡の中にいるもう1人の王貞治の顔を捉え損ねてしまう。王はそこで、鏡の奥にいる不可視の投手が放つ不可視の球を幻視しているというのに。
本作において、非人称化された主体は他にもいた。王の自宅から後楽園球場へと向かう途中にあるとされる国鉄列車の空調機を製造する工場の工員たちである。彼らにも吉田はインタビューを試みる。休憩中、仕事中を問わず、彼は工員たちに質問をする。「野球好きですか?」「ええ、巨人ファンです」。名前を持たない彼らは、野球場における純粋に数値化された選手たちと同じ地位にいる。
かつて吉田は、『嵐を呼ぶ十八人』(1963年)において、匿名化された若い労働者の集団を描いていた。ストによって労働から解放された彼らもまた、野球をはじめとするスポーツに興じていた。また、主人公は、恋人を探しに広島球場へと向かうが、そこではプロ野球の試合も行われていた。二つの作品は、フィルムに表面を導入する遊戯の規則としてのスポーツを主題にしている点で、兄弟関係にあるといえる。
蓮實重彥は吉田のフィルモグラフィを貫くスポーツの主題を早くから見抜き[9]、マチュー・カペルはそこに映し出されるスポーツの競技場に「純粋な表面」なるものを指摘している[10]。そして「表面」こそは、吉田の大学時代の友人であった宮川淳が、ジル・ドゥルーズの『意味の論理学』に触発されつつ思考の対象に選んだ特権的な主題であった。吉田は当時、宮川の著作もドゥルーズの著作もほとんど読んでいなかったとされるが、スポーツの美的要素を論じた中井正一[11]をおそらく経由しつつ、独自の回路で表面を発見するに至るのである。
しかし、宮川淳の文脈において「表面」では二項対立が成立しない。精神と肉体、意識と物質、主体と客体といった形而上学的、ないし存在論的テーマは、「表面」においてするりと「滑り落ちる」[12]。「表面」の背後に超越的なシニフィエを規定することはできず、「表面」の背後にあるのは無、あるいはもう一つ別の「表面」でしかない。そこに深さはなく、軽薄なまでに表面的な「表面」が同語反復的に広がっているとされる。
吉田の場合も同様である。一つのショット、一つの表面において、決闘する二者の顔は同時に捉えられない。カメラに背を向けている者の顔は、スクリーンの背後の無に向けられている。彼/彼女の顔は無である。したがって、カメラの方に顔を向けている者がこれから闘おうとする相手は、無の顔をしている。彼/彼女は無と闘おうとしているのである。
本作を撮影し、編集、公開するまでのあいだ、吉田もまた、もう一つ別の無と対面していたといえる。病床に臥していた宮川淳である。1977年6月、病で倒れた彼は手術のため入院する。1977年7月、吉田は、かつて大学時代に石川淳論を書いた宮川への返歌として、『エピステーメー』誌に「空間のエロティシズム」というタイトルの石川論を発表する[13]。若き宮川が「精神」の観点から石川を論じたのに対し、吉田は「肉体」の観点から論じたのだという。彼がこれを書いた時、その背後に彼が託していたメッセージとは、「彼に生きてもらいたい、人間はそう簡単に死ねるものではない」[14]という思いにほかならなかった。宮川が「鏡」という「表面」の底へ完全に落ち切るその手前で、吉田はあえて「肉体」という言葉を唱える。そうすることで、彼を「表面」という「底なしの深さのなさ」[15]から救い出そうとしたのであった。
1977年10月21日午後1時2分、宮川はこの世を去る。吉田はその前日、本作のクランク・アップを迎えている。
吉田は宮川と異なり、「肉体」という言葉を好む。しかし、それは、表面の発見を経た後に再定義された肉体であり、数値化され、非人称化された肉体、新たにでっち上げられ、再創造(réinventer)された肉体、鏡の底から浮き出た肉体、X線から「幻のあの一球」までをも含めたあらゆる電磁波/素粒子でさえ透視することを拒絶する肉体、この世のあらゆる光を遮断する、事象の地平面(L’Horizon des événements)としての肉体のことを指す。
こうした肉体同士が、表面の中において、決闘不可能な決闘を行うこと。本作が試みるのは、それらが残した運動の軌跡を「物語」として提示することにほかならない。
謝辞
本作の特別映写にご協力いただいた国立映画アーカイブ映画室の鈴木理世さま、ならびに小杉山立夏子さまに感謝と御礼を申し上げます。ありがとうございました。
参考文献
Capel, Mathieu, Évasion du Japon : Cinéma japonais des années 1960, Les prairies ordinaires, 2015.
映画生誕百年祭実行委員会『光の誕生 リュミエール!』朝日新聞社、1995年。
蓮實重彥「無時間的体験の演技者」『シネマ70』1970年8月号。
宮川淳「マグリット──あるいは表面の発見」『宮川淳著作集Ⅱ』美術出版社、1980年。
中井正一「スポーツの美的要素」『中井正一評論集』岩波文庫、1995年。
高部遼「水平性の暴動──吉田喜重監督、別役実脚本未映画化シナリオ『万延元年のフットボール』を分析する」『Phantastopia』第2号、2023年。
浦岡敬一『映画編集とは何か──浦岡敬一の技法』平凡社、1994年。
吉田喜重「映画の壁・ストーリー主義批判」『自己否定の論理・想像力による変身』三一書房、1970年。
吉田喜重「見てはならない 幻のあの一球」『BIG-1物語 王貞治』パンフレット、東映株式会社・宣伝事業部、1977年。
吉田喜重「空間のエロティシズム──あるいは風景の臍について」『吉田喜重 変貌の倫理』青土社、2006年。
吉田喜重+小林康夫+西澤栄美子『宮川淳とともに』水声社、2021年。
図版
(図1)『ピストルによる決闘(長さ12m)』(ガブリエル・ヴェール撮影、1896年)
〔出典:Youtube「GUN FIGHT/Duel au Pistolet (Mexico) – 1896 Gabriel Veyre (HD+ remastered)」<https://www.youtube.com/watch?v=64QZcCxvMbI>最終閲覧日:2024年8月30日。〕
Notes
-
[1]
浦岡が編集を担当する吉田映画は、『ろくでなし』以来初。浦岡によると、彼と吉田はほとんど良好な関係が築けていなかったとされる。浦岡敬一『映画編集とは何か──浦岡敬一の技法』平凡社、1994年、136頁。
-
[2]
詳しくは、拙論「水平性の暴動──吉田喜重監督、別役実脚本未映画化シナリオ『万延元年のフットボール』を分析する」『Phantastopia』第2号、2023年、88-111頁を参照。
-
[3]
吉田喜重「映画の壁・ストーリー主義批判」『自己否定の論理・想像力による変身』三一書房、1970年、32-38頁。
-
[4]
吉田喜重「見てはならない 幻のあの一球」『BIG-1物語 王貞治』パンフレット、東映株式会社・宣伝事業部、1977年、3頁。
-
[5]
同書、4頁。
-
[6]
2023年6月にシネマヴェーラ渋谷で行われた吉田喜重の追悼特集でも、本作は上映されなかった。2006年にポレポレ東中野で行われた特集上映では上映作品のリストに本作があがっている。
-
[7]
本作中、吉田の顔が映り込むショットが一つだけあった。選手控室のような部屋で、王と吉田が対話しているシーンである。王の左手にはテレビと思わしきものが置かれており、その画面上に、インタビュアーである吉田の顔が反射して映し出されていた。
-
[8]
映画生誕百年祭実行委員会『光の誕生 リュミエール!』朝日新聞社、1995年、79頁。
-
[9]
蓮實重彥「無時間的体験の演技者」『シネマ70』1970年8月号、14-15頁。
-
[10]
Capel, Mathieu, Évasion du Japon : Cinéma japonais des années 1960, Les prairies ordinaires, 2015, p.340.
-
[11]
中井正一「スポーツの美的要素」『中井正一評論集』岩波文庫、1995年、90-104頁。
-
[12]
宮川淳「マグリット──あるいは表面の発見」『宮川淳著作集Ⅱ』美術出版社、1980年、322頁。(初出は、『みづゑ』1971年5月号)。
-
[13]
吉田喜重「空間のエロティシズム──あるいは風景の臍について」『吉田喜重 変貌の倫理』青土社、2006年、256頁(初出は、『エピステーメー』1977年7月号)。
-
[14]
吉田喜重+小林康夫+西澤栄美子『宮川淳とともに』水声社、2021年、19頁。
-
[15]
宮川「マグリット──あるいは表面の発見」前掲書、322頁。
この記事を引用する
高部遼「表面そして/または決闘──吉田喜重『BIG-1物語 王貞治』における非人称性について」『Phantastopia』第4号、2025年、44-52ページ、URL : https://phantastopia.com/4/surface-and-or-duel/。(2026年02月12日閲覧)