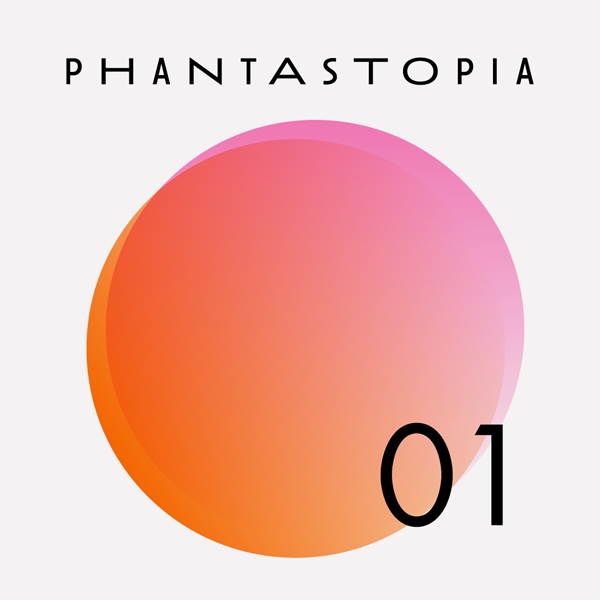ミシェル・ド・セルトーの思想を特徴づけるトポスのひとつに、「海」のイメージがある。それを示すテクストとしては、まず、かれの神学的マニフェストともいうべき「霊的経験」(1970年)を挙げることができる。神秘家の「道程〔itinéraire〕」を描くこの論攷において、その第一段階を画す例となるのが「オペラ座に向かおうとメトロに乗り、十字路に行き着くと突然、オペラ座ではなく海が見える」という「出来事」である[1]。個人的な体験に基づいていると窺わせる記述のなかで「海」は、言表しうる限界を超えた、日常のなかに「断絶〔rupture〕」を刻むものとして思い描かれている(「このことは表現されるのではない、経験されるのだ〔Ceci ne s’exprime pas, ceci s’expérimente〕」[2])。
くわえて、「海」のトポスは「島」や「浜辺」といった具体的な場所との結びつきをもつ。1976年のある論文では、神秘主義のディスクールは「押し寄せる海に臨む浜辺」に喩えられる。「それは、みずからが提示するもののなかに姿を消そう〔se perdre〕とする——空気と光によって消えゆく、ターナーの風景のように」[3]。なお、同論文には「砂州〔barre〕」のイメージも登場する[4]。「砂州」とは潮の流れや河川によって運ばれた土砂の堆積地であり、すなわち海と陸の狭間であるが、この「砂州」のイメージは明らかに、セルトーがしばしば引く『ロビンソン・クルーソー』の「島」のイメージに対置されている[5]。ロビンソンのように堅牢な「城砦」を中心にした、「保存し、検証し、征服する労働」[6]へ目的づけられたテリトリーを構築するのではなく、押し寄せては陸地を浸食してくる波を受けながら、あるいはそれを間近に目にしながら、「場所」が揺らいでゆくのを受けいれる神秘家のポジションを象徴するものとして、「砂州」は思い描かれているようだ。
さらに、歴史叙述論においても「海」のトポスは顔を覗かせている。セルトーが願うのは、歴史研究の認識論的な基礎そのものが揺らぎ——あるはずのない足跡を浜辺に見つけて戦慄するロビンソン・クルーソーのように[7]——意想外の事柄に巻き込まれ、「思考」[8]することを強いられる事態が生来することにほかならない。「研究者が分析のために用いる装置そのものを史料が変質させて」しまい、「研究者自身が史料に対して要求する事柄を、史料が提示する問いが変位させてしまう」とき[9]、かれは「奇異なるものの縁にみずからを見出すという好運」に与る[10]。このとき、「ひとは海へ向かう」[11]。このように、「海」は、既成の観念に囚われた見方や制度的枠組みが変容を被るさいに現れる形象として位置づけられている。
ここに概観したとおり、複数の領域を横断してテクストを彩る「海」のトポスがセルトーの思想においてどのような意義をもつかということに、本稿の関心は置かれる[12]。ただし、「海」とそれに関連するイメージ群がおそらくはセルトーの思想の全領域をカバーするものと考えられる以上、すべての観点を網羅するのではなく、ひとつの切り口に絞って議論を進めたい。すなわち、「書くこと」というモティーフである。エクリチュールについてのセルトー固有の問題系は、1970年代の前半に練り上げられるため、この時期に発表された一連の著作あるいは論文に本稿のコーパスを限定しておくのがよいだろう。
以下では、それらのテクストにみられる「死」、「時間」、「群衆」など、ほかのキーワードとの関連をふまえながらセルトーのエクリチュール論を読解してゆくが、本稿ではとりわけ「場所」という観点を重視したい。というのも「場所」は、セルトーにおける「書くこと」の問題構成を、いわばイメージの次元で基礎づけているものだからである。たとえば、『日常的なものの創造』の第1巻『もののやりかた』(1980年)において「戦略〔stratégie〕」と「戦術〔tactique〕」の対立的構図は、「場所」に関連する語彙によって展開される。「固有のものとして境界線を引くことができ、標的や脅威といった外部(客や競争相手、敵、都市周辺の田舎、研究の目標や対象など)との関係を管理するための基地にできるようなひとつの場所」に基づいた、対象への働きかけ、それが「戦略」である[13]。セルトーはその事例として、近代医学、植民地主義、都市工学などを挙げて検討をおこなうが、ここで重要なのは、「戦略」的な活動の範例として定位されるのが、ほかならぬ書くことであるという点である。エクリチュールは、自分の「場所」を構築して外部の対象に権能を及ぼし、未知なるものを取り込んで拡大するとともに、「時間」によって持ち込まれる摩滅や変転、不確実性を排除すること(「時間に対する場所の勝利」[14])を目指す活動として定位される[15]。さきに触れたロビンソン・クルーソーの「島」は、「書くこと」が権力を作用させる「戦略」的領域の寓意にほかならない。
その一方でセルトーは、「書くこと」を別の視角からとらえてもいる。「海」のトポスは、まさにそうした別様の「書くこと」が浮き彫りされるときに浮上する。以上に概観した「場所」をめぐる一連の形象——「場所/空間」[16]、「海」、「波」[17]、「砂州」、「島」、さらには「漂流」[18]、「難破」[19]、「地層」[20]なども含まれる——を、さしあたり場所論的(topique)なイメージと呼ぶことにしよう。以下では、セルトーの著作においてこれらのイメージが書くことと切り結んでいる必然的な関係、そして「戦略」的ならざる「書くこと」の実相を明らかにすることを試みる。
I. 大海のなかに失われる――「身体からエクリチュールへ」(1974年)
1974年の論攷「身体からエクリチュールへの、あるキリスト教的通過」において、セルトーは「書くこと」と「海」のイメージとを密接に結びつけている。本稿では何度も以下の一節に立ち返るが、まずはその記述を引用しよう。
ただかれひとりの言葉を物語るものでしかない、脆く〔fragile〕、漂うテクスト、だがそれでいて、数え切れない言葉のざわめきのうちに失われる、それゆえ儚い〔périssable〕テクストである。しかし、このものがたりがその資格によって告げているのは、みずからが描くもののうちに消滅し、おのれが生まれてきた名もなき務めに立ち返り、自身とは別の存在たるこの他なるものへと転じることの歓びにほかならない。信じるエクリチュールは、その弱さにおいて、ただ消え去るためにしか言語活動の海には現れない。このエクリチュールは、他のさまざまなエクリチュールが絶えず「寄ってきて〔viennent〕」は「去ってゆく〔s’en vont〕」運動を、それらのなかで露わにする務めにとらえられている。それは、神秘家たちの表現によるなら、「大海のなかの一滴」なのだ。[21](強調は原文による)
注釈をおこなうまえに、ここに引いたパッセージを取り囲む文脈を整理しておこう。一文目にいわれる「テクスト」とは、セルトー自身のそれを自己言及的に述べたものだ。この「テクスト」は、ジャン゠マリー・ドムナクとの対談の後記として『破砕したキリスト教』(1974年)に収められたもので、元々のタイトルは「大海のなかの一滴のように〔Comme une goutte d’eau dans la mer〕」であった。当時、『エスプリ』誌の編集長であったドムナクとの対談のテーマは「キリスト教、新たな神話?〔le Christianisme, une nouvelle mythologie ?〕」である。始終、セルトーの厳しい現状認識が告げられ、キリスト教の「フォークロア化」(過去の異物として享受されるにすぎない文化的な産物と化したこと)、教会から離れる者たちの増加などに話題は及ぶ[22]。セルトーの発言の深刻さは、『破砕したキリスト教』を刊行することで「〔イエズス〕会への「帰属」が困難になる、あるいは不可能になる」かもしれないとの危惧を書簡で打ち明けている事実からも窺える[23]。
それでは、具体的にセルトーはどのような発言をおこなったのか。質疑応答においてセルトーは、「キリスト教の信仰という、この特殊な選択が普遍的である(万人にとって真である)と想定することをやめなければなりません」と述べており、ドメナクはこの発言の真意をセルトーに問いただしている。ドメナクへ応答するセルトーは、「事実問題」としてキリスト教が限定的な現象であること、「権利問題」として、すなわちキリスト教の原理的なレベルにおいて、「絶対者とは普遍的ないし包括的な真理ではない」という認識があることを指摘する[24]。前後の文脈を補いながら敷衍すると、以上の発言は、「真理」とは出来合いの所与ではなく、自己の現在という限定的な地点から出発して探究される運動のうちにしかないという考えを仄めかすものである。そのような運動としてセルトーは「宣教」を挙げるのだが、「海」のイメージはその直後に引き合いに出される。注目すべきは、そこで「海」が「広大無辺な群衆〔foules immenses〕」、「不透明な人びと〔peuples opaques〕」と重ねられている点である(「知られざる神のざわめき」は「潮騒のようにわたしたちに届く」)[25]。セルトーのいう「群衆」をどのように解すべきだろうか。対談や同時期の論攷の内容をふまえるなら、教会に所属しない信仰者、霊的な活動家[26]、ブラジル独裁政権下のカトリック教会[27]、テクストのなかで名を明かされない有象無象の者たち[28]が「群衆」として念頭に置かれていると考えてよいだろう。だが、より重要なのは、「群衆」の具体的な内実ではなく、「群衆」という「海」とセルトーが結ぼうとしている関係のほうである。この関係にフォーカスするのが、さきに引用した一節にほかならない。
以上の文脈をおさえたうえで引用文に戻ろう。一見して確認できる事実として、一文目から最後まで、このパッセージは一貫して「海」のトポスのうちに置かれている。まず、セルトーの「漂う〔flottant〕テクスト」は、「ただ消え去るためにしか言語活動の海には現れない」、「大海のなかの一滴」に喩えられている。そのうえで、「……のうちに消滅する〔s’effacer dans〕」、「……に立ち返る〔retourner à〕」、「……へ転じる〔se convertir à〕」といった運動は「海」のなかに「失われる」ことと同義であると考えられ、イメージの水準において、「海」はこれらの述語の間接目的語と重ねられる。ただし注意しておかなければならないが、三つの目的語はそれぞれ異なることがらを指しているように思われる。というのも、テクストがそのなかに「消滅する」ところの「〔テクストが〕みずから描くもの」とは、描かれる対象であるが、「立ち返る」べき「名もなき務め〔travail anonyme〕」とは書くという行為を言わんとするものであり、それでいて、「自身とは別の存在たるこの他なるもの〔cet autre qu’elle n’est pas〕」とは、「転じ」られる方向として示唆されるかぎりで「テクスト」の宛先を意味するはずだからである。エクリチュールの対象、行為、宛先のいずれもが「海」のイメージによって結ばれ、同じひとつのものとして認められている。「海」が有象無象の「名もなき」人々、すなわち「群衆」と等置されていることと考えあわせるなら、以上の解釈から、いかなる帰結を引き出すことができるだろうか。
先へ進むまえに、一点注記しておきたい。そもそも、「大海のなかの一滴〔une goutte d’eau dans la mer〕」とは、神秘主義の伝統的なトポスを参照する比喩である[29]。以上に注釈した一節の末尾には註が付されており、クレルヴォーのベルナルドゥス『神を愛することについて』[30]、ハルフィウス『神秘神学』、フェヌロン「道徳とキリスト教的完徳をめぐる諸点についての教えと助言」[31]、スュラン『霊の導き』、そして自著『神秘のものがたり』第1巻が挙げられている[32]。『神秘のものがたり』を除くいずれのテクストも、魂と神との「合一〔union〕」を主題とし、海や葡萄酒などの流体的なイメージによって「合一」を叙述する点で特徴的である。こうした文脈をふまえたうえで「大海のなかの一滴」をめぐる先のパッセージを読みなおすなら、「書くこと」とはセルトーにとって「合一」の手段なのではないかという推測がおのずと導かれる。じっさい、テクストの前後の記述もまたそのような推測を妨げるものではない。ただしセルトーは、魂と他者が一つに溶け合う極点として「合一」を描いてはおらず、超越的な唯一神そのものを問題化しているわけでもない。以下でみるように、セルトーのエクリチュールが焦点とするのは、排他的な二者関係ではなく、一にして多であるような「あなた」との関係である[33]。以上をふまえて次節では、エクリチュールの対象、行為、宛先の同一性とは何を意味するのか、別のテクストをとりあげながら検討しよう。
Ⅱ. 二重の「あなた」——「エクリチュール」(1973年)
本節でとりあげるのは、1973年8月18日付の私的な覚書である。セルトーの遺稿管理者であるリュス・ジアールによって公にされた、この覚書の劈頭に掲げられる問いは、エクリチュールの根拠、あるいは起源にかかわっている。冒頭の一節を引こう。
どうして書くのか? 消えてしまわないようにするため。鋭敏に感じ取られた忘我の死に抗するために。それが最初のテクストだった——太陽あるいは海の様子を書き留めたもの……。束の間のめまいを固定し、とどめておくこと、それも、このめまいの後に続く、たったひとりで書く営みによって。[34]
引用文から指摘できることを四点に分けて述べてゆこう。まず、省察のなかでセルトーがフォーカスするのは、「忘我〔extase〕」と「めまい〔éblouissement〕」のあと、経験の強烈な印象が絶えつつある爾後の世界である。書く者が身を置いているのは、神秘的な経験——陽光に映える海を風景とする——が決定的に過去のものとなった地平なのだ。第二に、このような構造は、論攷「霊的経験」のなかで定式化されるものと類同的である。そこでも同様に、狭義の神秘的な経験そのものが問題として定位されるのではなく、出来事のあとに続いてゆく、歴史的な奥行きをもつ——神と信仰者、真理と主体とのあいだの関係が不断に組み代わってゆく過程——としての経験が問われている[35]。三つ目に指摘できる事柄として、「それが最初のテクストだった」といわれるが、原文では単純過去形で書かれている。ここには未だセルトーの一人称は現れていない。そのため、セルトーは自己経験に照らしつつもそれに限定せず、「テクスト」なるもの一般の神話的な起源を描こうとしているとも考えられよう。そして最後に、この段階での書くことは、「たったひとりで」遂行される孤独な営みと捉えられている。以上を確認したうえで、続くパッセージを見てゆこう。つぎのように、セルトーは明白に一人称を用いて自己経験を語りはじめる。
読まれるため、読みなおされるためにではなかった。わたしに到来した他なる何ものか、もしかすると記憶しえぬほど遥か太古からのもの、いかなる仕方によっても留めておくことができないかのものは、少なくとも、ある形象のもとで残りつづけるはずであった。ただし、この書かれた言葉という形象は、到来したものを貧しくさせてしまい、わたしのもとから逃れていった。不意に到来するものは、わたしにとって日常的なものに対する「忘却」であった。ただしそのあとで、わたしは別種の忘却に——まったく徒労に終わるのだけれど——抗することになる。そこに留まること、それを保持しておくことがわたしにはできないという忘却に。だから書かれた言葉は、わたし自身にはこの二重の不在を描くものだった。つまり、わたしに窓を開けてくれた不在と、窓のそばにとどまりつづけることをわたしにゆるさない不在。[36]
初めに焦点となるのは、「書かれた言葉という形象」の無力、それゆえの失望の経験である。感覚的な印象を同定しようとする言葉は、印象そのものの鮮烈さと釣り合うことなく、埋めようのない隔たりをもたらす[37]。「書かれた言葉」が出来事(「わたしに到来した他なる何ものか」)を掬い取ってはくれない以上、経験の記憶は摩滅してゆくほかない。つぎに、「忘却〔oubli〕」という語に注目してみよう。第一の「忘却」は、「日常的なもの」とは別の次元を垣間見せる。それに対して「別種の忘却」は、基調としては「他なる何ものか」との出会いの印象が失われてゆくことを意味するが、それがたんに否定的な経験としては叙述されていない点に注意しておこう。このことを念頭に置いて記述を辿りなおすと、まず、セルトーは第一の「忘却」を二つの方向から、すなわち「書かれた言葉」の無力からも、出来事の性質自体からも(「いかなる仕方によってもとどめておくことができないかのもの」)説明することで、書くことの虚しさを強調しているようにみえる。つづいて二つの「忘却」に対応する形で「二重の不在」が描かれるのだが、興味深いのは、そこで「窓」のイメージが用いられている点だ[38]。「窓」のイメージは、閉じた場所と開かれた世界のコントラストを導入する。それゆえ、このイメージを介して、「書かれた言葉」の無力はたんなる否定的な事実以上の価値を持つことになる。「窓」から外に出てゆくことは、出来事の記憶が薄れゆくなかで、それでも書くことをやめないことを示唆するからである(「窓のそばにとどまりつづけることをわたしにゆるさない」)。「それを保持しておくことがわたしにはできない」という「別種の忘却」は、「わたし」にとって新たな始まりを画すモーメントとなるのだ。
直後のパラグラフでは、論文執筆のような「労苦としてのエクリチュール〔écritures-labeurs〕」に省察の照準が向けられる。そこでセルトーは、出来事の印象ができるかぎり失われないようにとどめておくためのエクリチュールから、知的な分析過程としてのエクリチュールへと次第に移行してゆくという前提のもと、叙述を試みているように思われる。だが「じつを言うと」、とセルトーは続ける。「じつを言うと、書くという仕事には、漂流の経過が点線として刻まれている。書くことは、理解ではなく隔たりの実践であり、思考を形づくるのではなく探し求めるような活動であって、それは築きあげるというよりも移りゆく〔passer〕行為である」[39]。「漂流〔dérive〕」という語は、最初の段落に現れた「海」のイメージと連動しながら、書くことを空間的な変位の実践(「移りゆく行為」)として特徴づけていると考えてよい。言い換えれば、「みずからは変容されずに拡大してゆく、同〔le même〕による占有の空間」[40]を構築するのではなく、むしろその場所の脆さ、不安定性を受け入れてゆくプロセスとしてエクリチュールはとらえられている。このように、書く行為が「わたし」よりも大きな流れのなかで運ばれてゆく「漂流」の経験でもあることは、テクストの核心をつかむうえできわめて重要な点であるように思われる。つづく段落から引かれる以下のパッセージもまた、別のことを告げてはいない。
「やってきて」は「去ってゆく」ようすをとらえる「パースペクティヴ」を、テクストのうちに——わたしの書いたテクストであろうと他人のテクストであろうと同じことだ——探し求めること、それが書くということである。それが逃げ去る、あるいは近づいてくる角度を見出そうとし、別の仕方ではとうてい語ることができないものを運び去っては再びもたらしにやってくる運動(「文学的」な運動、それとも「現実的」な運動——どちらも同じことではないか)の軸を探し当てようとする、注意を要する仕事。これこそ、一つのテクストをめぐって、わたしが読みはじめるもの、あるいは書きはじめるものが最初に開始させる務めなのであって、それこそ、テクストを「つくる」という巡りゆく労苦が物語ろうとする事柄にほかならない。[41]
「やってきて〔il vient〕」は「去ってゆく〔il s’en va〕」、「運び去っては再びもたらしにやってくる運動〔mouvement qui emporte et rapporte〕」は、浜辺に絶えず押し寄せる波のイメージを喚起させるとともに、前節で引いた一節に含まれる「他のさまざまなエクリチュールが絶えず「寄ってきて」は「去ってゆく」運動」[42]とも呼応する。こうした記述からは、セルトーが、過去に遭遇した出来事の記憶をとどめておくためでも、知的な分析作業としてでもない、別様の営みとしてのエクリチュールの次元に迫ろうとしていることをはっきり見てとれる。対象を同定することは叶わないが、それが「わたし」の「パースペクティヴ」から「逃れ去」ったり「近づい」たりする律動を捉えることはできるというのである。つまり、「別の仕方ではとうてい語ることができないもの」が波のように寄せては返すリズムを「読む」ことこそ、書くことの中心で作動している実践にほかならない。ここで肝心なのは、自分が書いたテクストと他人が書いたテクストとのあいだに区別が設けられていない、いいかえれば、両方ともが同様に巻き込まれている「運動」こそが問題となっていることである。したがって、次のように敷衍できるだろう。この「運動」を表現するとき、「たったひとりで」遂行される書くことの孤独は和らげられる。書く主体の場所が一定でなく過渡的であり、揺れ動くものとして認められることは、書くことの共同的な次元、すなわち書くことは本質的にともに書くことであるという根本的な事実を明かすのだ。
とはいえしかし、以上と引き合わせて考えなくてはならない点がある。すなわち、書くことの共同性が、むしろ「わたし」が書くことの限界を徴づけてもいるということである。それは覚書の最後の段落にいたって、時間的な限界として現れる。「死」という語そのものが現れるわけではないが、セルトーが以下のように述べるとき、自分自身の「死」という限界を念頭に置いていることは明らかではないだろうか。
〔エクリチュールを〕絶えず生成するこの亀裂を指で辿りながら、わたしは、錯覚と再認とが移り替わる運動のなかに自分がとらえられていることを知っている。さりながら、恐れられてもいれば望まれてもいる疎外の経験につきものである、かくなる両義性を最終的に乗り越えてゆくものは何ひとつとして存在しないだろうし、「わたしがあなたへ最後に書くべきだった言葉」によっても、両義性が乗り越えられることはないだろう。あなた——あなたとはだれだろうか——ただひとりにして幾人でもあるあなたへと、わたしは、この仕事を絶えず捧げている。[43]
ここでセルトーが述べていることはそれほど複雑ではない。「再認〔reconnaissance〕」と「錯覚〔illusion〕」とのあいだを揺れ動く「移り替わり〔alternance〕」、すなわち理解と誤解、誤解の自覚と再解釈からなる倦むことなきプロセスは、発展や深化として捉えられてはいない(「両義性を最終的に乗り越えてゆくものは何ひとつとして存在しないだろう〔rien ne la [=ambivalence] surmontera définitivement〕」)。唯一ここでのみ動詞の未来形が用いられている点は注目に値する。未来形は、「最終的に」という副詞と、それに続く「わたしがあなたへ最後に書くべきだった言葉〔les derniers mots que je t’aurais écrits〕」における条件法過去と呼応して、先取りされたセルトー自身の「死」を示唆する。ひるがえって、「死」という絶対的なリミットは、「死」によってさえ「乗り越える」ことのできない「両義性」を浮かび上がらせる。そして「両義性」を生み出すのは、突きつめていえば、セルトーが描こうとする対象、すなわち「運び去っては再びもたらしにやってくる運動」、「他のさまざまなエクリチュールが絶えず「寄ってきて」は「去ってゆく」運動」であろう。
テクストの最終文では、書くという「仕事〔travail〕」の宛先、「あなた」の存在が明示される。この「あなた」が「ただひとりにして幾人でもある〔unique et multiple〕」といわれている点は決定的に重要である。なぜなら、唯一であると同時に有象無象でもあるという宛先の二重性は、書くことの対象の二重性、すなわち「わたしに到来した他なる何ものか」の単独性と、波のざわめきのように「他のさまざまなエクリチュールが絶えず「寄ってきて」は「去ってゆく」運動」の複数性からなる二重性と厳密に対応するからである。
この「ただひとりにして幾人でもあるあなた」を、たとえば、福音書のイエスとあえて重ねてとらえることも可能であるように思われるが、本稿ではそのような解釈をとらない。そもそも、「あなた」の身分そのものをセルトーは問いに付しており(「あなたとはだれだろうか」)、「わたしに到来した他なる何ものか」の捉えがたさが主題化される以上、「あなた」の形象を特定の名と同一視することは、テクストのねらいと齟齬をきたすことになりかねない。この私的なノートは、「あなた」を「イエス」や「神」といった固有名にすり替えてしまった途端に見失われる繊細な次元を問題にしているのだ。「戦略」的ならざるエクリチュールにおいて表出するのはそのような次元——いかなる存在も匿名的にならざるをえない——であり、それを描くための形象として、「海」をめぐる「場所論的」なイメージが要請されているのだと考えることができる。
前節においてわたしたちは、エクリチュールにおける対象と行為と宛先の同一性という解釈を1974年の論攷から引き出したが、その解釈を、本節の議論を振り返る形で再定式化してみよう。セルトーにとって書くことは、「わたし」が被った出来事(「束の間のめまい」、「不意に到来するもの」)の印象をとどめるための孤独な営為であり、同時に、書く行為それ自体の虚しさ、描きたいと願うもののとらえがたさが露呈されてくるプロセスにほかならない。だが、書くことがその虚しさを明かせば明かすほどに、自分が描き取ろうとする「運動」へと、自分が書いたのではないテクストもまた同じように巻き込まれているという共同性が浮かび上がる(「他のさまざまなエクリチュールが絶えず「寄ってきて」は「去ってゆく」運動を[……]露わにする務め」)。「海」のトポスは、このような過程全体をイメージの水準で支えており、書くこと——「漂流」あるいは「渡りゆく」こと——のなかで対象と宛先は一つになり、書く者は「ただひとりにして幾人でもあるあなた」——海あるいは群衆——のうちに「消滅する〔s’effacer〕」、あるいは「消え去る〔disparaître〕」。
以上を踏まえて前節の引用文を読みなおすとき、そこでエクリチュールの「弱さ」が執拗に際立たせられていることに気づく。「脆く[……]それゆえ儚いテクスト〔texte fragile […], et donc périssable 〕」とセルトーはいう[44]。« périssable »の語幹« périr »、ならびに「消滅する」、「消え去る」といった語は、セルトー自身の「死」をいやおうなく喚起する。このように示唆される「死」をどこまで文字通りの意味で解すべきかは断定できないものの、その記述からは、「死」を先取りする、もっといえば待望する時間性をセルトーが書く行為に付与していることがうかがえる。Ⅲ節では、「海」を素地とする場所論的なイメージ群のなかで具体化される書くことの時間性、ならびに「死」への関係を検討してみよう。
Ⅲ. 喪失を弁証法化する——「名づけえぬものを書く」(1975年)
1975年9月、ユゲット・ブリアン゠ル・ボットらを編集主幹とする雑誌『トラヴェルス』の第1号に、セルトーは「名づけえぬものを書く(Écrire l’innommable)」というエッセーを寄稿している[45]。創刊号の冒頭を飾るこのエッセーのなかで初めにとりあげられるのは次のような光景である——「瀕死の病人があると、病院のスタッフたちは〔患者を病室に置き去りにしたまま〕引きこもってしまう」[46]。なりふり構わずに断末魔の叫びをあげる「瀕死の者」がほかの患者から引き離されるのは、「末期の時」を迎えつつある「病人」の悶え苦しむ声が、「不安、絶望、苦痛の発話行為を周囲の者が耐え忍ぶことの不可能性」を露わにするからだ[47]。いいかえれば、「死」という存在論的な臨界点を前にして、言語と制度の無力が明らかになることをあらかじめ防ぐためである。
このエッセーは、加筆・修正を経て『もののやりかた(Arts de faire)』に最終章(「名づけえぬもの——死」)として収録されるが、同書を序論から読み進めてきた者にとっては、以上に概観した病院内の「操作」は自己に固有の場を構築し堅守しようとする「戦略」のパラダイムに属するものであることが容易に了解される。セルトーはこのような「操作」に対して「いたずらに死を待つしかない者」の身振りを対立させているわけだが、「戦略」の範例的活動がほかならぬ「書くこと」であったことを思い起こしておくなら、ここでセルトーは、二つの「書くこと」を対立させていることになる。すなわち、未知なるものや偶然性を排除するロビンソン的なエクリチュールと、外部者として抑圧される「瀕死の者」のエクリチュールの対立である。ただし、この対立的な構図のなかでセルトーは、後者にみずからのテクストを重ねながらも、同一化を周到に避けている。というのも、「瀕死の者」を誇張的に、いくぶん戯画的に描くことで「死」に「表象」を与え、「死」を自分とは関係のない別の場所に「悪魔祓い」してしまわないようにするためである[48]。それほどに「死」は、セルトーの書く欲望にとって本質的な何かなのだ。ところで、このエッセーが興味深いのは、セルトーが、日常行為の「戦略/戦術」をめぐる分析からいっとき離脱するようにして、自分自身にとって書くとは、死ぬとはどういうことであるかを打ち明けている点にある。書物への再録にあたってセルトーは少なからぬ加筆・修正をおこなっているが[49]、以下に引用するのは、丸ごと加筆されたパラグラフである。書物の終盤にいたって、文体はほとんど自分語りのような様相を呈してくる。
それでもなお、死ぬこと、信じること、語ることは、最初から最後まで一致している。じっさい、わたしが生きてきたなかで最終的に信じることができるのは、わたしの死だけである——もしも信じるということが、わたしに先立ち、たえず来たってやまない他者との関係を指し示すのであれば。わたしの死と同じほどに「他なる」ものは存在しない。わたしの死とはあらゆる他性の指標なのだから。だが、わたしの死以上に、わたしがそこから語るところの場所を証しているものもない。わたしはその場所で、他者への願い、他者を待ちのぞんでいるのに無力な言葉のなかに——保証もなく捧げるべき財さえも持たずに——受けいれられることへの感謝を語るのである。それゆえ、話すとはどういうことかを、わたしの死以上に正確に規定するものもない。[50]
かいつまんでいえば、ここでセルトーが述べているのは次のようなことだ。まず、「わたし」と「わたしの死」の関係を基準として、「わたし」と「他者」——つまり「信じる」相手——との関係を測ることができる。というのも「わたしの死」とは、どこまでいっても経験可能な領野からは逃れ去るものであって、その意味で、「わたし」にとってもっとも「他なる」ものであるからだ。だがその一方で、「わたしの死」は、「わたし」以外の誰にも代わってもらえないという意味で、「わたし」自身が話す言葉の「場所」を深くしるしづけてもいる。このように「死」を基軸として、「信じること」と「語ること」が結びつくというのである。
引用文にあらわれる「他者」は、私的なメモのなかに見られた「ただひとりにして幾人でもあるあなた」と重ねて解釈しうるように思われるが、まずは引用文から直接読み取れることがらを指摘しよう。第一に、ここでもまたセルトーの思考には「場所」のイメージがついてまわっている。セルトーは、「語ること」や「話すこと」はどのような営みでありうるかをそのまま説明するかわりに、「わたしがそこから語るところの場所」について語る。つぎに、セルトーにとって「語ること」——文脈からいって「書くこと」と換言しうる——に刻印されている「わたしの死」は、ここでは、たんなる時間的な限界ではなく、「語ること」を本質的に特徴づけるような「あらゆる他性の指標」として示されている。さいごに、宛先の存在が明示されるが(「他者への願い、他者を待ちのぞんでいるのに無力な言葉のなかに[……]受けいれられることへの感謝」)、この「他者」には、おそらくは往時の作家などを含む過去の人々も、セルトーのテクストの読者となりうるまだ見ぬ人々も含まれると考えられる(「わたしに先立ち、たえず来たってやまない他者との関係」)。つまり、書くことが読者とともに〈わたしたち〉というテクストの共同体をつくるとしても、そこにはセルトーが読んだ過去の書き手も含まれており、ひいてはセルトーの読者が書くことになるテクストの読者もまた、その〈わたしたち〉に参与する。「死」への問いを介することでセルトーが浮き彫りにしようとするのは、この潜在的な〈わたしたち〉の次元なのだ。
以上に引いたパッセージのすこし後で、セルトーはふたたび「場所」のイメージをもちいて書くとはいかなる謂いかを語るのだが、そこには「わたしに先立ち、たえず来たってやまない他者との関係」により焦点を絞った記述がみられる。
エクリチュールの始原には、一つの喪失がある。語りえぬもの——現前と記号とのあいだの、不可能な一致——、それが〔書くという〕不断の仕事の前提条件であり、その仕事の原理とは、同一性の非-場所とものの犠牲にほかならない。[……]エクリチュールは、その綴り一つひとつ、言語を横切ってゆく歩みの残す遺物の一つひとつによって、どこまでもこの欠如を反復しつづけてゆく。エクリチュールは自分自身の前提条件にして宛先となる、一つの不在をたどたどしく呟いてみせる。だれかが空けていった場所を占めてはまた空けてゆく歩みをたどりつづけ、自己から逃れてゆく外部と結ばれ合っている。そうしてエクリチュールが結ばれているのは、他所からやってくる名宛人であり、到来を待ちわびながら、けっしてその声を聞くことのできない来訪者、欲望の旅路がページのうえに描いていった文字の道の途上ではけっして声の聞こえぬ来訪者なのである。[51]
「エクリチュールの始原には、一つの喪失がある」という一節をスタティックに解釈してはならない。つまり、その含意を、〈エクリチュールの起源とは一つの喪失である〉というテーゼに還元することを避けなくてはならない。取り返しのつかない仕方で貴重な何かが失われてはじめてエクリチュールは可能となる、あるいは決定的な「喪失」こそが創造行為の起源にある——以上のパッセージをこのように要約するのは、いくぶん単純にすぎるように思われる。そもそも、ここでセルトーが焦点を当てているのは、「書くこと」の起源としての「喪失」ではなくて、「喪失」を「仕事の原理」とする「書くこと」である。セルトーは「喪失」を絶対化——それゆえ実体化——しているのではなく、時間化しているのだ(「どこまでもこの欠如を反復しつづけてゆく」)[52]。
「喪失」を時間化するとはどういうことか。それは、「喪失」を一度かぎりの例外的な経験とするのでなく、失いつづける過程(「欲望の旅路〔voyages d’un désir〕」)として呈示することである。その過程は、「語りえぬもの」をそれでもなお「たどたどしく呟く〔épeler〕」、いいかえれば、「現前と記号とのあいだの不可能な一致」ゆえに充分には記述できない、語り尽くせないものを再び認識してゆく過程と一致する。「物の犠牲〔sacrifice de la chose〕」という——それ自体はヘーゲルに由来する——きわめてラカン的な言い回しをもちいているのは、「現前と記号とのあいだの一致」の不可能性に抗して、あるいはそれゆえに書こうとする欲望の弁証法を特徴づけるためであろう[53]。「喪失」を時間化するとは、「喪失」を弁証法化することに等しいのだ[54]。
つぎに、二文目の「同一性の非-場所〔un non-lieu de l’identité〕」という表現に注目しよう。くだんの私的なメモのなかで、セルトーが書くことを「移りゆく〔passer〕」ことになぞらえていた点を思い起こしておきたい。いま検討の俎上に載せているエッセーにおいても同様に、書くことは、固定した場所に身を据えて「戦略」的な拠点を防衛するのではなく、過渡的な「歩み〔marche〕」としてとらえられている。重要な点なので注記しておくと、セルトーにおいて「非-場所」(「場所をもたざるもの」と訳すこともできる)とは「時間」と呼応する符牒である。『歴史と精神分析——科学とフィクションのあいだ』の第四章から、簡にして要を得た一節を引こう。
時間とはまさしく、場所に対してみずからを一致させることの不可能性である〔Le temps est précisément l’impossibilité de l’identité au lieu〕。[55]
一つの場所にとどまることは、ほかの無数の場所に(同時に)いる可能性を否定することに等しい[56]。ひるがえって、書くことは、既存の制度や知を押し流してゆく「時間」の破壊作用——その最終的な帰結はもちろん「死ぬこと」だ——のうちに身を置き、他所へと連れてゆかれることであるだろう。「同一性の非-場所」という表現によってセルトーは、エクリチュールに時間を与える。それは、時間による摩滅から身を護り、時間そのものに内在する不確定性や偶然性を排除するのではなく、時間に身をさらすエクリチュールにほかならない。
引用文の後半で焦点となるのは、「宛先」の問題である。やはりここでも、セルトーは「場所」のイメージを駆使している。「宛先」、すなわち「ただひとりにして幾人でもあるあなた」が問題となるのだから、ひいては、書くことによって形成される〈わたしたち〉こそがここで主題化されているとみることもできる。そのようなエクリチュールの共同性は、前節では「海」のトポスのなかで展開されていたが、ここで「海」や「波」のイメージは現れていないようにみえる。たしかに、海に類した風景はテクストから読み取れない。だが、「海」の「運動」を、寄せては返す波のリズムを聴き取ることはできる。「喪失」を弁証法化する反復的な律動は、まず矛盾として(「現前と記号とのあいだの不可能な一致」)、つぎに連続として(「この欠如を反復しつづける」、「不断の仕事〔travail toujours recommençant〕」)、また移動として(「だれかが空けていった場所を占めてはまた空けてゆく〔procéde[r] par abandonnements successifs des places occupées〕」)あらわれている。セルトーの〈わたしたち〉は、このようなリズムのなかに表出する。I節で引用したパッセージには、「消滅」し「消え去る」ことへの「歓び」が語られていたが、セルトーにおいて「死ぬこと」が「歓び」でありうるのは、「死」の可能性のなかにあるエクリチュール、つまり時間化されたエクリチュールだけが、〈わたしたち〉を表出させるリズムや「運動」を描くことができるからであろう。
ここまで、1973年の生前未刊行のテクストから1975年のエッセーへ(加筆と修正を加味するなら1980年の『もののやりかた』へ)いたる一連のセルトーのテクストをたどってきた。その作業から明らかになったのは、セルトーにおいて、「海」を中心に組織される場所論的なイメージ群と書くことのあいだには密接な思想的関係があるという事実である。「海」のイメージのもとで展開されるかれのエクリチュールの思考は、以下の三つの性質によって特徴づけられるといえる。第一に、「語りえぬもの」の前にした言葉の無力(「現前と記号とのあいだの不可能な一致」)。第二に、先取りされた「死」の時間性(「同一性の非-場所」)。第三に、書くことの対象・行為・宛先の同一性(〈わたしたち〉)。Ⅰ節の末尾でみたように、セルトーはみずからの思想を神秘主義の伝統的なトポスに引き寄せつつ、エクリチュールをめぐる独自の思考として(あえていえば、ひとつの「哲学」として)展開しているのだ。
以上を別の角度からいいかえて結論を導こう。セルトーのエクリチュール論は、「語りえぬもの」に焦点を当てるかぎりにおいて、やはり一種の否定神学なのだろうか。十全に語ることの不可能性を描くことによって、むしろその対象の唯一性や重要性を浮き彫りにするのがセルトーの主眼であったといえるだろうか。たしかに、そのような企図をセルトーの記述のなかに探知することはできる。だが本稿が明らかにしたのは、セルトーのエクリチュール論はそれに尽きるものでないということであった。書けないことを書くという果てしない迂回と接近は、エクリチュールの自己目的化と表裏一体である。セルトーが描こうとしているのは、そのような自己目的化が徹底され、孤絶した活動として閉じられてゆくにつれて、その極限において、むしろひとりではありえないような次元が開示されるという事態にほかならない。それは、書く者が露わにする「運動」にほかのテクストもまた巻き込まれている事実によって示されるのであり、書き手たるセルトーは、「ただひとりにして幾人でもあるあなた」とともにその「運動」を描く。このような思考をなおも否定神学的といいうるとすれば、それは否定神学それ自体を変容させる否定神学であるといわねばならないだろう。なぜなら、セルトーにおいて「語りえぬもの」とは思考の虚焦点のようなものではなく、それでもなお(誰かとともに)語らずにはいられないものだからである。
参考文献
[ミシェル・ド・セルトーの文献]
CERTEAU, Michel de, L’Absent de l’histoire, Ligugé, Mame, 1973.
——, « Écritures » [1973], in Luce Giard (dir.), Michel de Certeau, Paris, Centre Georges Pompidou, « Cahiers pour un temps », 1987.
——, Le christianisme éclaté, Paris, Seuil, 1974.
——, « L’énonciation mystique », Recherches de Science Religieuse, 64/2, 1976.
——, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire [1980], éd. Luce Giard, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1990.[『日常的実践のポイエティーク』山田登世子訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2021年]
——, La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle [1982], Paris, Gallimard, Coll. « Tel », 2003.
——, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987.
——, L’étranger ou l’union dans la différence, éd. Luce Giard, Paris, Seuil, « Point Essais », 2005.
——, Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, édition établie par Luce Giard, Gallimard / Seuil, 2005.
——, La fable mystique II, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 2013.
Bernard de Clairvaux, L’amour de Dieu, La grảce et le libre arbitre, introductions, traductions, notes et index par Françoise Callerot, Paris, Éditions du Cerf, « Sources chrétiennes », 1993.[ベルナール『キリスト教神秘主義著作集2 神を愛することについて 雅歌の説教』金子晴勇訳、教文館、2005年]
[二次文献]
DOSSE, François, Michel de Certeau, La marcheur blessé, Paris, la Découverte, Coll. « Poche » 2007.
FÉNELON, « Instructions et avis sur divers points de la morale et la perfection chrétienne », Œuvres complètes, précédées de son histoire littéraire par M. Gosselin, tome VI, Genève, Slatkine Reprints, 1971.
LE BRUN, Jacques, Le pur amour de Platon à Lacan, Paris, Seuil, 2002.
PETITDEMANGE, Guy, « Le deuil impossible de la mystique » [1999], Les Chemins d’histoire, sous la direction de Christian Delacroix, Bruxelles, Éditions Complexe, 2002.
RUUSBROEC, Jan van, Vanden Blinkenden Steen, in Corpvs Christianorvm, Continuatio mediaevalis 110, edited by G. de Baere, Th. Mertens and H. Noë, translated into English by A. Lefevere, translated into Latin by L. Surius, Tielt: Lannoo / Turnhout: Brepols.[ヤン・ファン・ルースブルーク「「燦めく石」あるいは「指環」について」柴田健策訳、『中世思想原典集成17 中世末期の神秘思想』平凡社、1992年]
坂口ふみ『個の誕生―—キリスト教教理をつくった人びと』岩波書店(岩波現代文庫)、2023年[1996年]。
TERESTCHENKO, Michel, Amour et désespoir. De François de Sales à Fénelon, Paris, Seuil, « Points », 2000.
鶴岡賀雄「現前と不在―—ミシェル・ド・セルトーの神秘主義研究」『宗教哲学研究』第19号、2002年、26頁。
渡辺優『ジャン゠ジョゼフ・スュラン——一七世紀フランス神秘主義の光芒』慶應義塾大学出版会、2016年。
WATANABE, Yu, « Lire Surin et/ou lire Certeau », Michel de Certeau. Le voyage de l’œuvre, sous la direction de Luce Giard, Paris, Facultés jésuites de Paris, 2017.
——, « Michel de Certeau, lecteur/auditeur des mystiques. Écouter le murmure de l’Absent », Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 06 August 2024, https://doi.org/10.30965/23642807-bja10103[最終アクセス:2024年12月26日].
Notes
-
[1]
Michel de Certeau, « L’expérience spirituelle » [1970], L’étranger ou l’union dans la différence, éd. Luce Giard, Paris, Seuil, « Point Essais », 2005, p. 4.
-
[2]
Ibid.
-
[3]
Id., « L’énonciation mystique », Recherches de Science Religieuse, 64/2, 1976, p. 185 ; Id., La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle [1982], Paris, Gallimard, « Tel », 2003, p. 27.
-
[4]
« L’énonciation mystique », art. cit., p. 201.
-
[5]
Id,, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire [1980], éd. Luce Giard, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1990, p. 202[『日常的実践のポイエティーク』山田登世子訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2021年、324頁]. 以下を参照のこと。福井有人「ミシェル・ド・セルトーにおける「場所」の問題——歴史記述と神秘主義をめぐって」『フランス哲学・思想研究』第25号、2020年、175-185頁。
-
[6]
Id., L’écriture de l’histoire [1975], Paris, Gallimard, « Folio Histoire », 2002, p. 256.
-
[7]
Id., L’Absent de l’histoire, Ligugé, Mame, 1973, p. 179 ; L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, op. cit., p. 225-226[『日常的実践のポイエティーク』、358-360頁].
-
[8]
Ibid., p. 296[同書、459頁].
-
[9]
Id., « Historicités mystique », La fable mystique II, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 2013, p. 19.
-
[10]
セルトーによる歴史実践の認識論的批判については、以下を参照のこと。福井有人「幻視する解釈者―—ミシェル・ド・セルトーにおける「記憶」の概念について」『超域文化科学紀要』第27号、2022年、37-53頁。
-
[11]
« Historicités mystique », art. cit., p. 19.
-
[12]
「海」のトポスがセルトーのテクストにおいてもつ存在感の大きさにもかかわらず、その意義はじゅうぶんに顧みられていない。例外として、以下の渡辺優による研究と、僅かながら「海」への言及をふくむギイ・プティドマンジュの論攷を参照のこと。Yu Watanabe « Lire Surin et/ou lire Certeau », Michel de Certeau. Le voyage de l’œuvre, sous la direction de Luce Giard, Paris, Facultés jésuites de Paris, 2017, pp. 97-99 ; Id., « Michel de Certeau, lecteur/auditeur des mystiques. Écouter le murmure de l’Absent », Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 06 August 2024, https://doi.org/10.30965/23642807-bja10103[最終アクセス:2024年12月26日]; Guy Petitdemange, « Le deuil impossible de la mystique » [1999], Les Chemins d’histoire, sous la direction de Christian Delacroix, Bruxelles, Éditions Complexe, 2002, p. 52.
-
[13]
L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, op. cit., p. 59[『日常的実践のポイエティーク』、119頁]. 強調は原文による。
-
[14]
Ibid,, p. 60[同書、120頁]. 強調は原文による。
-
[15]
Ibid,, p. 198-205[同書、319-330頁].
-
[16]
Ibid,, p. 172-175[同書、283-286頁].
-
[17]
La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle, cit., p. 408-410.
-
[18]
L’écriture de l’histoire, cit., p. 256.
-
[19]
La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle, op. cit., p. 319.
-
[20]
Ibid., p. 305.
-
[21]
Id., « Du corps à l’écriture, un transit chrétien », La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 305. Cf. Michel de Certeau et Jean-Marie Domenach, Le christianisme éclaté, Paris, Seuil, 1974, p. 71.
-
[22]
Ibid., p. 9-13, 24-27, etc.
-
[23]
1974年3月13日、スティーヴン・イングランド宛の書簡(François Dosse, Michel de Certeau, La marcheur blessé, Paris, la Découverte, Coll. « Poche » 2007, p. 201)。
-
[24]
Le christianisme éclaté, cit., p. 69.
-
[25]
Ibid., p. 71.
-
[26]
La faiblesse de croire, op. cit., p. 277.
-
[27]
Ibid., p. 147-156, 309.
-
[28]
La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle, op. cit., p. 281-285, 328-329.
-
[29]
ミシェル・テレスチェンコはギュイヨン夫人の「奔流〔torrents〕」を論じるなかで、神秘主義における海のトポスをエックハルトならびにマルグリット・ポレートに送り返している。Michel Terestchenko, Amour et désespoir. De François de Sales à Fénelon, Paris, Seuil, « Points », 2000, p. 132. テレスチェンコはほかにも、十字架のヨハネ『愛の生ける炎』(str. I, v. 6, n. 30, etc.)などを引き合いに出し、神への合一が海/河のメタファーによって語られることに注意を促してもいる(ibid., p. 144-145, n. 9)。
-
[30]
セルトーが送り返している箇所においてベルナルドゥスは、三つの比喩、すなわち、葡萄酒に溶け込む一滴の水、火と同化するほどに熱せられた鉄、太陽の光に染まる空気によって愛の合一を説明している。Bernard de Clairvaux, L’amour de Dieu, La grảce et le libre arbitre, introductions, traductions, notes et index par Françoise Callerot, Paris, Éditions du Cerf, « Sources chrétiennes », 1993, p. 130-133[ベルナール『キリスト教神秘主義著作集2 神を愛することについて 雅歌の説教』金子晴勇訳、教文館、2005年、38-39頁].
-
[31]
ただし、セルトーの参照する箇所に海のイメージや流体的な比喩は現れていない。Fénelon, « Instructions et avis sur divers points de la morale et la perfection chrétienne », Œuvres complètes, précédées de son histoire littéraire par M. Gosselin, tome VI, Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 116.
-
[32]
論文内で挙げられてはいないが、ヤン・ファン・ルースブルーク『「燦めく石」あるいは「指環」について』の第9章も考えあわせなくてはならないだろう。Jan van Ruusbroec, Vanden Blinkenden Steen, in Corpvs Christianorvm, Continuatio mediaevalis 110, edited by G. de Baere, Th. Mertens and H. Noë, translated into English by A. Lefevere, translated into Latin by L. Surius, Tielt: Lannoo / Turnhout: Brepols, p. 152, 154[ヤン・ファン・ルースブルーク「「燦めく石」あるいは「指環」について」柴田健策訳、『中世思想原典集成17 中世末期の神秘思想』平凡社、1992年、304頁].
-
[33]
もちろん、一にして多であるような「神」こそすぐれてキリスト教的な形象であるというべきであろう。この点については、坂口ふみ『個の誕生──キリスト教教理をつくった人びと』岩波書店(岩波現代文庫)、2023年[1996年]、とりわけ74-88頁を参照のこと。ただしここでは、セルトーが「神」という固有名をもって対象を同定することをあえてしない、という事実に鑑みて、テクストの論理を再構成し論及することに注力したい。
-
[34]
Michel de Certeau, « Écritures », in Luce Giard (dir.), Michel de Certeau, Paris, Centre Georges Pompidou, « Cahiers pour un temps », 1987, p. 13. リュス・ジアールによれば、このテクストが書かれた1973年夏は、『歴史のエクリチュール』第五章のジャン・ド・レリ論が執筆された時期にあたり、セルトーは「エクリチュールについて、友人〔おそらくジアールそのひと〕と密な対話を書面上や口頭で交わし」たとされ、当該のノートはその対話の一部である。ジアールはまた、最初のページの上方には以下の文言が詩のように付記されていたことも伝えている。« transhumance / on va, on va / on vient, on vient »(Ibid., p. 16).
-
[35]
Michel de Certeau, « L’éxpérience spirituelle », art. cit., p. 1-12.「霊的経験」においては、夜通し祈りをやめずに日の出を待ちつづけ、ようやく到来した陽の光の暖かさを掌に受けとめるといった「イメージ」が語られている(Ibid., p.3)。
-
[36]
Id., « Écritures », art. cit., p. 13. 強調は原文による。
-
[37]
Cf. Id., « Mystique » [1971], Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, éd. Luce Giard, Paris, Seuil/Gallimard, 2005, p. 328.
-
[38]
「窓」のイメージの背後には、スュランによる投身自殺未遂のエピソードが控えていると考えられる。ルーダンの悪魔憑き事件からボルドーへ帰還したのち、長い間「心身の麻痺状態」にあったスュランは、1645年5月、「修道院の一室から、ガロンヌ川をほど近くに臨む窓を突き破っての投身自殺を図っている」(渡辺優『ジャン゠ジョゼフ・スュラン—―一七世紀フランス神秘主義の光芒』慶應義塾大学出版会、2016年、22頁)。
-
[39]
« Écritures », art. cit., p. 13. 強調は原文による。
-
[40]
L’écriture de l’histoire, cit., p. 257.
-
[41]
« Écritures », art. cit., p. 14, 16.
-
[42]
« Du corps à l’écriture, un transit chrétien », art. cit., p. 305.
-
[43]
« Écritures », art. cit., p. 16.
-
[44]
« Du corps à l’écriture, un transit chrétien », art. cit., p. 305.
-
[45]
Michel de Certeau, « Écrire l’innommable », Traverses, no 1, Paris, Éditions de Minuit, septembre 1975, p. 9-15 ; L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, op. cit., p. 276-287[『日常的実践のポイエティーク』、432-450頁].
-
[46]
ibid., p. 276[同書、432頁].
-
[47]
Ibid[同上].
-
[48]
Ibid., p. 282[同書、441頁].
-
[49]
修正としては、いくかの文言の消去、段落の分割、代名詞から一般名詞への置き換え(« il »→« le mourant »、« elle »→« la mort »)、数箇所での時制の変化(複合過去→現在)、本文への註の移植、同義語への換言(« échec »→« raté »)、イタリックの解除、セクションのタイトルの変更など数多くあるが、全体の論旨に関わるほどの変更点はない。ただし、最終段落の「マラルメ以降……」の直前には、『日常的なものの創造』の全体をふまえて新しいセンテンスが挿入される(Ibid., p. 287[『日常的実践のポイエティーク』、449頁])。
-
[50]
Ibid., p. 281[『日常的実践のポイエティーク』、440頁].
-
[51]
Ibid.
-
[52]
Cf. La fable mystique I, XVIe-XVIIe siècle, op. cit., p. 243 ; L’écriture de l’histoire, op. cit., p. 411.
-
[53]
「かくして象徴は物の殺害として現れる。そしてこの死は、主体においてその欲望を永遠のものとする〔cette mort constitue dans le sujet l’éternisation de son désir〕。」Jacques Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » [1953], Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 319.
-
[54]
以下の鶴岡賀雄による指摘を参照のこと。「彼〔セルトー〕の徹底的歴史主義を、現在の知的境位として引き受けるならば、関わりの対象が――過去の他者であれ、絶対他者たる神であれ―—不在であることは、その現前の単なる欠如態(としての悪しき事態)としては考えられなくなるだろう。あるいは、当の対象との関わりのありようを捉える際に、その対象の現前と不在という仕方の区分は、少なくともその価値を、あるいは意味を、根本的に変えることとなるだろう。両者の区別がほとんど意味をもたなくなるほどに。」鶴岡賀雄「現前と不在―—ミシェル・ド・セルトーの神秘主義研究」『宗教哲学研究』第19号、2002年、26頁。
-
[55]
Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, présentation de Luce Giard, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1987, p. 92. Cf. Ibid., p. 90.
-
[56]
『日常的なものの創造』から、以下の一節を参照のこと。「読むこと、それは他所にいることである。彼らがいるのとは別の場所、別の世界にいることだ。[……]読者の場所は、ここかあそこ、この場所か別の場所か、ではなくて、ここでもなくあそこでもなく、同時に内部でもあれば外部でもあって、二つを一つにしながらいずれをも失う」(L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, op. cit., p. 250-252[『日常的実践のポイエティーク』、396-397、399頁]. 強調は原文による)。
この記事を引用する
福井有人「場所から非-場所へ──ミシェル・ド・セルトーにおける「書くこと」のモティーフ」『Phantastopia』第4号、2025年、1-19ページ、URL : https://phantastopia.com/4/from-place-to-non-place/。(2026年02月17日閲覧)