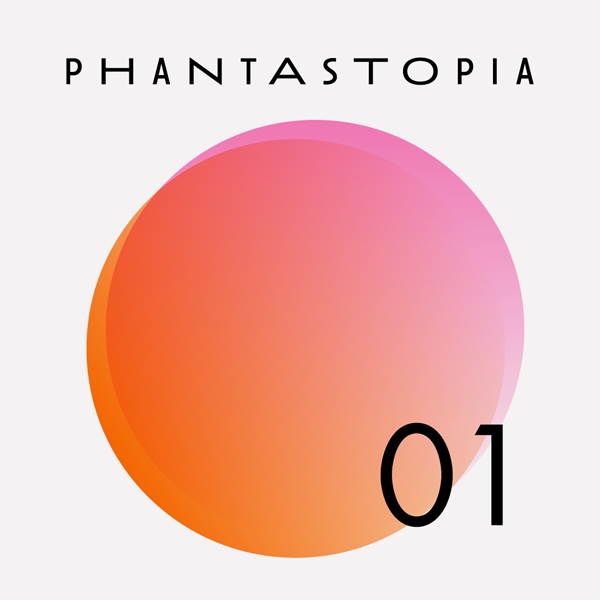本稿では、フランスの作家エリック・シュヴィヤール(Éric Chevillard)の2002年の作品『ハリネズミについて』(Du hérisson)を取り上げる。まるで学術書のようなこの書名[1]は、小説(roman)と銘打たれている作品の題としては風変わりな印象を与える。しかしその内容は、ある意味でタイトルの通りだ。作家として自叙伝の出版を構想していた語り手の「ぼく(je)」は、自室の仕事机の上に不意に現れた一匹のハリネズミのために、執筆に取りかかることができない。大切な仕事を妨害された語り手は、この動物に机のみならず思考まで占拠され、物語はハリネズミをめぐる取り留めのないモノローグへと突入することになる。
エリック・シュヴィヤールは1964年生まれの作家であり、23歳で発表した最初の小説作品『死ぬと風邪をひく』(Mourir m’enrhume, 1987)以降、その作品の大半を実験文学の拠点として知られるミニュイ社から刊行している。シュヴィヤールと同じく1980年代ごろから同社より作品を発表し、しばしば共に言及される作家として、ジャン・エシュノーズ(Jean Echenoz, 1947-)、ジャン゠フィリップ・トゥーサン(Jean-Philippe Toussaint, 1957-)、フランソワ・ボン(François Bon, 1953-)等がいる。シュヴィヤールを含めたこれらの作家は1950年代に同じくミニュイ社を中心にして起こった「ヌーヴォー・ロマン」の運動のあとで、その遺産を継承しながらふたたび小説を刷新しようとする世代として知られ、彼らがしばしば装飾的表現の排除や物語の最小化といった手法にうったえることから、「ミニマリズムの作家(écrivains minimalistes)」と称されることが多い[2]。
なかでもシュヴィヤールは、既存の文学形式をパロディ的に用いたり、動物や非人間を主要な登場人物に据えたりすることによって、ジャンルやコードをめぐる慣習を文学的な遊戯へ変えていく作風で知られる。いわゆる伝統的な自伝文学からはかけ離れたところにいる作家だが、自己を語るというテーマ、あるいは作者の問題はとりわけ2000年代ごろから現在に至るまで、シュヴィヤールの著述活動のなかで大きな位置を占める。たとえば本作品のほかにも、『トマ・ピラスターの遺稿』(L’œuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999)、『ニザール弾劾』(Démolir Nisard, 2006)『作者と私』(L’Auteur et moi, 2012)、『モノトビオ』(Monotobio, 2020)(以上すべてミニュイ社より刊行)等において、死後の著者、注釈者、伝記作家、自伝作家など、じつに多様な「作者」の表象を見いだすことができる。さらには2007年9月にインターネット上にブログ「オートフィクティフ(L’Autofictif)」を開設して以来、虚実入り交じる私的日記を17年以上にわたって綴りつづけていることでも知られる[3]。
2000年代初頭に発表された『ハリネズミについて』は、シュヴィヤールが『トマ・ピラスターの遺稿』(1999)で着手した作者の表象に関する探求を継続しつつ、「自伝」というテーマにはじめて取り組んだ作品だといえる。物語の展開がほとんどなく、時空間の飛躍もいっさいないこの小説の筋書きを説明するには、冒頭付近の以下のような一節でじゅうぶんである。
せっかく自分のことに興味をもっているのだ。今回こそはより内密なしかたで執筆し、個人的な思い出を呼び起こすつもりだったのに、[…]一匹の無邪気でつぶらなハリネズミが、胸をひきさくようなぼくの自伝的告白を邪魔しにやってくるではないか(voici qu’un hérisson naïf et globuleux vient parasiter ma confession autobiographique déchirante)。[4] (H, 13-14)
作家の自叙伝執筆の計画は、「無邪気でつぶらな(naïf et globuleux)」(と常に形容される)ハリネズミの到来によっていともたやすく頓挫してしまう。取り組むべき仕事を失った語り手の意識は当て所なくさまよいはじめ、ミニマルな物語は奇妙な言葉の渦と化していく。ハリネズミによる妨害さえなければ自伝に書くつもりだったという子供時代の思い出、売れない作家であるみずからの現状の憂慮、ハリネズミの観察、そこから想起される類似の動植物やオブジェ、さらにはハリネズミにまつわるビュフォンやシェイクスピアの著作からの引用など、さまざまな思考や空想、記憶が繰り広げられるが、ひとつひとつの話題はけっして完結せず、つねに連想や言葉遊び、あるいは語り手の注意散漫によって別の話題へと逸脱する。物語的・言語的秩序の乱れを反映するかのように、テクストは話の脈絡や構文にかかわらず無造作に断ち切られ、そうして作られたパラグラフごとに約二行分の空白が挿入される。そして各パラグラフにおいて必ず一度以上は「無邪気でつぶらなハリネズミ」が登場するのである。
参照的な重みをもたず、言葉の端がひらりとめくれあがるようにして読む者の想定を逃れていくこの作品には、散文詩のような愉しさがある。しかしあまりにつかみどころのないハリネズミの存在と、目的地の見いだせない執拗な脱線は次第に読者を迷わせ、批評を行き詰まらせてしまう。ハリネズミはいったいなにを意味し、物語はどこへ向かっているのだろうか。
*
夜行性で草の根、果実、虫などを雑食し、危険を感じると直ちに背中に密生した棘を逆立て、栗のいがのように丸くなり天敵から身を守る臆病な小動物。本作品においてハリネズミは、反自伝的な形象であり、語り手が対峙しなければならない他者であり、しかし同時に自分の世界に閉じこもる傾向のある作家自身の鏡像でもある。そしてこの動物は作家の憎しみと殺意、親しみと共感を受け止めるいっぽうで、純粋な好奇心の対象ともなり、さらには単なる比較やアレゴリーの一端を引き受けることもできる。このようにあらゆる意味づけをすり抜け、机の上と作者の頭の中の、物理的脅威と心理的な鎧の、意味と無意味のあいだを行き来する「無邪気でつぶらなハリネズミ」は、「無邪気でつぶら」であるということ以外にいかなる固定的な性質ももたないからこそ、作品中のすべてのパラグラフに登場することができるのだ。
しかし元はと言えば、それは作家の机上に現れた小さな物理的存在にすぎないはずである。棘に覆われているとはいえ、手のひらほどの大きさの動物をいつまでも追い払うことができず(あるいは作家のほうがその場を離れてもよさそうなのに)、思考の隅々まで支配されてしまうのはなぜなのか。ハリネズミのこの恐るべき侵襲性の背景には、この動物そのものに備わった意味や象徴性よりも、シュヴィヤールがインタビューの中で明かしているような、主体と言語の関係性についての見方のほうが大きくかかわっていると思われる。
私の文章はしばしば脱線的な性格をもっているため、どこから、あるいは誰から発せられたものなのか、すぐにわからなくなってしまいます。[…]作者は多くの場合、囮(leurres)あるいは藁人形(hommes de paille)であり、いってみれば、自分が制御しているはずの言葉によって四方八方から圧倒されているのです。[5]
たとえば以下の箇所は、語り手が自伝を妨害するハリネズミを殺すことで言語活動の主導権を取り戻そうとするが、いわば言葉のほうが作家を翻弄し、彼に殺害を思いとどまらせるに至る場面である。
ぼくは自分の中に殺意が再び湧き上がってくるのを感じる。めいっぱい腕を伸ばして辞書を高々と持ち上げ、無邪気でつぶらなハリネズミの上に、残酷にも叩きつけるのだ。辞書のほうも、ハリネズミとの接触から無傷では帰ってこられない。穴だらけになって、その哀れな状態を記述するための言葉がひどく不足することになるだろう。(H, 82)
語り手がハリネズミの上に叩きつけようとした凶器としての辞書は、かりにハリネズミの棘が刺さって穴だらけになったとしても、そこに載っている言葉そのものが失われるはずはない。しかし文字通りの意味と比喩的な意味は一瞬にして入れ替わり、辞書は作家の語彙を表す象徴的なオブジェに、そこに開けられた穴は言語の喪失のメタファーに転じることで彼を躊躇させ、その企みを不条理にも断念させるのである。
あるいはこんな場面もある。
ぼくは皆と同じように、スーザンが好きだった。彼女はブロンドの髪と青色の目をしていたので、風の強い日には、つむじ風の中で彼女は、色の混合の結果として緑色になるはずだった。ぼくは試してみたが、青に黄を混ぜると緑色になる。紙の上ではうまくいっていたのだ(ça marchait sur le papier)。ところでぼくは、つねに紙の上にあるものを信じたかった。今でもそうだ、この無邪気でつぶらなハリネズミも例外ではない。どうしてその存在を疑うことができるだろうか?紙の上に成り立つものだけが、ぼくにとって常に唯一の現実を構成してきた。作家というのは紙の上を歩むものなのだ(Ce qui marche sur le papier a toujours constitué pour moi la seule réalité. L’écrivain marche sur le papier)。(H, 62-63)
語り手は現実から目を背け、「紙の上」、つまり言語やイメージの世界の中で生きていくことを望んでいる。ところが « marcher sur le papier » という表現がいつの間にか文字通りの意味へ横滑りしていて、作家は原稿用紙の上に居座って執筆を妨害する「ハリネズミ」の存在をあっさりと承認してしまう。そして何ごともなかったかのように、「紙の上」という語はもとの比喩的な意味へと戻り、言語の揺らぎ[6]を突いて不意に侵入したハリネズミを含みこんだまま、作家の語りは続いていくのである。
*
このように言葉の意味をうまく制御することができず、その多義性に翻弄されてしまっているこの語り手は、自伝の執筆どころか、健全な思考と認識すらおぼつかない人物としてわたしたちに提示されている。こうした「作者」の描かれ方は、自伝文学の復権が叫ばれる1970年代後半以降、これまで自伝や伝記というジャンルからはかけ離れたところにいた多くの作家が、みずからの不統一な自己から出発し、さまざまな方法で「傷ついたコギト」を癒しながら、「私」のイメージが獲得される過程を記述しようとしてきた流れのなかではやや異質なものと見えるかもしれない。ブリュノ・ブランクマンが指摘するように、「オートフィクション」をはじめとして今日までつづく「自己のエクリチュール」の流行に対して、シュヴィヤールの本作品は「作者」という観念に対して改めて鋭いまなざしを向けているといえるだろう[7]。
それでも、シュヴィヤールの意図は自伝を書くことの欺瞞や困難あるいは不可能性について繰り返されてきた言説に単に回帰することではないはずだ。たとえば次のような箇所を見てみよう。
周知のとおり、ぼくの差し迫った企図は、生まれてから死ぬまでの人生を語ることにある(自伝作家というのは概して意気地なしで、その仕事を全うすることができない――ぼくは最後までやり遂げよう)。この計画においては、ぼくの記憶よりも消しゴムの方が役に立つだろう。(H, 54)
ここではルイ・マランが指摘したような自伝文学をめぐる伝統的なアポリア、つまり自伝は「「私は生まれた」と「私は死んだ」というふたつの本来的に言われることのありえない言表によってしか始まることも終わることもでき」[8] ないという命題が提示されている。しかし自己表象における始点と終点の欠落というこの難題は、ここで「消しゴム」がその領分を超えて乱入してくることによって、作家によって正面から取り組まれることなく、頓知のような奇妙な理屈で片付けられようとしているのである。こうした傾向は作品全体に通底しており、たとえば語り手が「ぼくのつらい秘密(mon douloureux secret)」と呼ぶ自身のトラウマ的出来事を記述するとき、あるいは自己認識の根本的な不可能性に語り手が直面したときでさえ、こうした自伝文学の諸困難は、言葉遊びによって――あるいはハリネズミの侵入によって――次々といわば骨抜きにされてしまうのである。
もちろん、自伝文学はそれを書くことの困難とともに発展してきたのであり、それを無効化するという身振りが、果たして自伝を擁護しているのか批判しているのか、あるいはどちらでもないのか、というのは区別しがたい問題である。いずれにせよシュヴィヤールは、自伝というジャンルに対するシニカルなスタンスを保ちながらも、たんに読者をあざむく不誠実な存在として作者の「私」を描くのでもなければ、アラン・ロブ゠グリエやロラン・バルトがしたようにそれを断片化、あるいは三人称化することによって遠ざけようとするのでもない。シュヴィヤールの場合はむしろ、「私」というものに敢然として接近していっているように思われるのだ。そしてそれは、伝統的な自伝文学が描いてきたような自由で透明な「私」ではなく、心理的・存在論的な深さをうばわれて書斎に閉じ込められ、明らかに矛盾した言葉をハリネズミのまわりに張り巡らせつづける、混乱と欠損にみちた「私」である。シュヴィヤールはハリネズミが自伝を妨害する、というきわめてシンプルな舞台設定から出発しながらも、それを単なる反自伝的な形象に固定することはない。まるでこの動物自身がそうした還元を拒んでいるかのように、それはあらゆる意味づけをすり抜けながらも、作家の机上とその独白のなかに不条理にも位置を占め続ける――このハリネズミと自伝作家の奇妙な競演からシュヴィヤールが描き出しているのは、言葉との抜き差しならない関係の中で立ち上がってくる、不確かであれ豊かな「私」のあり方であるといえるのではないだろうか。
参考文献
Bruno Blanckeman, « « L’écrivain marche sur le papier ». Une étude du Hérisson », Roman 20-50, vol. 46, no. 2, 2008, p. 67-76.
Éric Chevillard, Du hérisson, Éditions de Minuit, 2002.
Anne Cousseau, « Lecture, jeu et autobiographie dans Du hérisson d’Éric Chevillard ». Romanciers minimalistes 1979-2003, édité par Marc Dambre et Bruno Blanckeman, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012, p. 231-243.
Louis Marin, La voix excommuniée Essais de mémoire, Éditions Galilée, 1981. (ルイ・マラン『声の回復 回想の試み』梶野吉郎訳、法政大学出版局、1989年。)
Pascal Riendeau, « « Des leurres ou des hommes de paille ». Entretien avec Éric Chevillard », Roman 20-50, vol. 46, no. 2, 2008, p. 11-22.
David Ruffel, « Les romans d’Éric Chevillard sont très utiles ». Romanciers minimalistes 1979-2003, édité par Marc Dambre et Bruno Blanckeman, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012, p. 27-32.
Notes
-
[1]
前置詞de(定冠詞leと縮約しduになっている)はここでは英語のonにあたり主題を提示する。アンヌ・クソーは『ハリネズミについて』のタイトルにおけるこの前置詞の用法について、「古風であると同時に学問的な含みをもち、読者を科学的エッセーないし論文を読むことへと導いているように思われる」と述べている。Anne Cousseau, « Lecture, jeu et autobiographie dans Du hérisson d’Éric Chevillard ». Romanciers minimalistes 1979-2003, édité par Marc Dambre et Bruno Blanckeman, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012, p. 232.
-
[2]
「ミニマリスト」という分類が正確でないとする指摘も多く、註1で挙げたミニマリストと呼ばれる作家についての論集では、多くの著者がこの用語の使用に関して留保を表明している。同じ論集のなかでダヴィッド・リュフェールはこの呼称の位置づけを整理し、それがその世代の作家たちがみずからもっていた共通認識ではないとしたうえで、「このミニマリズムをもっとも正確に規定しているのは、数人の作家と編集者ジェローム・ランドン(Jérôme Lindon)が共有した欲望である。何人かのほかの作家たち(たとえばピエール・ミション(Pierre Michon))が明確にミニュイ社と決別していた当時[1980年代]、彼らは1950年代にミニュイ社を中心に発明された美学を刷新しようとしたのである」と述べる。David Ruffel, « Les romans d’Éric Chevillard sont très utiles ». Romanciers minimalistes 1979-2003, édité par Marc Dambre et Bruno Blanckeman, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012, p. 27.
-
[3]
https://autofictif.blogspot.com/参照。夏期の数週間を除いてほぼ毎日更新され、ひとつの投稿は三つの断片からなる。なお、毎年1月に前年分の全記事がL’Arbre vengeur社より刊行されている。
-
[4]
引用はÉric Chevillard, Du hérisson, Éditions de Minuit, 2002. より、以降頁数を括弧内に略号Hとともに示す。
-
[5]
Pascal Riendeau, « « Des leurres ou des hommes de paille ». Entretien avec Éric Chevillard », Roman 20-50, vol. 46, no. 2, 2008, p. 11.
-
[6]
シュヴィヤールにおけるこうした独特のアンタナクラシス(同語異義復言法:一つの文(節)のなかで同じ語を違った意味で使い分けること)にかんする包括的な分析については、今後の課題としたい。
-
[7]
Bruno Blanckeman, « « L’écrivain marche sur le papier ». Une étude du Hérisson», Roman 20-50, vol. 46, no. 2, 2008, p. 74.
-
[8]
Louis Marin, La voix excommuniée Essais de mémoire, Éditions Galilée, 1981, p. 42. (ルイ・マラン『声の回復 回想の試み』梶野吉郎訳、法政大学出版局、1989年、41頁。)
この記事を引用する
稲田紘子「ハリネズミと自伝作家」『Phantastopia』第4号、2025年、60-66ページ、URL : https://phantastopia.com/4/du-herisson-chevillard/。(2026年02月27日閲覧)