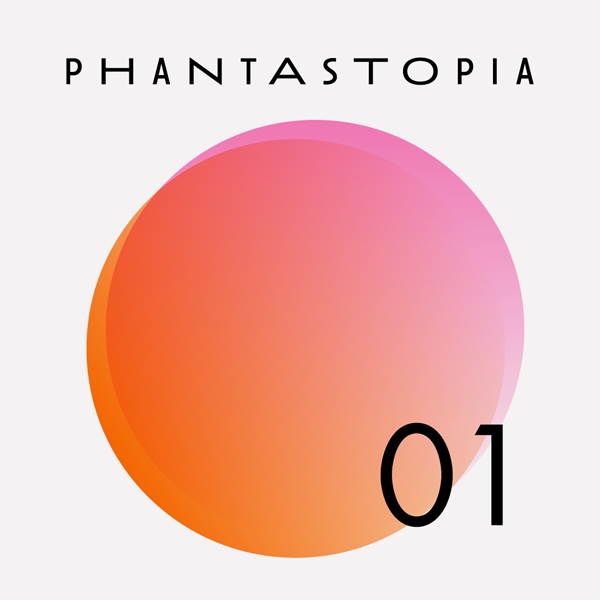2024年9月23日18時、ギーセン大学応用演劇学科からの留学生アリサ・ミュラーとタッグを組み、三鷹にある雑居ビル5階のスペースSCOOLにて[a]gainを上演した。ここに記すことはあくまでもわたしの視点にすぎないが、上演は概ねこのように進行したと記憶している。
***
![[a]lisa, [a]gain, SCOOL (Tokyo), 2024. Photo: Nanami Furut](https://phantastopia.com/wp/wp-content/uploads/2025/03/1Ausstellung3-1200x659.jpg)
[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta
来場者は受付にてアリサ・ミュラーと加藤理沙からドイツ語で、入場料は2,000円であること、壁に立てかけてある椅子を自由に取ってどこにでも座っていいこと、中で展示が行われていることを告げられる。来場者はなんとか入場料の支払いに成功すると部屋に入ることを許可される。ホワイトキューブの部屋の中には絵本やぬいぐるみ、洗濯かご、ヘアアイロンなどアリサと理沙の私物が床一面に並べられており、それぞれに日本語、英語、ドイツ語の3か国語で私物にまつわる私的なエピソードの記されたキャプションが付いている。その合間をカラフルなプラスチック製のおもちゃの列車が安っぽい音楽を大きな音で繰り返し奏でながら自由に走り回っている。部屋の奥には白いロール紙が天井から吊るされ床まで伸びている。部屋の手前側には折り畳まれた椅子がいくつか壁に立てかけられており、そのことに気付いた一部の来場者は椅子を手に取り、好きな場所に置いて座る。部屋の左右の壁にはアリサと理沙が自室にて事前に撮影した2人の睡眠中の映像が高明度で投影されている。中央には白いテーブルが置かれ、その上には二膳の白い箸と透明な容器に入った焼きじゃがいもが置かれている。中央上方には白い靴下と濡れた白い雑巾が白いピンチハンガーで吊るされている。

[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta

[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta

[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta

[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta
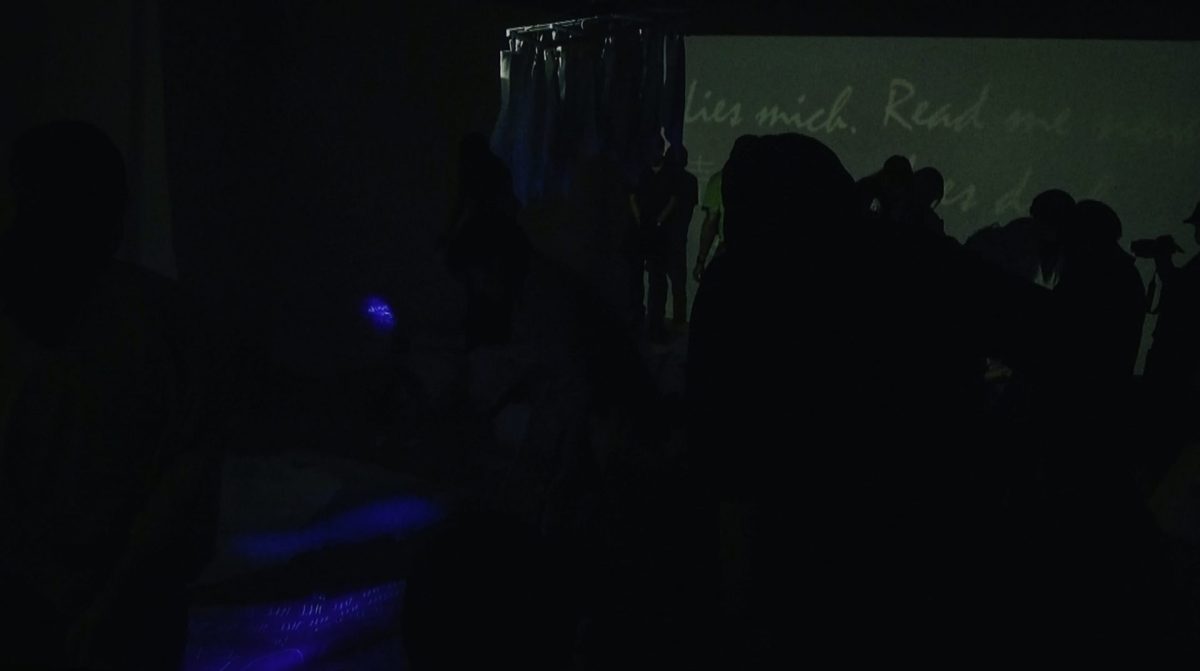
[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta

[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta

[a]lisa, [a]gain,
SCOOL (Tokyo), 2024.
Photo: Nanami Furuta
アリサはひょっとしたらまったく違うところから構想をはじめたかもしれないが、そしてこのように前置きできるところが共同制作の美しさなのだが、わたしは生を持つものがまるで物であるかのように扱われるときや、反対に物が語りかけてくるように感じられるときはいかにして生じるのか、という問いを出発点に制作をはじめていた。本上演の最初の演者はわたしたちの私物、そしてその合間を縫うようにして走るおもちゃの列車であり、次いでアリサと理沙、つまり出演者としてクレジットされた身体であり、最終的には来場者の身体となる。このような物から観客にいたるまでの演者の変遷は、誰が舞台に立つに値するのか、誰が注目に値するのか、誰が「いま、ここ」に生じる状況を変えられるのかという問いへの応答を、従来の演劇であれば見逃されていた物や観客にまで広げるという、演劇という形式を問うような関心と実験に基づいていた。
指先の動きひとつで全世界へと到達するように感じられるスクリーンの誘惑と戦いながらアイデンティティを形成してきた世代であるわたしたちは、感染症や戦争、分断や自然災害によって増えゆく2020年代前半の世界の悲しみの総量に対して、創作によっていかにして応答できるのかを考えることに、創作プロセスにおいて長い時間を費やした。お互いに異なる母語や文化的背景を持つわたしたちには、幸か不幸かそもそも見てきた演劇シーンがまったく違っていたために、上演の完成形に関する暗黙の了解事項がなかったのだが、捨てる意図もなく捨てるに至ったのは観客と俳優との間にへだたる「第四の壁」である。19世紀に照明技術によっても推進された「第四の壁」という概念は、舞台上の俳優たちが、まるで舞台と観客席との間に見えない壁が存在するかのように振る舞うべきだとする発想である。同時に観客の遅刻やおしゃべりなどの不規則行動は取り締まられることとなり、観客の身体は照明を落とされた暗闇のなかに据えられた。そのようにして分厚い壁によって隔てられた見られる者と見る者は、メディア社会に置き換えるのであれば、画面の向こうにありありと映し出され流れていく出来事が、とりわけ大惨事が、あたかも画面のこちら側の主体には介入する余地のない客体であるかのように提示され、錯覚されるさまに似ている[1]。そのようなメディア社会を背景に、上演の「仕掛け人」と上演への「来場者」が同じ時空間に集うことによってはじめて成り立つ上演芸術の特徴をひとつあげるとするならば、それはライブで出来事が生じるということである[2]。[a]gainの試みは、ドイツの演劇学者ハンス=ティース・レーマンが、メディア社会の到来以降、観客という問いが演劇人たちの主要な関心事となったと述べた[3]ことと呼応していた。目の前で生じた出来事に対し「来場者」はいかに反応するか、そしてその反応がいかにして状況を動かし変形させるのか、だれが積極的に状況にかかわり合って変化を起こす起点となり、だれが「観客」にとどまりそれを外から観察するのか、という挑戦を、[a]gainは来場者に突き付けていた。
上演の仕掛け人が来場者に何らかの指示を与え、来場者がその指示通りに動くことによってはじめて上演が成り立つような、現代演劇に見られる観客参加型のイマーシブ・シアターの実践と異なり、[a]gainにおいて特徴的だったのは、来場者が仕掛け人からの指示に応えることも、応えないでいることもできるということであった。そのような状況においてわたしが上演の仕掛け人およびクレジットされた出演者として上演中に楽しんでいたのは、来場者のだれが積極的に状況の内に飛び込み、演技、劇、遊び(Spiel)にかかわり合い、だれが観客として状況の外から観察することに専念するかを、上演の仕掛け人であることによって特等席で観察することができた、ということである。上演中にわたしが楽しんでいたのは来場者の反応であり、上演中に交わされる来場者との会話、リアルタイムで発される感想の盗み聞き、来場者の佇まい、また他の来場者の行為に触発された来場者の行為であった。つまり観客(来場者)は、クレジットされた演者(わたし)を見ているということと同じかそれ以上に、実は演者(わたし)からの視線から逃れなかったのである。わたしは演者であると同時に観客でもあったし、来場者は観客であると同時に演者でもあった。観客として状況の外にとどまることに決めた来場者も、わたしにとっては積極的な参加者となった来場者と同じように意味を持った。それは自ら企画したものを発表するという側面以上に、ひとりひとりに会えていい日だった、という思い出をわたしに残していった。
註

[a]gain
共同主催・企画制作・出演:[a]lisa(Alica Müller 加藤理沙):[a]lisa(Alica Müller 加藤理沙)
音響・照明:近藤侑羽 映像・字幕:西山珠生
記録撮影:古田七海 宣伝美術:ポーラは嘘をついた
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[スタートアップ助成]