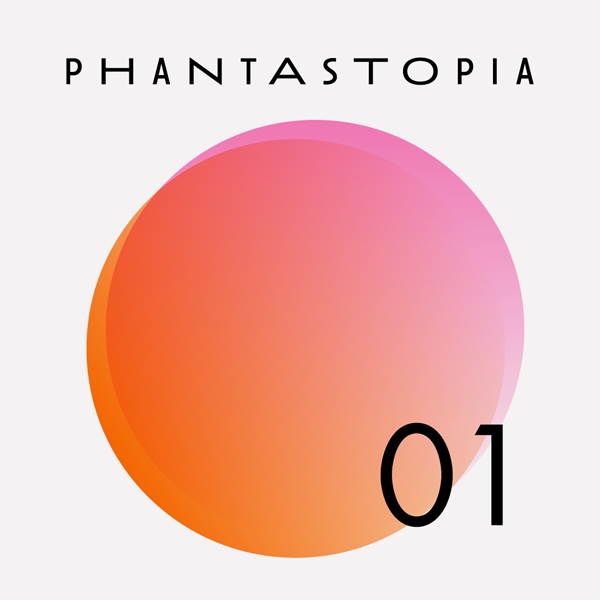このたび『Phantastopia(パンタストピア)』第4号を公開する運びとなりました。『Phantastopia』は、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コースに所属する修士課程・博士課程の大学院生が主体となって運営するWebジャーナルです。2021年度に創刊された本ジャーナルも、気づけば4号を迎え、いわゆる三号雑誌になることなく存続できたことは、誠に喜ばしい限りです。
第4号では、2本の「論文」を掲載しています。「論文」は、本コースの教員による厳正な査読プロセスを経ており、4本の「研究ノート」と共に、表象文化論コースの大学院生による最新の研究成果を伝えるものです。また、「ブックレビュー」3本を掲載しました。いずれも、院生による、各分野の専門的知見に基づいた解説が行われており、未邦訳文献を紹介する貴重な資料となるでしょう。
コース学生による活動に焦点を当てた「レポート」記事を2本公開しました。1本目は、本コース院生の加藤理沙さん、ギーセン大学応用演劇学科のアリサ・ミュラーさんによる演劇、「[a]gain」の記録です。レポートには、出演者の視点から企画、上演がどのように進行したかが記録され、読み応えのあるものになっています。2本目は、東京大学本郷キャンパス情報学環オープンスタジオ中山未来ファクトリーで行われた展示「イマーシブ・メディアの現在 vol.1———白昼落下 Sleepwalk/Downfall」の記録です。本コース院生の原田遠さん、東京藝術大学の荒川弘憲、山下紗弥さんによる企画、作品が記録されているだけでなく、本コース学生も多数登壇した複数回のトークイベントの要約、2月13日に行われた比較文学比較文化コース准教授の松井裕美先生を招待したトークの記録が掲載され、研究と実践が大学の中で結びつく様子が記事のなかで克明に浮かび上がっています。
両レポートは、コース内に留まらない交流に基づいた制作、実践を記録しており、院生間の対話、議論の“場”となるようにという思いから、場所を意味する接尾辞「-topia」が名前に付けられた当ジャーナルにとって、両記事を掲載することには大きな意義があります。交流の場として大学が機能することが、研究や実践にどのような成果を生み出すかを、両記事は示しています。
2024年は、振り返れば、院生の間で、そうした交流の場としてのコース、大学の役割が見出された年でした。6月には授業料値上げに関連して集会やアンケートが大学内で行われ、本コースで行われた所属学生投票の結果は、実行委員会の依頼により、本ジャーナルに掲載されました。こうした出来事を期に、自治会組織の形成が進められ、1月には、東京大学大学院表象文化論コース学生生活・研究協議会(表象学生会)が発足しました。こうした状況の下で、今までにないほどに学生間の交流が活発化したことは、本コース所属の大学院生が互いに交流しながら、知のダイナミズムを創出する「場」となるという目標を掲げてきた本ジャーナルとしては、こうした動きが、学術的な議論の場としての本コース、そして、本ジャーナルにさらなる活力を与えてくれることを期待しています。
本ジャーナル第4号の編集、刊行にあたり、多くの方の力添えをいただきました。
とりわけWebサイトの制作をご担当いただいているBOSCO小林雅人さんには、本号でも、様々な作業に関して、迅速かつ丁寧にご対応してくださり、心より感謝を申し上げます。
表象文化論研究室の先生方、スタッフのみなさまには、投稿論文の査読をはじめとして全面的なご協力をいただいています。とりわけ担当教員の桑田光平先生には、多大なご助力をいただきました。誠にありがとうございます。コース内での連絡、「研究のトポス」の連載に関して、度々お力添えを頂いた教務補佐員の谷口奈々恵さん、そして、論文等の投稿やレポート記事の執筆をしていただいたコースの院生のみなさんにも、深くお礼申し上げます。
『Phantastopia』第4号編集委員会
安倍拓真、鈴木紗和、陰山涼、
趙婭冰、浜渦理起(編集後記文責)