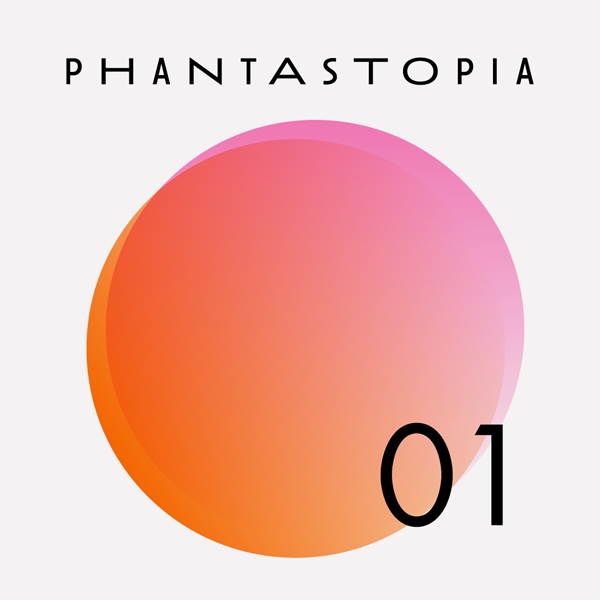はじめに
はっぴいえんどが1971年に発表したアルバム『風街ろまん』の一曲目「抱きしめたい」、そのイントロには奇妙な仕掛けが施されている。アコースティックギターとベースが頭から始まり、一拍あとからドラムが入ってきてこの三つのパートで演奏されるイントロだが、リズムがどこかでずれているようにして進んでいき、「淡い光が」と歌が始まるとリズムはすっかり揃っている。本稿では、この「抱きしめたい」のイントロ部分がどのような構成になっているのかを分析することから出発し、1962年に発表されて日本でも大ヒットとなった同名異曲、ビートルズの「抱きしめたい」などを参照しながら、日本のポピュラー音楽史におけるはっぴいえんどの位置づけについても検討する。
1. はっぴいえんど「抱きしめたい」のイントロ
松本隆作詞、大瀧詠一作曲の「抱きしめたい」だが、イントロのリズムアレンジは大瀧の発案により始まったという[1]。このイントロが工夫を凝らされたもので、各パートのリズムがずれて聞こえるものであるという指摘は多くされているが、ここで組み合わされているリズムパターンについて具体的に記述しているものはあまり見られない。各パートがどのようなパターンを刻んで演奏しているのかを分析することで、このイントロの構造を探っていきたい。
およそ14秒のイントロ部は、4分の4拍子で4小節+1拍の17拍から成っており、このはみ出た一拍の置き方こそがイントロの奇妙なずれを感じさせる大きな要因となっている。各パートの演奏を、ドラム、ベース、ギターの順で分析していく。
松本が演奏しているドラムのパートは、演奏の始まりがベースとギターに対して1拍遅れている。その後は、8分でハイハットを刻みながら頭の2つでバスドラムを鳴らし、3つ目にスネアが来て4つ目はハイハットのみという、2拍分の長さからなる(8分音符4つを単位とした)パターンが繰り返される。この「ズン ズン タン ツッ」というパターンが計8回登場し、頭の1拍を休んでいるためこれでちょうど1+2×8で17拍のイントロとなる。細かくは、パターンの頭が符点のドラムとなったり、イントロ最後のパターンはやや異なっていたりするが、基本の形として頭に1拍休みがあって、そのあとに4分の4拍子に収まるパターンが繰り返されていることが確認できる。
このドラムに対して、細野晴臣が演奏しているベースのパートは、冒頭から演奏が始まる。大まかにいうと、基本のパターンは8分の1つ目にA(ラ)の音を鳴らし、次の2つで1オクターブ低いAの音を鳴らし、4つ目は休むという2拍分の長さのパターンであるといえる。頭で音をスライドさせたり、時折16分の入ったパターンが登場したりもするが、基本は「ドウィー ドゥッ ドゥー」のパターンであり、それを8回繰り返して最後の1拍では音階が上昇する異なる動きとなる。こうしてベースも2×8+1で17拍のイントロとなっている。ドラムもベースも、2拍分の長さのパターンを8回繰り返す点では同じ(16拍分)だが、そのパターンからはみ出る1拍が置かれている場所が異なっているといえる。ドラムは頭の1拍を休むことでパターンからはみでる1拍となっていたが、ベースは頭からパターンを繰り返し、イントロの最後の1拍がイレギュラーな動きとなっている。「抱きしめたい」のイントロは、この1拍の置き方のずれが奇妙なリズムを生じさせる大きな要因となっている。
そして最後に、大瀧が演奏するギターのパターンを分析する。このギターは、ベースと揃って頭から演奏を始めているため、ベースと同じようにして拍を取りたくなってしまうが、見通しのよいパターンを取り出すには、ベースと異なり冒頭の1拍がパターンからはみ出た拍だと捉える必要があるだろう。ギターもまた8分のリズムを基本にした演奏をしているが、冒頭の1拍にあたる「ズン チャン」を切り離し、それ以降をパターンとして捉えると、「ズン チャン ズン チャン ズン チャッチャーン」(パターンa)という4拍からなるパターンが2回繰り返され、そこから「ズン ズン チャン ズン チャン ズン チャッチャーン」(パターンb)という4拍からなるがやや異なるパターンが2回繰り返されている、とおよそ捉えることができる。前半のパターンaでは低音のAを拍の表で鳴らし(上で「ズン」と表記した部分)、拍の裏で和音を動かす(「チャン」と表記した部分)ようにして、三拍目の裏で和音を鳴らした後に四拍目の表で和音を鳴らして伸ばすという構成だと大まかに捉えられる。それを2回繰り返した後はパターンbのようになり、パターンaの拍の表と裏をひっくり返したようなパターンが演奏される。低音Aを1拍目の表と裏で2回鳴らし(ここで2回鳴らすことで以降の表裏がひっくり返る)、2拍目と3拍目は表で和音、裏で低音が鳴らされ、四拍目の表から「チャッチャーン」と和音が入る。このギターのパートもまた、細かく言えば異なる鳴らし方をしている箇所もあるが、パターンの概形としては以上のように捉えることができるだろう。すなわち、最初に1拍「ズン チャン」が入るが、その後は4拍のパターンaを2回、4拍のパターンbを2回繰り返すことで、1+4×2+4×2で計17拍のイントロとなっている。
以上のことから、イントロの構成を整理してみたい。3つのパートの演奏からなっている「抱きしめたい」のイントロは、ドラム、ベース、ギターそれぞれ単体では決して複雑ではないパターンを繰り返すことを基本にしている。しかし、17拍(4分の4拍子で4小節と1拍)からなるイントロでは、パターンの繰り返しとなる16拍の他に1拍はみ出すことになる。そしてこのはみ出す1拍が、ドラムとギターは冒頭の1拍、ベースはイントロ最後の1拍に置かれていることにより、リズムのずれを引き起こしているといえるだろう。さらに、演奏の始まり方としてはギターとベースが揃って始まりドラムだけが1拍遅れて入るため、パターンの繰り返しで各パートを捉えたときの拍のずれは、演奏開始部分のずれともずれている。さらにギターは途中でパターンが少し変わり、表と裏がひっくり返るようになるため、そこでもずれたような感覚を生じさせる。こうしてはっぴいえんどの「抱きしめたい」のイントロは、決して複雑ではないパターンの、その組み合わせを凝ることによってリズムが奇妙なアレンジとなっている。
2. はっぴいえんどとビートルズ
「抱きしめたい」というタイトルの曲といえば、ビートルズの曲が最も有名だろう。「アイ・ウォント・トゥー・ホールド・ユア・ハンド(I Want to Hold Your Hand)」は1963年11月にイギリス、12月にアメリカと順にシングル盤が発売され、アメリカではビートルズの初の大ヒット曲となる。1964年2月に日本で最初に発売されたビートルズのレコードがこの曲で、そのときに邦題が「抱きしめたい」となった[2]。このビートルズの「抱きしめたい」とはっぴいえんどの「抱きしめたい」に直接の影響関係があるかは明らかではないが、ビートルズの「抱きしめたい」から約7年後、はっぴいえんどの松本が「抱きしめたい」というタイトルの詞をつけたとき(歌詞の中には「抱きしめたい」のフレーズは登場せず、内容的にもこのタイトルである必然性はあまり感じられない)、そしてその曲をバンドとして演奏するとなったときに、ビートルズの同名異曲が一切念頭になかったとは考え難い[3]。
ビートルズの「抱きしめたい」もまた、イントロに仕掛けが施された曲である。この曲は裏拍から演奏が始まっており、初めて聴く場合などは特に、聴き手はイントロで拍の裏表を間違える可能性が高い。そして「オーイェーアーイ」と歌が始まるあたりでは拍の表の場所がはっきりする。これもまた、イントロのリズムがずれているように感じさせる仕掛けの一つといえるが、その内容ははっぴいえんどの場合とは性質が異なっている。裏拍と思わせておいたほうが実際は表拍だった、というように聴き手に対してリズムの乗り方をミスリードするようなビートルズの「抱きしめたい」に対し、はっぴいえんどの場合は演奏が表拍から始まり、裏表の拍のミスリードはない。
しかし、残されているはっぴいえんどのライブ演奏の音源を聴くと、「抱きしめたい」の演奏開始時に、『風街ろまん』のバージョンには聴かれない要素をさらに見出すことができる[4]。イントロの構成自体は『風街ろまん』のバージョンと殆ど同一であるが、その演奏を開始する直前、ドラマーの松本がカウントを取る。すると、細野のベースと大瀧のギターは松本のカウントの裏から演奏を始めてしまう。そしてそこから1拍後からドラムの演奏が入るのだが、この演奏を裏拍から始めることははっぴいえんどの「抱きしめたい」において必然性がないといえる。ビートルズが「抱きしめたい」をライブ演奏するとき[5]、ドラムのカウントの裏から入るのは必然性があり妥当な入り方であるが、それに対しはっぴいえんどが「抱きしめたい」の演奏をドラムのカウントの裏から始めることは、演奏を揃えるという目的に限ってみれば必然性のない振る舞いとみなせるだろう。ただ、これによってはっぴいえんどは、「抱きしめたい」のイントロにさらにリズムがずれて聞こえるような要素を加えていたと考えられるとともに、この仕掛けにはビートルズの「抱きしめたい」への目配せもまた感じられる。
はっぴいえんどが解散して数十年が経った後、雑誌のインタビューなどでメンバー自身が当時を振り返って語っているものは多く存在している。バッファロー・スプリングフィールドやモビー・グレープなどアメリカ西海岸のロックバンドを手本にしていたことは、メンバー自身が度々公言しているが[6]、特に大瀧は、自身が作曲したはっぴいえんどの曲について、その参照先のミュージシャンや楽曲について具体的に語る場合がある。「抱きしめたい」のイントロに関しては、イントロで拍をずらしている曲としてキンクスの「セット・ミー・フリー」[7]、「ユー・リアリー・ガット・ミー」[8]などを引き合いに出して言及している。これらのキンクスの曲も、ビートルズの「抱きしめたい」のイントロと同様で、聴き手に拍の裏表をミスリードさせる系統の曲であり、はっぴいえんどの「抱きしめたい」のイントロとは性格が異なっている。これまで挙げたビートルズやキンクスの曲では、聴き手に拍の裏表をミスリードさせるがその拍のずらし方は演奏者たちの間では揃えているものだといえる。これに対し『風街ろまん』の「抱きしめたい」は、1拍はみ出た構成ではあるが拍の裏表を混乱させるのではなく、聴き手がリズムに乗ることは決して難しくはない。キンクスなどの曲は、何気なく聴いていると拍の表裏が分からず混乱する感覚を覚えることがあるが、はっぴいえんどの場合は何気なく聴き流していても拍の裏表で混乱してリズムが分からなくなる可能性はほぼない。はっぴいえんどの場合は寧ろ、各パートの拍がずれているため、演奏者たちが合わせることが難しいといえる。このようにキンクスの場合とはっぴいえんどの場合とでずらし方が異なることは大瀧自身も言及しているが[9]、ここで妙なのは、ビートルズの「抱きしめたい」がこうした場面で引き合いに出されている例が見られないことである。キンクスの曲が出る前に、それと同じ系統のイントロを持っており、かつ同じタイトルでさえあるビートルズの曲の名前が出てもいいはずである。
さらに大瀧は、はっぴいえんど時代にはビートルズのネタを一切使わなかったと断言している[10]。そこには、最も有名なロックバンドであるビートルズの影響を取り入れなかったと言うことで、他の日本で当時活動していたロックバンドとの差別化を図っていたことを事後的に補強した後づけの言葉だとする見方もあり得ようが、ここには寧ろ、大瀧による影響関係を解説する言葉における戯れを見て取ることができるように思われる。
おわりに はっぴいえんどと東京ビートルズ
ビートルズの「抱きしめたい」が1964年2月に日本で発売されて以降、直ちに日本語でのカバーバージョンもいくつか発売された。そのうちの一つは1964年4月に東京ビートルズというグループの名で発売された。「抱きしめたい」を含む東京ビートルズの音源は1994年にCD化されて再発売されたが、そこで監修を手掛け、ライナーノーツに「東京ビートルズは何故生まれたか」という解説文を著したのは大瀧である。そこでは、明治期以降の日本のポピュラー音楽の展開を、外来のものをいかに取り込むかという一貫した課題のもとで、その時代ごとに具体的に異なる音楽様式を輸入し独自の解釈を施してきた過程として紹介し、その文脈において東京ビートルズを捉えている。「本物のロック時代への対処のないまま迎えたビートルズ・ブーム、ここに〈東京ビートルズ〉が抱えた〝状況的な〟悲劇があ」[11]ったのであり、歌はロックの情熱が空回り、バックでは涼し気なジャズの演奏というアンバランスな状況が生じた。こうした東京ビートルズの状況を解説したうえで、大瀧は「〈はっぴいえんど〉も70年代の〈東京ビートルズ〉そのものでした」[12]と述べている。これは第一には、はっぴいえんどもまた欧米の音楽をいかに取り込むかという、東京ビートルズと共通の課題に面していたのであり、その悪戦苦闘の記録(レコード)としてはっぴいえんどの録音物を聴くことができるというものであろう。
この東京ビートルズの「抱きしめたい」のイントロを聴くと、ジャズ編成のバックの演奏陣は、拍の裏表に関してはビートルズを正しく模倣し、裏拍から演奏が始まっている。それに対して歌の方は、歌いだしの「オー」がややフライング気味になっている。これは、演奏陣は拍の裏表のずれを正しく共有して演奏していながら、歌の方はこのずれに正しく乗りきれなかったことによるものと推察される。東京ビートルズもまた「抱きしめたい」のイントロには、図らずもではあるにせよ、演奏においてずれを孕んだものとなっている。リズムを意図的にずらそうとしなければ実現できないはっぴいえんどの場合と、東京ビートルズの「そうなってしまった」ずれの間には決定的な性格の違いがある。東京ビートルズとはっぴいえんどは、日本のポピュラー音楽史において同様の側面を見出すことができるが、欧米のロックとの関係において、リアルタイムでの生々しい記録としてのずれが生じた東京ビートルズと比較したとき、はっぴいえんどにはそうしたずれを演出する意識が見られるといえるだろう。
参考文献
高護(監修)『漣健児と60年代ポップス』シンコーミュージック、1998年。
萩原健太『はっぴいえんど伝説』シンコー・ミュージック、1992年。
萩原健太「大瀧詠一 インタヴュー」『はっぴいえんど HAPPY END BOX』プライムディレクション、2004 年、IOCD-40051~8 付属のブックレット、49-64頁。
大川俊昭、高護(編集)『定本はっぴいえんど』SFC音楽出版、1986年。
大瀧詠一、湯浅学「『大瀧詠一』ができるまで 『風街ろまん』、『大瀧詠一』、『Happy End』、そしてナイアガラ・レーベル始動を語る」『文藝別冊 大瀧詠一〈増補新版〉』河出書房新社、2014年、190-223頁。
大瀧詠一「東京ビートルズは何故生まれたか」、大瀧詠一『大瀧詠一 Writing & Talking』白夜書房、2015年、690-699頁。
堀内久彦『大滝詠一レコーディング・ダイアリーVol.2』リットーミュージック、2022年。
音声資料
細馬宏通、安田謙一『しりすぎてるうた “抱きしめたいのすべて”』NHK-FM、2019年12月29日放送[ラジオ]。
Notes
-
[1]
萩原健太「大瀧詠一 インタヴュー」『はっぴいえんど HAPPY END BOX』プライムディレクション、2004 年、IOCD-40051~8 付属のブックレット、58頁。
-
[2]
細馬宏通、安田謙一『しりすぎてるうた “抱きしめたいのすべて”』NHK-FM、2019年12月29日放送。高護(監修)『漣健児と60年代ポップス』シンコーミュージック、1998年、33頁。
-
[3]
大川俊昭、高護(編集)『定本はっぴいえんど』SFC音楽出版、1986年、136頁。
-
[4]
『はっぴいえんど ライヴ・ヒストリー〜レアリティーズ〜 VOL.2』プライムディレクション、2004 年、IOCD-40056 に収録されている。
-
[5]
The Beatles, Live At The Hollywood Bowl, 2016.
-
[6]
萩原健太『はっぴいえんど伝説』シンコー・ミュージック、1992年、44-48頁。
-
[7]
萩原健太「大瀧詠一 インタヴュー」前掲書、58頁。
-
[8]
大瀧詠一、湯浅学「『大瀧詠一』ができるまで 『風街ろまん』、『大瀧詠一』、『Happy End』、そしてナイアガラ・レーベル始動を語る」『文藝別冊 大瀧詠一〈増補新版〉』河出書房新社、2014年、194頁。
-
[9]
堀内久彦『大滝詠一レコーディング・ダイアリーVol.2』リットーミュージック、2022年、100頁。
-
[10]
大瀧詠一、湯浅学、前掲書、203頁。
-
[11]
大瀧詠一「東京ビートルズは何故生まれたか」、大瀧詠一『大瀧詠一 Writing & Talking』白夜書房、2015年、696頁。大瀧は筆名に厚家羅漢の名義を使っている。
-
[12]
同上、698頁。
この記事を引用する
安倍拓真「はっぴいえんどと(東京)ビートルズ──「抱きしめたい」のイントロを聴く」『Phantastopia』第4号、2025年、53-59ページ、URL : https://phantastopia.com/4/happy-tokyo-beatles/。(2026年02月04日閲覧)