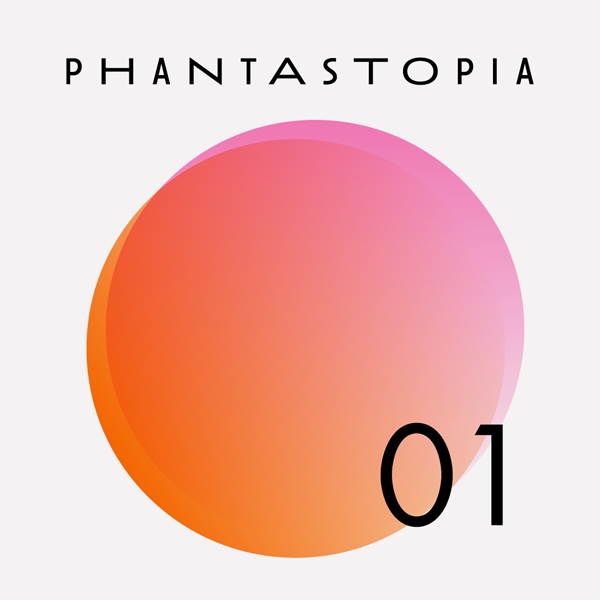序
1963年頃に東映で製作された一群の時代劇映画を山根貞男は「集団時代劇」と呼び、文字通り暗い調子の画面、苛烈な暴力性を伴った独特の魅力をそこに見出した[1]。そうした作品群に先んじて、大映の時代劇においても陰影の深い画面に特徴づけられた、死や暴力を題材に積極的に導入した作品傾向を山根は指摘している[2]。
山根に限らず、これまでの言説は総じて、1960年代に時代劇映画の衰退が進むなかで、作品傾向の転換が起き、残酷表現への傾斜が強まったことを述べている[3]。
本稿では、「明るい」時代劇が主流だった時期とは、同時に極端に「暗い」怪談映画というサブジャンルが根を張っていた時期でもあるという、従来注目されてこなかった枠組みを示したうえで、「明るい」主流の時代劇が失効する過程で模索された集団時代劇の「暗さ」には怪談映画との連続性を認めることができることを、『十三人の刺客』などを例に示す。
1.集団時代劇というカテゴリ
山根貞男は、1963年前後に現れた東映が製作する時代劇映画が登場人物の集団性に重きを置いた新たな潮流を形作っていたことについて、次のように述べる。
「集団時代劇」といっても、そんなジャンルが明確にあるわけでも、ちゃんとした定義があるわけでもない。ときには「集団抗争時代劇」とも、「集団残酷時代劇」とも呼ばれることがある。六三年一二月、工藤栄一監督『十三人の刺客』が出現したとき、ラストのえんえんと長い凄惨な殺陣が多くの人に衝撃を与え、ジャーナリズム上にそうした呼称が生まれたのであろう。[…]
ともあれわたしとしては、「集団」という点にアクセントを置いて、「集団時代劇」と呼ぶことにしよう。むろんそこには、集団による残酷な抗争ドラマであることも含まれている。だから、いくら群衆チャンバラ場面が売りものになった作品でも、その大殺陣がしょせん彩りでしかなく、本質的には昔ながらの明朗なヒーロー劇である場合には、集団時代劇としては取り扱わない。[4]
山根は続けて、集団時代劇はそれまでの時代劇で人気を博した「人気スターによるヒーローが不可能」となったがゆえに複数の俳優を組み合わせる集団劇に活路が見出されたこと、そして集団時代劇が「一言でいって、きわめて陰惨であり、見た者に爽快感をもたらすどころか、陰鬱な気分だけをひたすら与える」と述べる[5]。山根はそのように規定しながら、以下の作品を集団時代劇としてみなす。すなわち1963年に公開された『柳生武芸帳 片目の忍者』(松村昌治監督)、『十七人の忍者』(長谷川安人監督)、『十三人の刺客』(工藤栄一監督)、『江戸忍法帖 七つの影』(倉田準二監督)、1964年に公開された『大殺陣』(工藤栄一監督)、『十兵衛暗殺剣』(倉田準二監督)、『集団奉行所破り』(長谷川安人監督)、『幕末残酷物語』(加藤泰監督)、『十七人の忍者 大血戦』(1966、鳥居元宏監督)そして『十一人の侍』(1967、工藤栄一監督)である。集団同士の争いを題材としている『大喧嘩』(1964、山下耕作監督)と『大勝負』(1965、井上梅次監督)は既に引用したような理由から、このカテゴリから外されている。山根によると、集団時代劇には独特の魅力があり、それは「集団による死闘、積み重ねられてゆく員数としての死」であり、そこでなされる「死との戯れ」に「陰鬱な活劇性」を見出すがゆえに高く評価するのだが、それは1960年から64年の日本社会の「転形期」という時代と深く結びつけられるのだという[6]。
山根によれば、集団性が陰鬱で残酷な印象と結びつくのは、作中でチャンバラとしてあらわれる苛烈な争いを戦う一人ひとりの人物が、単なる「員数」に過ぎないという突き放した視線ゆえということになる。これは、黒澤明の『用心棒』(1961)以降強まった「リアリズム」の追求が、無敵の剣豪といったジャンルの約束事を取り払い、スター俳優も含めて彼らの演じる身体が痛みや死に対してさらされるという繰り返し語られてきた図式を補う論点である。
2.集団と空間の合理化という主題
集団時代劇のなかでも特に『十三人の刺客』と『十七人の忍者』に関しては、山根の述べるような集団のあり方を空間の表現と結びつけて「合理化」に着目して分析することで、ジャンル全体の転換期を理解する手がかりを得ることができる。
『十七人の忍者』では、幕政の転覆を企てる駿河公徳川忠直が傘下の大名から集めた連判状を奪取する任務が下されると、伊賀忍者甚伍左(大友柳太郎)は配下の忍者たちを集め、任務の説明を行う。3分以上続くこの場面では、目的の共有がなされたうえで3~4人の下位集団への分節を通して甚伍左を含む伊賀三ノ組の17名は再編成される。甚伍左は事務的ともいえる淡々とした調子で、忍者たちの名前を呼び、呼ばれた者は甚伍左の前へ出て、駿河への侵入経路を指示され、それぞれ旅支度を仕上げて目的地へ向けて出発していく。次郎長一家や忠臣蔵の浅野家遺臣のように[7]、イエ的に結合している集団が一丸となって敵に向かうのと比べて、相対的に構成員それぞれが自律的で、目的に即して分散した作戦行動―アクションとして画面にあらわれる―が可能であることが示される。
『十三人の刺客』では、集団が合理的に再編成される描写が『十七人の忍者』ほどあからさまではないように見えるが、明石藩主の暗殺という任務に向けて、責任者である島田新左衛門(片岡千恵蔵)が配下の者から適格な侍を招集する過程が描かれる。
こうしたシークエンスをある程度抽象するならば、1954年に公開された黒澤明の『七人の侍』に同型のものを見ることができる。しかし、『七人の侍』では戦国時代にフリーランスの侍たちが偶然の出逢いを介して集まるのに対して、『十七人の忍者』と『十三人の刺客』では計画の実行部隊が幕府の組織を基盤として(再)編成されており、『七人の侍』と比べて集団内の力関係が明白で、また人数の多寡が違うこともあり、成員の個別性の印象が弱く、登場人物たちは「員数」としての性質をより強く帯びることになる[8]。
このような集団の合理化にくわえて、彼らが用いる地図が丁寧に撮られることで、任務を遂行する集団が、標的とする場所をいかに合理的に認識しているかが明らかにされる。『十三人の刺客』では、島田新左衛門らが国元へ江戸から向かう明石藩主を殺害するための場所を中山道の宿場落合宿に設定するが、彼らは複数の街道の地図をみながら戦略を練る。そして、明石藩の一行を罠にかけるために土木工事によって落合宿に手を加えるにあたり、宿場の地図が活用される。さらに実際の戦闘が行われるシークエンスでは、島田新左衛門は参謀役の倉永(嵐寛寿郎)とともに安全地帯で宿場の地図を眺めながら現場の報告を受け、戦闘の推移に沿って命令を下す。『十七人の忍者』においても、忍者たちが忍び込む駿府城の地図が提示され、作中で焦点となる本丸と櫓などの位置関係が明瞭に見せられる。映画を見る者にとって、こうした地図のショットを通じて、舞台となる場所の空間的な位置関係と階層性が明らかにされる。さらに観客は、地図をみることを介してチャンバラ活劇とその舞台となる場所の関係を必然的で密接なものとして感じるとともに、地図に描かれている場所とその外部の遮断を自然に受け入れ、落合宿や駿府城を閉じた場所として認識するようになる。このような形で、空間の合理化は、リアリズムの要請に応えながら、『十三人の刺客』と『十七人の忍者』がともに人工的な構築物と人物たちの相互作用をめぐってアクションを展開することを支える。前者では、大勢の侍たちを閉じ込め、分断し、彼らを少数の刺客たちが一方的に殺害することを大規模に土木工事を施された宿場町が可能にし、後者では、高い石垣を忍者が上り、床に穴を開けたり暗がりに潜んだりしながら、堅固に守られた櫓に潜入し、城中奥深くで守られている連判状に向けて忍者たちが進んでいく。つまり、二本の映画では場所が単なるアクションの舞台ではなく、任務遂行の道具あるいは障害として存在し、場所と人間の相互作用が前景化される。そのような状況が描き出されるにあたり、集団と空間の双方が合理化されるのだ。
3.時代劇映画のジャンル構成
時代劇の重要なサブジャンルである怪談映画に関してもまた、昭和三十年代後半には製作本数の急速な減少がみられる。敗戦後、占領政策の変化を受けて、1952年7月に大映が『怪談深川情話』(犬塚稔監督)を公開したのを皮切りに、夏のお盆の時期に怪談映画を公開するという慣行を映画会社各社は維持していたが[9]、そうした慣行は昭和三十五年(1960)以降途切れていく。大倉貢が率いた新東宝は、1956年以降毎夏怪談二本立て興行をおこない[10]、一年に3本から4本と熱心に怪談映画を公開していたが1961年に倒産する。それ以降、怪談映画の減産が進み、1955年から毎年1本は怪談映画を公開していた東映でも1960年にその流れが途切れる。1961年に加藤泰が監督した『怪談 お岩の亡霊』、翌62年に『怪談 三味線堀』(内出好吉監督)を出すが、それ以降1968年に『怪談 呪いの沼』を公開するまで怪談映画の製作には手を付けていない[11]。戦後怪談映画をいち早くリードした大映は、1963年6月公開の『怪談 鬼火の沼』以降は1968年6月公開の『牡丹灯籠』(山本薩夫監督)まで怪談映画の製作を止めている。したがって、正確にいえば1963年から1968年の5年間は怪談映画にとって文字通りの冬の季節といってよいのだが、そのことは戦前からのスター俳優によるシリーズものの時代劇が同時期に終了を迎えていったことと関係づけて考えるべきだと思われる。
1963年1月に東映の市川右太衛門主演の『旗本退屈男』シリーズが『謎の龍神岬』(佐々木康監督)で終了し、同年5月に公開された『江戸無情』(大映、西山正輝監督)を最後に長谷川一夫が映画界から退いた。これらに先立ち、1962年2月に片岡千恵蔵が遠山金四郎を演じる『奉行』シリーズの最終作『さくら判官』(小沢茂弘監督)が公開されている。これらは山根貞男がいうところの〈勧善懲悪パターンの活劇〉といえ、そうしたパターンの図式の乱れを集団時代劇の流れに山根は見て取っている[12]。「神通力」と山根がいったようなスターイメージの力が失われていったこととあわせて考えると[13]、映画の内容と、映画と観客を媒介するスターイメージの双方で働いていた、合理的には説明できないような力が減衰していったことが推察される。前者は映画ジャンルをめぐって観客と映画の作り手が共有する慣習および本物らしさと関わっており、後者はエドガール・モランの論じたように、映画スターとそのファンの関係に認められる宗教的ともいえる熱狂と関わる。モランは1950年代から1960年代にかけて西側諸国のメディア空間での映画の位置が変化するにしたがってスター・システムが衰退したことに注目し、「スターはなるほど見世物的映画では勝利しているが、もはやそこでは、前時代のような神話的総合を行うことはできないでいる」と述べているが[14]、これは日本映画についても当てはまるように思われる。怪談映画と絶対的な権威を帯びたスター俳優たちのシリーズものの双方の衰退は、映画作品そのものとスター俳優たちと観客の関係によって成立する時代劇映画の表象システムが合理化に屈していく過程を構成していたのではないか。
言い換えれば、1960年から65年頃にかけてスター・システムの主軸をなしていた、いわば王道の時代劇が作られなくなると同時に、怪談映画もまたいったん存立の余地を失うのだ。広範な目配りと、具体的なテクストの分析なくしてその理由を明らかにすることはできないため、ここでは端的に歴史的な現象として指摘するにとどめるが、昭和三十年代前半に築かれた時代劇映画の製作興行システムにおいては、〈勧善懲悪パターンの活劇〉と怪談映画は表裏一体といってよい二極を形作っていた。怪談映画は、〈勧善懲悪パターンの活劇〉が排除するエロチシズムと残酷を一手に担いながら、支配的な時代劇映画では悪を成敗するはずの剣技が、女性や病人、老人など身体的にも社会的にも弱い立場の人間を惨たらしく殺害し、亡魂を招来する事態を繰り返し提示し続けたのだ。
したがって昭和三十年代とは、お盆を一つの区切りとする歳時的なサイクルのもと、既に述べたような二極を通して、勧善懲悪の規範、性と暴力といった要素を整理し、なおかつそれらを相補的なかたちで観客に提供する時代劇の安定的なシステムの形成と崩壊の過程として理解することができる。
そのシステムの崩壊過程に特有の現象として、〈勧善懲悪パターンの活劇〉と怪談映画的なものの混淆が『十三人の刺客』において認められることをここで明らかにし、本稿を締めくくる。
4.『十三人の刺客』における血と闇
山根は、『十三人の刺客』の大半が昼のシーンで構成されており、「白昼」にチャンバラがおこなわれることを強調している[15]。しかしながら、山根の批評が後半のチャンバラに焦点を絞りこんでいることと関わっているのだが、この記述は不正確と言わざるを得ない。実のところ、本作の前半では夜のシーンが続き、その画面の暗さは、「白昼」にチャンバラが繰り広げられる後半との視覚的な対比関係を生んでいる。
冒頭のショットは、「弘化元年九月五日早朝…」というナレーション(声は芥川隆行)を伴いながら平明な画面で、切腹して果てている明石藩家老が提示されることで、出来事の発端と帰結(落合宿での松平斉韶暗殺)を、白昼でのアクションの展開という一つの連続的な相に統合することに寄与している。しかし、それに続く江戸でのシークエンスすなわち江戸城内での老中たちの密議、老中土井(丹波哲郎)邸内での島田新左衛門への情報共有と密命の下知、そして松平斉韶の暴虐を語る牧野靭負(月形龍之介)の回想シーンではモノクロームの黒を高度に活用した暗い画面構成が続き、特に松平斉韶が木曽上松の本陣で靱負の義娘を凌辱し、その夫を殺害するシークエンスでは、不可視なほどの黒い闇が画面上に広がり、奥行きの深い画面構成とあいまって、冒頭の平明かつ平面的な画面と著しい対照をなしている。
両者は、明石藩家老間宮の遺骸から流れ出た大量の血液の黒さによって冒頭のショットと媒介されている。本作に限らず、モノクロームのフィルムが流血を本物らしく見せることを『椿三十郎』が鮮やかに示したという言説はこれまで繰り返されてきたが[16]、そうした迫真性に支えられながら、どす黒い血だまりはその血を流した者の苦痛を指し示しつつ、白砂に支配された平明な画面にあって際立ってその異質さを印象づける。
その異質さは、画面上半分を占める巨大な門が武家の格式と権威を誇示する空間に投げ込まれた猟奇と怨念の世界すなわち怪談的なものへの糸口たり得ているように思われる。モノクロームで撮られた血だまりの黒は、夜の闇の黒と呼応する。続く牧野の回想シーンは、深い奥行きの暗い画面構成を活かしながら、犠牲者―怨念―因果応報という伝統的な怪談の主題の系列へと、我々の想像力を誘うとともに、白昼に繰り広げられる死闘と要人暗殺という顛末が、この前半に流された血と夜の闇によってもたらされることをも理解させる。
参考文献
石塚洋史「東映集団時代劇と近衛十四郎」『映像学』第73巻、日本映像学会、2004、66-83頁。
大澤浄「新東宝のお化け映画と『東海道四谷怪談』」内山一樹 編『怪奇と幻想への回路 : 怪談からJホラーへ(日本映画史叢書 ; 8)』森話社、2008、67-99頁。
小川順子『「殺陣」という文化』世界思想社、2007。
筒井清忠『時代劇映画の思想』PHP研究所、2000。
永田哲朗『殺陣 チャンバラ映画史』社会思想社、1993。
エドガール・モラン『スター』渡辺淳、山崎正巳訳、法政大学出版局、1976。
山根貞男『活劇の行方』草思社、1984。
Notes
-
[1]
山根貞男『活劇の行方』草思社、1984、128-130頁。
-
[2]
山根によると(大映の時代劇映画の)「変貌もしくは新展開は、一口にいって、単純に明朗な勧善懲悪パターンの古典的チャンバラ映画の超克として行われた」。同書、94頁。
-
[3]
小川順子『「殺陣」という文化』世界思想社、2007、70頁。筒井清忠『時代劇映画の思想』PHP研究所、2000、96-97頁および永田哲朗『殺陣 チャンバラ映画史』社会思想社、1993、243-248頁。
-
[4]
山根前掲書、127-8頁。
-
[5]
同書、128頁。
-
[6]
同書、159頁。
-
[7]
いずれも、東映時代劇が正月などのオールスターが出演する企画で題材としてきた。
-
[8]
『十三人の刺客』においては、武士の道を半ば放棄し放蕩暮らしをする新六郎(里見浩太朗)が叔父の島田とのやりとりを通じて、任務への参加を決意し、武士として生きる道を選び取る場面が挿入され、主体性をめぐる実存主義的な契機が混入する。このくだりは、全体が無個性な集団として目的合理性に埋没することを避けるとともに、里見浩太朗というスター俳優が演じる新六郎を他の多くの登場人物から際立たせる機能を果たしている。
-
[9]
いわゆる関東お盆にあわせて七月に公開することも多く、夏の間配給できるようしていた。
-
[10]
大澤浄「新東宝のお化け映画と『東海道四谷怪談』」内山一樹 編『怪奇と幻想への回路 : 怪談からJホラーへ(日本映画史叢書 ; 8)』森話社、2008、69-70頁。
-
[11]
1965年8月に東京撮影所が製作した佐藤肇監督の『怪談 せむし男』が公開されているが、これは時代劇ではなく、現代劇のホラーというべきであろう。
-
[12]
山根貞男前掲書、21頁および30-33頁。ただし山根は現代劇を含む東映映画全体の特徴として〈勧善懲悪パターンの活劇〉をあげている。ここでは、東映に限らず大映や松竹を含む京都の時代劇映画における支配的なフォーマットである捕物帖のシリーズに山根の端的な指摘が幅広くあてはまるものと認め、適用範囲を敢えて広げた。なお、松竹は高田浩吉の『伝七捕物帖』(1954-1959)、大映は長谷川一夫の『銭形平次捕物控』(1949-1961)があり、また嵐寛寿郎は松竹、新東宝、東映、東宝で戦前から人気だった『鞍馬天狗』シリーズ(1950-1956)に出演している。
-
[13]
山根前掲書、32頁。
-
[14]
エドガール・モラン『スター』渡辺淳、山崎正巳訳、法政大学出版局、1976、189頁。
-
[15]
「全篇、夜のシーンがほとんどないに等しい」と山根は述べている。山根前掲書、148頁。
-
[16]
石塚洋史「東映集団時代劇と近衛十四郎」『映像学』第73巻、日本映像学会、2004、69頁。
この記事を引用する
藤田奈比古「集団時代劇と怪談映画の関係──『十三人の刺客』と『十七人の忍者』をめぐって」『Phantastopia』第4号、2025年、36-43ページ、URL : https://phantastopia.com/4/13assasins/。(2026年01月29日閲覧)