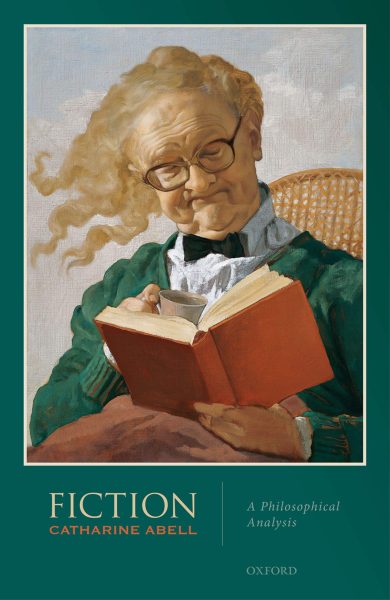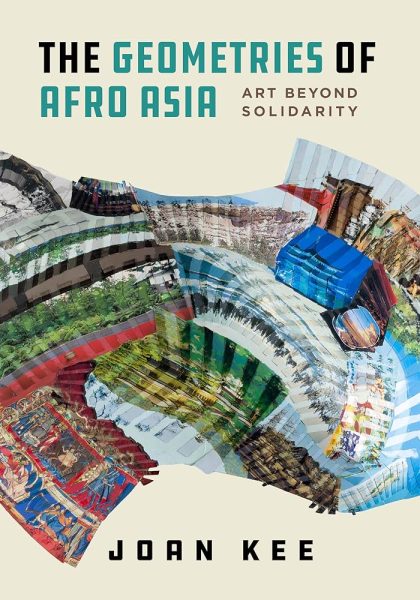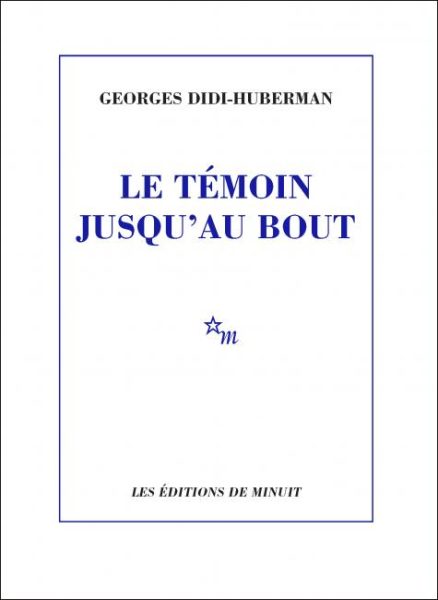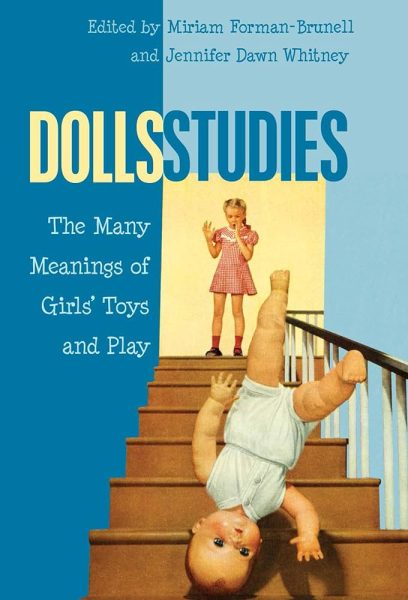私たちが自身の生について考えを巡らすとき、そこに「習慣」についての思考が含まれないことなどほとんどあり得ないと言ってよい。改めて考えてみると、私たちは実にさまざまな習慣のうちに置かれている。寝起きの時間、歯磨き、お風呂で体を洗う順番、いつも通る道、包丁の使い方、スーパーの売り場を巡る順番、何かを思考するときについつい当てはめてしまう図式、応答のさいに口をついて出てくるフレーズ、等々、数え上げればきりがないだろう。しかし一言に習慣とはいっても、その内実にはさまざまなグラデーションを見出すことができる。生きていくなかでおのずから身につけた習慣もあれば、スポーツ選手がしばしばやるように意識的に獲得されたルーティンのようなものも習慣と呼べる。さらには、ついやってしまう「くせ」なども習慣のカテゴリーのうちに含めることができるだろう。こうした内実に従って、習慣は獲得が望まれるものであったり、逆に廃棄すべきものであったりと、さまざまな価値づけを受けることになる。このように、ときに正反対の性質を併せ持つ「習慣」という主題について、過去の哲学者たちの思想を経巡りつつ検討しているのがここで紹介する『習慣について(On Habit)』(2014)である。
著者のクレア・カーライル(Clare Carlisle, 1977-)は2022年現在、ロンドン大学キングス・カレッジで哲学教授の職にある哲学者である。彼女の専門は神学および哲学、特にキルケゴールやジョージ・エリオットを中心にした19世紀の哲学、またスピノザを中心にした近世哲学であり、本書の主題でもある習慣や宗教生活、瞑想などの主題についても哲学的な思索を行っている。すでに6冊の著書があり、『習慣について』のほかにも『キルケゴールの「おそれとおののき」(Kierkegaard’s ‘Fear and Trembling‘)』(2010)、『スピノザの宗教(Spinoza’s Religion)』(2021)などが出版されている。またフェリックス・ラヴェッソンの『習慣論(De l’habitude)』(1838)の英訳を2008年に出版するなどの翻訳活動も行っている。
ここで紹介する『習慣について』はラウトレッジ社の「シンキング・イン・アクション(Thinking in Action)」シリーズの一冊として刊行されたものである。同シリーズは、現代におけるさまざまな主題について、国際的に活躍する哲学者たちが平明にしかし鋭く紹介するという方針で編まれているものであり、すでに32冊が刊行されている。邦訳もすでに数冊存在する[1]。また、邦訳はないものの、ジャック・デリダによる『コスモポリタニズムと赦しについて(On Cosmopolitanism and forgiveness)』(2001)やポール・リクールによる『翻訳について(On Translation)』(2006)などもシリーズの一冊としてよく知られている。このシリーズに含まれる図書は、現代哲学における議論への入門書として重要な地位を与えられていると言えるだろう。
カーライルは、習慣を見ることの難しさを確認するところから議論を開始している。私たちは自分がどのような習慣をもっているかを比較的容易に把握することができるが、一方で、習慣がいったいどのようなものであるのかを考え始めると途端に困難と出会うことになる。それは習慣がその親密性や反復されるという性質によって、私たちの理性や感覚を鈍らせるものであるからである。習慣のうちに生きつつ、習慣それ自体について思考することは極めて難しいと言えるだろう。
上で述べたように、習慣はまず思考の力を鈍らせるものとして捉えることができる。こうした理由から哲学者たちはしばしば、習慣を打ち破って思考することの重要性を強調してきた。例えばプルーストは習慣を、私たちから世界や私たち自身を隠してしまう「鉄のカーテン」に譬え、真理の探究のさいには破られるべきものとしてみなしていた。ソクラテスの問いかけやデカルトの懐疑、ハイデガーの特異な語法などは、思考における習慣との闘いのうちで生み出されてきた一つのわざであると捉え直すことができる。
しかし、一方で習慣がなくては思考することすら叶わなくなってしまうと考える哲学者もいた。反復によって成立する「連合」を重視したヒュームや、ヒュームを引き継いで主体と習慣のとりもつ関係を強調したドゥルーズなどがその一例である。彼らの思索を経ずとも、言語的な習慣がなくては思考が不可能であり、文字を書く習慣やタイピングの習慣を獲得していなくては思考を形成することはできないということはすぐに理解できる。また、習慣がなくては全てを即興で行わなくてはならないことになり、そのような世界は「耐え難い」ものとして現れるに違いない。ニーチェはここから、「束の間の習慣」の重要性を説いていた。
カーライルは、数々の哲学者たちの習慣についての議論を、以下の2つの解釈ラインに整理することができると論じている。
- 習慣を、反省的思考への障害や自由への脅威であるとみなす解釈。この立場の人々は、習慣とは生の格下げであり、自発性や生命力を機械的なルーティンへと縮減してしまうものであると考える。
- 習慣を、私たちに秩序をもたらし、さらに私たちを創造的で自由な存在にしてくれるものであるとみなす解釈。この立場の人々は習慣を、私たちが「些細なものごと」から解放されるための手段であるとみなす。また、共有された習慣が私たちを共同体へと引き入れるのであり、従って習慣は倫理的・宗教的生の基礎をなしていると主張する。
習慣についての言説の多くは、おおよそこの2つの解釈ラインに振り分けることができるが、重要なのはどちらかの解釈に軍配をあげることではなく、むしろ習慣というものにはそもそもこれら2つの側面が同時に備わっているとみなしたうえで思考を進めることである。最初の解釈は人間の本性を「変化」に求め、習慣を人間の自動化あるいは機械化とみなして批判する。一方で第二の解釈は、「恒常性」の確立によってこそ人間的な生は営まれうると考え、良き習慣の確立を志向することになる。
しかし、必ずしも第一の解釈の人びとが一切の習慣を放棄せよと言うわけでもなければ、第二の解釈の人びとも一切の変化を拒否するわけではない。そもそも習慣がなければ「変化」を唱えることはできないし、また変化がなければ習慣の「形成」など不可能であるからだ。カーライルは以下のように述べている。「習慣の原理は、恒常性と変化の両方(both constancy and change)を含んでいる。」(p.17)この原理は、本書において「受容性と抵抗(receptivity and resistance)」、「可塑性(plasticity)」などと言い換えられつつ何度も反芻されている。一方で習慣は存在の「かたち」を形成し、保持することでその同一性を保つ役割を果たすが、他方で習慣は、私たちが自身の行為や経験によって変様されうることによって初めて形成されうるものである。アリストテレスやラヴェッソンの言うように、石は習慣をもちえない。石は変化しないかたちをつねにすでに有している一方で、自らの外部の変化に完全に従属しているという意味で、二重に習慣から疎外されているのである。
カーライルは以上の議論を「習慣の二重法則(double law of habit)」として整理し、提示している。これはジョセフ・バトラーが見出し、ラヴェッソンが発展させた用語であり、私たちを単なる自然法則から切り離して固有の同一性を与える「薬」であると同時に、しばしば取り返しのつかない中毒をもたらす「毒」でもある習慣の両義的な本性を示している。
彼女は本書第1章「習慣の概念」においてこの法則を提示し、第2章「習慣と知」、第3章「習慣と善き生」、第4章「習慣、信仰、恩寵」、結論「習慣と哲学」ではこの法則を適用しつつ、知や善き生、信仰/恩寵、哲学と習慣との関係について検討している。
こうした一連の議論においてとりわけ重要なのは、彼女が「実践」と呼ぶ習慣の形態についての議論である。習慣には非反省的な習慣と反省的な習慣を区別することができる。前者はおのずから身に着いた習慣であり、後者は意識的に身に着けた習慣であると言える。カーライルは前者を「ふつうの習慣(ordinary habit)」、後者を「実践(practice)」と呼ぶことで区別を試みている。実践とは意図的に発展させられた習慣であり、それは何よりもある行為によって自身の受容性と抵抗のあり方、すなわち何を変化として受け入れ、何を拒絶するのかという線引きのあり方そのものを変化させるような営みである。例えば、スポーツの練習とは、たんなる日常生活では身に着かない特定の動きを反復によって体に覚えさせつつ、それ以外の余計な動きを排除していく営みであろう。そしてスポーツが上達するとは、こうした受容-排除の機制を反省しつつ、洗練させていくことを意味する。スポーツとはこの意味で「実践」の重要な範例をなすものである。このような実践においてこそ、私たちは自らの生を導くことが可能になるのである。「人間の習慣とは必ずしも本性の固定化ではなく、むしろその変様、あるいは霊性化(spiritualization)ですらあるのだ。」(p.135)
カーライルは習慣を「小径(pathway)」に譬えている。私たちは繰り返し踏みしめることで道を作り、保ち、ときに新たな道を作るべく荒野へと踏み出していく。こうした道はまた次に通る人々を導くものである。この比喩には、習慣の創造性と保守性が同時に含まれているだろう。本書の最も重要な主張の一つは、人間の倫理性や自由を、特定の習慣のあり方や自由の類型の自身への適用のなかでも、また習慣からの完全な解放の下での営みのなかにでもなく、自身の習慣についての不断の反省と変様可能性の模索というダイナミックな「実践」のうちに位置付けたという点にある。一見すると保守的であるとすら言えるこうした主張のうちにこそ、「伝統」なるものに固執する旧弊な生き方とも、また一切の慣習を拒否する究極的に自由な生といった理想的な形象とも別の、ラディカルな議論の可能性が備わっているのではないか。
註
-
[1]
スラヴォイ・ジジェク『信じるということ(On Belief)』(原著2001年;邦訳2003年、松浦俊輔訳、産業図書)、ヒューバート・L・ドレイファス『インターネットについて:哲学的考察(On the Internet)』(原著2001年;邦訳2002年、石原孝二訳、産業図書)、シャンタル・ムフ『政治的なものについて:ラディカル・デモクラシー(On the Political)』(原著2005年;邦訳2008年、酒井隆史監訳、篠原雅武訳、明石書店)、ノエル・キャロル『批評について(On Criticism)』(原著2008年;邦訳2017年、森功次訳、勁草書房)、セオドア・グレイシック『音楽の哲学入門(On music)』(原著2013年;邦訳2019年、源河亨/木下頌子訳、慶應義塾大学出版会)が現行で存在するシリーズの邦訳である。